劣化対策等級とは?1〜3の基準や確認方法、証明書の取得方法も紹介

目次
一建設の分譲戸建住宅
一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度5分野7項目の最高等級取得を標準化。
お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。
住宅の性能を数値や等級で示す「住宅性能評価」項目のうち「劣化対策等級」とは、具体的に住宅のどのような性能を評価しているのでしょうか?
今回は、劣化対策等級1〜3の評価基準や耐用年数を木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造別に紹介します。また、劣化対策等級の証明書の取得方法や確認方法、申請費用の相場、取得によるメリットなども紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
1. 劣化対策等級 とは
劣化対策等級とは「建物の耐久性を評価するための基準」のことで、住宅性能表示制度における性能表示事項の一つです。
柱や梁といった、住宅の建築において主要な材料となる「構造材」に対し、どの程度の劣化軽減対策を施しているかを調査します。
等級は1〜3に分かれ、数字が大きいほど、より耐久性が高くより長い耐用期間を確保できることを表しています。劣化対策等級3は、最も高性能な劣化対策を施されていることを示し、取得することで長期優良住宅認定を受けることも可能です。
各等級の評価基準や耐用年数に関しては、後述の「2.劣化対策等級1〜3別の基準・耐用年数」を参考にしてください。
ちなみに住宅性能表示制度とは、消費者が住宅の性能を比較して購入を検討できるよう設けられた、「国土交通大臣の定めた基準のもと、第三者機関によって住宅の性能を客観的に評価・表示する」制度です。10分野34事項の性能表示事項から成り立っています。
1.1. 劣化対策等級 の取得方法
劣化対策等級は、住宅性能表示制度の性能表示事項のうち「劣化の軽減に関すること」の分野に該当する評価項目です。
取得方法は住宅性能表示制度の仕組みに基づいて、登録住宅性能評価機関に住宅の性能評価を申請し、住宅性能評価書を交付してもらう必要があります。
住宅性能評価書には「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があり、それぞれ10万円〜20万円ほどの申請費用が必要です。
具体的な評価基準や住宅性能評価書の作成方法は、後述の「3.劣化対策等級の評価基準【住宅構造別】」や「4.劣化対策等級の証明書はある?確認方法は?」を参考にしてください。
2. 劣化対策等級1〜3別の基準・耐用年数
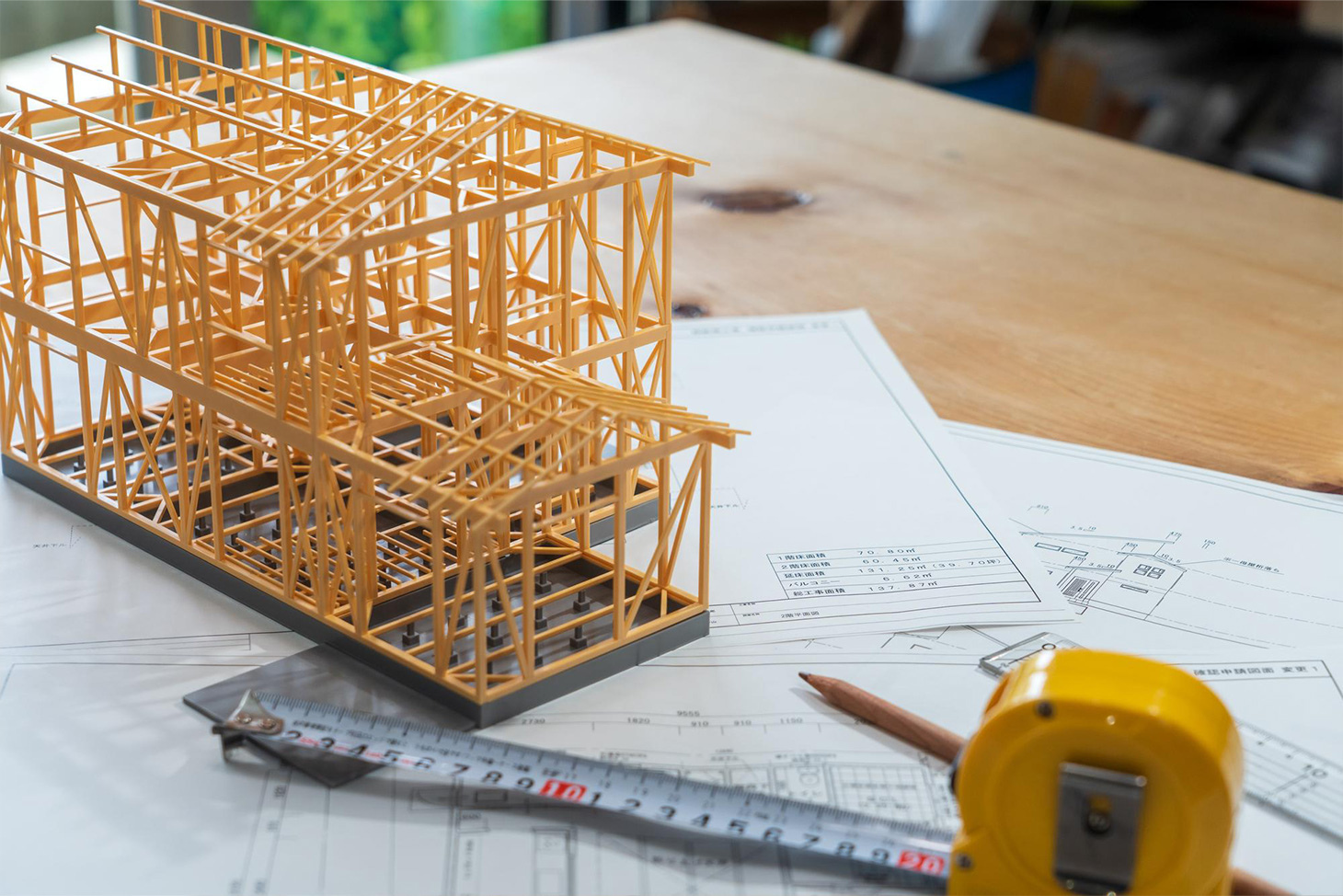
先述しているように、劣化対策等級は対策の程度に応じて1〜3の等級が設けられており、数字が大きいほど性能の高さを示しています。
劣化対策等級1〜3の評価基準や耐用年数をそれぞれ下記のとおりです。
2.1. 劣化対策等級1
| 評価基準 | 建築基準法に定められた程度の対策がされている。 |
|---|---|
| 耐用年数 | 法令により定められている住宅の耐用年数は25~30年。 |
2.2. 劣化対策等級2
| 評価基準 | 通常想定される自然条件および維持管理の条件のもと、2世代までは大規模な改修工事が不要になるよう対策されている。 |
|---|---|
| 耐用年数 | およそ50〜60年。 |
2.3. 劣化対策等級3
| 評価基準 | 通常想定される自然条件および維持管理の条件の下で、3世代までは大規模な改修工事が不要になるよう対策されている。 |
|---|---|
| 耐用年数 | およそ75〜90年。 |
3. 劣化対策等級の評価基準【住宅構造別】
建築に使用する材料によって劣化の原因や対策方法が異なるため、劣化対策等級の評価基準の内容は住宅構造によって異なります。
「木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造」の住宅構造別に、劣化対策等級1〜3の評価基準を解説します。
また、それぞれの住宅構造の特徴を知りたい方は、下記記事で解説しているのでぜひ参考にしてください。
>>木造と鉄筋・鉄骨の違いは?メリットやデメリットを解説
3.1. 木造
木造住宅では、主に、木材を腐食させる「シロアリ」や「腐朽菌」への対策を劣化対策等級の評価基準にします。等級1〜3別の評価基準は以下の通りです。
3.1.1. 劣化対策等級1
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.1.2. 劣化対策等級2
- 外壁の軸組などの防蟻・防腐処理
- 土台の防蟻・防腐措置
- 浴室および脱衣室の防水措置
- 地盤の防蟻措置
- 地盤から基礎の高さの確保
- 床下の防湿・換気措置
- 小屋裏の換気措置
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.1.3. 劣化対策等級3
- 外壁の軸組などの防蟻・防腐処理
- 等級2に記載の「土台、浴室および脱衣所、地盤、基礎、床下、小屋裏」に関する基準への適合
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.2. 鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造住宅では、主に、「鉄筋のサビ」や「コンクリートの品質維持」への対策を劣化対策等級の評価基準にします。等級1〜3別の評価基準は以下の通りです。
3.2.1. 劣化対策等級1
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.2.2. 劣化対策等級2
- 使用するセメントの種類
- コンクリートの水セメント比
- 施工誤差を考慮した部材の設計・配筋
- コンクリートの品質の適合
- 施工計画における指定事項
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.2.3. 劣化対策等級3
- 等級2への適合(ただし、コンクリートの水セメント比の数値は低くなる)
3.3. 鉄骨造
鉄骨造では、主に、サビによる腐食・劣化対策を劣化対策等級の評価基準にします。等級1〜3別の評価基準は以下の通りです。
3.3.1. 劣化対策等級1
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.3.2. 劣化対策等級2
- 鋼材の防錆措置
- 床下の防湿・換気措置
- 小屋裏の換気措置
- 構造部材などの基準法施行令規定への適合
3.3.3. 劣化対策等級3
- 構造躯体の防錆措置
- 等級2に記載の「床下、小屋裏」に関する基準への適合
- 構造部材等の基準法施行令規定への適合
4. 劣化対策等級の証明書はある?確認方法は?

劣化対策等級の評価結果は「住宅性能評価書」として交付されます。
住宅性能評価書とは、国土交通大臣などに登録された第三者機関による公平な審査のもと、住宅の性能に関する評価結果を等級や数値で示したものです。主な評価項目は下記の10分野で、劣化対策等級は「3.劣化の軽減に関すること」に含まれます。
設計住宅性能評価書における評価項目
1.構造の安定に関すること
2.火災時の安全に関すること
3.劣化の軽減に関すること
4.維持管理・更新への配慮に関すること
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること
6.空気環境に関すること
7.光・視環境に関すること
8.音環境に関すること
9.高齢者等への配慮に関すること
10.防犯に関すること
参照:新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド | 国土交通省
住宅性能評価書は、「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類に分かれます。費用相場はそれぞれ10万円〜20万円ほどであり、どちらも取得する場合は30万円前後かかるといわれています。
4.1. 設計住宅性能評価書
設計住宅性能評価書とは、住宅の設計段階の図面や計算書から性能を評価した結果をまとめた書面です。上記の10分野の項目に関して、施工・完成段階では確認できない箇所を評価します。
第三者機関による審査を通過後、下記のマークのついた設計住宅性能評価書が発行されます。
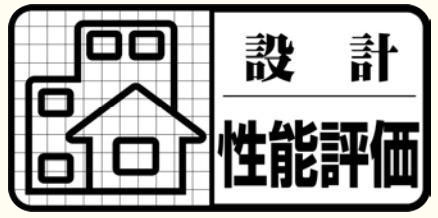
4.2. 建設住宅性能評価書
建設住宅性能評価書とは、住宅の施工段階と完成段階の現場検証による評価結果をまとめた書面です。設計図書のとおりに施工されているかを評価します。
第三者機関による審査を通過後、下記のマークのついた建設住宅性能評価書が発行されます。

5. 劣化対策等級付き住宅のメリット
劣化対策等級付き住宅のメリットを下記5点紹介します。
- 住宅の性能を比較しやすい
- トラブルを防止しやすい
- 高値で売却できる可能性がある
- メンテナンス費用を軽減できる
- 住宅ローンや地震保険で優遇を受けられる
5.1. 住宅の性能を比較しやすい
劣化対策等級の取得は、国土交通大臣の定めた評価基準に基づき、第三者機関による公平な審査を通過したことを示します。一定の性能が保証されているほか、数値や等級といった具体的な数字によって評価が可視化されているため、容易に性能を比較できます。
5.2. トラブルを防止しやすい
劣化対策等級付き住宅のうち建設住宅性能評価書の認定を受けている場合は、請負契約や売買契約などに関するトラブルが発生した際、国土交通省指定の「指定住宅紛争処理機関」を頼ることができます。
指定住宅紛争処理機関には全国の弁護士会などが指定されており、トラブルに関する無料相談や紛争処理の依頼が可能です。紛争処理は1万円から安価に依頼でき、裁判をおこなう必要もないため、大きなメリットといえます。
劣化対策等級を取得していない場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターや国民生活センターなどに相談するのが一般的です。
5.3. 高値で売却できる可能性がある
劣化対策等級付きの住宅は、一定の性能を認められ耐久性の高さや耐用年数の長さが保証されているため、中古住宅でも購入希望者が多くなる傾向にあります。
購入希望者の多さは売却価格に影響を与えやすいので、劣化対策等級を取得していない住宅に比べて高値で売却できる可能性があります。
5.4. メンテナンス費用を軽減できる
劣化対策等級付きの住宅は、長期的に居住できるよう構法や材料の選択を工夫しており耐久性が高いため、メンテナンスに手がかかりにくく、メンテナンス費用を軽減できます。
5.5 住宅ローンや地震保険で優遇を受けられる
劣化対策等級付き住宅のうち建設住宅性能評価書が交付されている場合は、住宅ローンや地震保険の支払いが一部控除されることもあります。
また、資産価値が落ちにくいため住宅ローンの審査にとおりやすく、低金利のローンを組みやすいこともメリットの一つです。
6. 劣化対策等級に関するQ&A

劣化対策等級に関するよくある2つの質問をFAQ形式でまとめました。
6.1. 劣化対策等級の取得にかかる費用は?
劣化対策等級の取得にかかる費用は、評価機関や住宅の規模、追加項目、評価の等級などによって異なりますが、一般的に10万円〜20万円です。
設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書を併せて取得する場合は、30万円前後かかるといわれています。
6.2. 劣化対策等級3のデメリットは?
劣化対策等級3の住宅は、等級2に比べて建築コストが高くなりやすいです。
また、長期優良住宅の条件には「定期的な点検と補修の計画」が含まれているため、住み始めてからの定期点検が必須になります。それにより、トータルの金銭的負担が変わる可能性があります。
7. 一建設は最高等級の劣化対策等級3を取得
今回は劣化対策等級についてまとめました。劣化対策等級は、住宅の性能が一定以上であり長期居住が可能であることを証明するものです。
住宅性能評価書の発行には10万円〜20万円ほどの費用がかかりますが、劣化対策等級を取得していることで下記のようなメリットが得られます。
- 住宅の性能を比較しやすい
- トラブルを防止しやすい
- 高値で売却できる可能性がある
- メンテナンス費用を軽減できる
- 住宅ローンや地震保険で優遇を受けられる
一建設の分譲戸建て住宅は、最高等級である劣化対策等級3を取得しています。住宅性能評価における5分野7項目での最高等級取得を標準化しており、「低価格✕高品質」を実現しています。
>>一建設の取得する住宅性能評価はこちら
長期的に居住できる、耐久性の高い住宅をできるだけ低価格で購入したい方は、ぜひ一建設にご相談ください。
>>一建設のHPはこちら
>>リーブルガーデンのHPはこちら

















