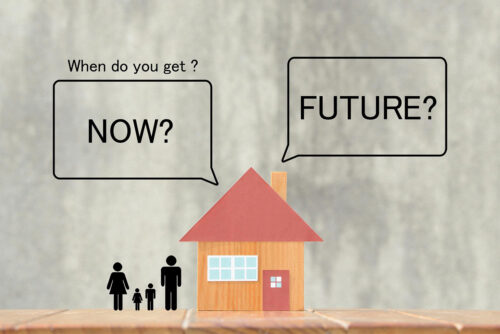3階建て住宅のメリット・デメリットは?後悔しないためのポイントも紹介

目次
一建設の分譲戸建住宅
一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度4分野6項目の最高等級取得を標準化。
お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。
「限られた土地でも理想の住まいを実現したい」そんな願いを叶えてくれるのが3階建て住宅です。土地の有効活用や眺望の良さなど多くの魅力がある一方で、暮らしてみて初めて気付く注意点や不便さもあります。
この記事では、3階建て住宅のメリットとデメリットを解説するとともに、後悔しないためのポイントやよくある疑問への回答もまとめました。これからマイホームを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
1. 3階建て住宅とは

3階建て住宅とは、文字通り3つのフロアを持つ住宅のことです。敷地面積が限られた都市部を中心に、限られた土地を最大限に活用できる住宅形態として注目されています。通常、1階をガレージや玄関・収納スペース、2階をリビングやダイニング、3階を寝室や子ども部屋などに使うケースが多く見られます。
3階建て住宅は、垂直方向への空間の広がりによって、有効面積の小さい土地でも機能的で快適な居住空間を確保できるのが特徴です。特に、土地が高額な都市部や駅近などでは、広い家を持ちたいというニーズと、限られた面積のバランスを取るための現実的な選択肢となっています。
1.1. 3階建て住宅が増えた理由
近年、3階建て住宅が都市部で増えてきた背景には、いくつかの理由があります。
一つは、都市部の地価が高騰し十分な広さの土地を取得するのが難しく、限られた土地面積のなかで広さを確保する必要性が高まっているということ。そのため、縦方向に空間を活用する3階建て住宅が選ばれやすくなっているのです。
1987年の建築基準法改正により、準防火地域でも一定の条件を満たせば木造3階建て住宅を建てられるようになりました。この法改正は、それまで木造では難しかった都市部の3階建て住宅建築を可能にし、結果として都市部での3階建て住宅の普及を後押しする大きな要因となりました。
また、都市再開発や市街地の密集化によって、建て替え時に3階建てを選ぶケースも多くなっています。実際に、都市部では限られた土地を有効に活用するために3階建て住宅を選択する方が増えており、今後もこうしたニーズはさらに高まっていくと考えられます。
2. 3階建て住宅のメリット
3階建て住宅を選ぶことにより、さまざまなメリットを得ることができます。メリットは以下のとおりです。
- 狭い土地でも床面積を確保できる
- 価格の高いエリアでも住宅を購入できる
- フロアごとに使用用途を分けやすい
- 上の階は日当たりや眺望が良い
- 構造計算義務で安心感がある
- 固定資産税の優遇措置がある
- 水害時の対策になる
2.1. 狭い土地でも床面積を確保できる
都市部の住宅地は、一般的に敷地が20〜30坪前後と限られています。このような限られた敷地でも、3階建てにすることで延べ床面積を100〜120平方メートル程度確保できるため、ファミリー層でも快適に暮らすことが可能です。
また、建ぺい率や容積率の制限があっても、3階建てであれば法的基準の範囲内で実用的な広さを得られることから、敷地を無駄なく有効活用できます。
2.2. 価格の高いエリアでも住宅を購入できる
土地価格が高騰している都心部では、広い敷地を購入すること自体が困難です。しかし、狭小地に建てられる3階建て住宅であれば、坪単価が高いエリアでも総額を抑えて住宅を手に入れることができます。
例えば、都内23区内で土地30坪を購入する場合と、15坪の狭小地で3階建てを建てる場合では、土地価格に数千万円単位の差が生じることもあります。その分、住宅ローンの負担を軽減したり、内装や設備に費用を回すことも可能になります。
2.3. フロアごとに使用用途を分けやすい
3階建て住宅では、階ごとに明確な機能分担がしやすくなります。
- 1階:玄関・収納・駐車場・水回り
- 2階:リビング・ダイニング・キッチン(家族の集まる空間)
- 3階:寝室・子ども部屋・書斎などのプライベート空間
このように階ごとに生活動線を分けることで、プライバシーの確保や騒音の軽減につながります。また、二世帯住宅として、2階を共有スペースとし、1階と3階でフロアを分けて暮らすというスタイルも可能です。
2.4. 上の階は日当たりや眺望が良い
3階建て住宅では、2階建てと比べて最上階が周囲の建物よりも高くなるため、日照条件が良くなりやすいです。特に南側に大きな窓やバルコニーを設けることで、明るく開放的な空間が実現できます。
さらに、3階からは街並みや公園、遠方の景色などが一望できることもあり、都会にいながらも自然や季節の移り変わりを感じることができます。
2.5. 構造計算義務で安心感がある
3階建て以上の木造住宅には、建築基準法により「構造計算」が義務付けられています。これは、建物の耐震性や安全性を確保するために必要なもので、設計段階で建物が受ける地震や風圧などの外力に対して、どのように耐えられるかを数値で検証するものです。
2階建て以下の木造住宅ではこの構造計算が免除されるケースもありましたが、3階建て以上では必須となっているため安心感があります。
また、2025年からは「4号特例」が縮小されており、これまで構造計算が不要だった2階建て以下の木造住宅でも、一定の条件下では構造計算が求められるようになります。これにより、より多くの住宅で安全性の確保が重視されるようになり、建物全体の品質向上にもつながると考えられます。
長く安心して暮らせる家を手に入れるためにも、構造のチェックは欠かせないポイントといえるでしょう。
2.6. 固定資産税の優遇措置がある
3階建て以上の耐火・準耐火建築物は、固定資産税が新築から5年間にわたって2分の1に減額される優遇措置があります。さらに、長期優良住宅に認定された場合には、その軽減期間が7年間に延長されることもあります。
例えば、年間の固定資産税が20万円の場合、5年間で本来なら100万円かかるところ、優遇措置により50万円に軽減されます。長期優良住宅であれば7年間の軽減となり、合計で70万円の節税が可能です。
このように、優遇措置を活用することで、初期のコストを大きく抑えることができます。
固定資産税については、下記のコラムも併せてご覧ください。
>>一戸建ての固定資産税はいくら?計算式や軽減措置、シミュレーションも紹介
2.7. 水害時の対策になる
3階建て住宅は、万が一の水害時に2階・3階へ避難できるため、安全性と生活の継続性を確保しやすい住宅です。特に1階をガレージや収納スペースにして、2階以上に居住空間を集約する設計にすることで、浸水による被害を最小限に抑えることが可能です。
日本では近年、台風やゲリラ豪雨による水害リスクが高まり、ハザードマップ上の「浸水想定地域」に住宅が位置するケースも増えています。こうした背景から、水害に強い住宅構造として3階建て住宅が注目されています。
3. 3階建て住宅のデメリット

3階建て住宅には少なからずデメリットもあるため、これらを理解したうえでしっかりと検討しましょう。デメリットは以下のとおりです。
- 工期が長く、建築費が割高になる場合がある
- メンテナンスの手間やコストがかかる
- 建築基準法の制限がある
- 階段移動の負担や、家事動線が悪い
- 上下階で温度差が出やすい
- 建物の揺れが伝わりやすい
- 家具の搬入が大変なケースがある
3.1. 工期が長く、建築費が割高になる場合がある
3階建て住宅は、工期が長くなりやすく、建築コストも割高になる傾向があります。これは、構造が複雑であることに加え、建設時にクレーンや足場といった特殊な設備が必要になるためです。
一般的には、2階建て住宅が3〜4ヵ月程度で完成するのに対し、3階建て住宅では4〜6ヵ月ほどかかることが多くなります。施工の工程が増える分、現場管理や人件費もかさみ、工期全体が延びやすい点も見逃せません。
さらに、建築コストについても、坪単価で比較すると2階建てより10%〜20%程度高くなることが一般的です。例えば30坪の住宅であれば、2階建てと比べて総額で200万円〜400万円ほど費用が増加する可能性があります。
3.2. メンテナンスの手間やコストがかかる
3階建て住宅は、高さがある分、外壁や屋根のメンテナンスに足場が必要になり、作業費用が高くなる傾向があります。特に、外壁塗装や屋根の修理などは、足場代だけで20万円〜50万円ほど追加でかかることも。
また、給排水や電気、空調などの配管・配線が複雑化しやすく、それぞれのフロアに個別の設備を設ける場合はメンテナンスも分散されるため、定期点検や故障対応の手間も増します。
3.3. 建築基準法の制限がある
3階建て住宅は、2階建て以下の住宅と比べて建築基準法による制限が厳しくなります。例えば、防火地域や準防火地域では、外壁や屋根に防火性能を持つ建材を使用する必要があり、さらに開口部のサイズや位置にも規定があります。
また、高さや斜線に関する規制も影響しやすく、設計の自由度が制限されるケースが少なくありません。
こうした制限は、周囲の環境への配慮や防災の観点から設けられていますが、理想の間取りや外観デザインを実現するには、法令との調整が必要不可欠です。
3.4. 階段移動の負担や、家事動線が悪い
3階建て住宅の大きなネックは、階段移動の多さです。洗濯機が1階にあり、物干しスペースが3階にある場合など、家事動線が悪くなりがちで、家事の負担が大きくなります。
高齢者や小さな子どもがいる家庭では、転倒や事故のリスクが高まることも懸念点です。階段に手すりを付ける、滑りにくい素材を使用するなどの対策を講じる必要があります。
3.5. 上下階で温度差が出やすい
夏場は3階がとても暑くなり、冬場は1階が冷え込みやすいという温度差の課題もあります。これは「重力換気」や「熱の上昇性質」によるもので、冷暖房効率が下がり、光熱費が増える原因にもなります。
また、隣家との距離が近い場合が多いため、風通しや日当たりに制約が出ることもあります。3階部分は比較的光を取り入れやすい一方で、1階や2階の居室では周囲の建物の影響で採光が不足するケースもあります。
3.6. 建物の揺れが伝わりやすい
3階建て住宅は高さがある分、地震や風の影響を受けやすく、揺れを感じやすい構造です。特に3階は揺れが増幅される傾向にあるため、不安を感じる方も少なくありません。
3.7. 家具の搬入が大変なケースがある
大型の家具や家電を2階や3階まで運ぶ必要がある場合、階段の幅や形状によっては搬入が困難になることがあります。特に2階にリビングを配置している間取りでは、冷蔵庫やソファなどの大型家電・家具を上階まで持ち上げる必要があるため、引っ越しや買い替えの際に苦労することが少なくありません。
このような場合、ベランダから搬入するケースも多く見られますが、そのためには窓の開口部サイズやバルコニーの構造などが搬入に適しているかを事前に確認しておく必要があります。
4. 3階建て住宅で後悔しないためのポイント
3階建て住宅を選んで後悔しないようにするために、次の4つのポイントを押さえておきましょう。
- 建物の構造・耐震性の確認をする
- 間取り・生活動線が適切か確認をする
- 冷暖房効率を高める工夫をする
- 収納スペースを工夫する
4.1. 建物の構造・耐震性の確認をする
前述のとおり、3階建て住宅は建物の高さゆえに地震や風による揺れが上階に伝わりやすくなります。そのため、構造や耐震性の確認は重要なポイントです。
構造計算の種類を確認し、建物にかかる外力に対して十分な耐力があるかを検証する必要があります。また、使用される建材の性能や、地盤調査による安全性の評価も合わせて確認しておくと安心です。
加えて、耐震等級の取得や地震保険への加入など、万が一に備えた対策を講じておくことで、長期にわたって安心して暮らせる住まいとなります。
耐震等級について詳しくは下記のコラムも併せてご覧ください。
>>建売住宅の耐震等級とは?耐震強度の調べ方や購入前の注意点も紹介
4.2. 間取り・生活動線が適切か確認をする
フロアごとに用途を分ける場合、自由度が高い反面、生活動線に不便が生じるデメリットもあります。特に家事を効率よくおこなうための導線では、例えば「洗濯→干す→収納」といった流れや、キッチンから食卓・リビングへのアクセスなどを意識して設計することが大切です。
加えて、玄関やトイレの配置、来客時の動線なども事前にイメージしておくと、暮らしやすさが大きく変わってきます。
4.3. 冷暖房効率を高める工夫をする
上下階での温度差を解消するためには、断熱性能の高い素材の使用に加えて、区切りの工夫や空調設備の導入が重要です。以下は具体的な対策の一例となります。
- 階ごとの空間をカーテンや引き戸でしっかり区切る
- サーキュレーターやシーリングファンを活用
- 個別エアコン+メッシュWi-Fi付き温度センサーで管理
冷暖房費は年間で数万円単位の差が出ることもあるため、初期投資としての設備強化は費用対効果が高いといえます。
4.4. 収納スペースを工夫する
3階建て住宅、特に狭小地に建てられた場合は、収納スペースが限られがちです。そのため、空間を無駄なく活用する工夫が求められます。
例えば、天井高を活かして設けるロフトや小屋裏収納は、季節用品や普段あまり使わない荷物の収納場所として有効です。
また、ベンチ収納や階段下収納、壁面収納など「見せる収納」と「隠す収納」をバランスよく取り入れることで、暮らしの快適さが大きく向上します。特にリビングやダイニングなど、生活感が出やすい空間では、収納付き家具を取り入れることで整理整頓がしやすくなります。
5. 3階建て住宅のよくある質問

ここでは、3階建て住宅に関するよくある質問をまとめました。
5.1. 売却時に売れにくくなるの?
「階段の昇り降りが大変」「高齢者に向かない」といった理由から、3階建て住宅は売却しにくいイメージを持たれることもあります。
しかし、実際には立地条件や間取り、築年数によって需要は大きく異なります。特に都市部や駅から徒歩10分以内といった利便性の高いエリアの戸建てニーズは高く、3階建て住宅は子育て世帯や共働きの若い夫婦などからの支持を集めています。
将来的な売却を見据えるのであれば、誰にとっても使いやすい汎用性の高い間取りや、必要に応じてバリアフリー化が可能な設計の住宅を選択すると安心です。
5.2. 3階部分は電波が届きにくいの?
高さがある分電波が届きにくいイメージを持つ方が多いですが、木造住宅の場合は壁や床が電波を大きく遮ることが少なく、構造上の問題で通信が極端に悪くなることはあまりありません。
それでも電波が弱いと感じる場合には、Wi-Fiルーターの設置場所を見直すことで解消できます。ルーターを2階など中央の階に設置する、あるいはメッシュWi-Fiや中継器を活用することで、家全体に安定した通信環境を確保できます。
適切な機器と設置方法を選べば、3階建て住宅でも快適なインターネット環境を実現できます。
5.3. 3階部分は水圧が弱くなるの?
3階は高さがある分、他の階より水圧が低くなるケースがあるため、水回りの設備は基本的に1階または2階に配置するのがおすすめです。
どうしても3階に水回りを設置したい場合には、給水管の口径を太くする、または加圧ポンプを設置することで水圧不足を解消できます。
5.4. 隣家との距離は近いの?
都市部や住宅密集地では、3階建て住宅は狭小地に建てられることが多く、隣家との距離が1メートル未満というケースもあります。実際の採光や通風の状況、隣家との視線の関係などは、図面だけではわかりにくいため、必ず現地で確認しておくことをおすすめします。
6. 持ち家を探すなら、「リーブルガーデン」がおすすめ
3階建て住宅は、都市部でも広い居住空間や日当たりの良さ、眺望の確保といった魅力があり、設計の工夫次第で快適な暮らしを手に入れることができます。
ただし、階段移動の負担や温度差、水圧・電波の影響などの課題もあるため、事前に対策を考えておくことが大切になります。
3階建て住宅を検討している方には「リーブルガーデン」がおすすめです。
リーブルガーデンは、すべての物件で最高等級である「耐震等級3」を取得しており、これは建築基準法で定められた地震力の1.5倍の揺れにも耐えられる高い耐震性を意味します。地震が多い日本で、家族の安全を守るうえで心強い仕様です。
さらに、リーブルガーデンでは充実した設備と機能的な間取りを兼ね備えた住宅が多数そろっており、都市部の限られた土地でも快適な住空間を実現できます。購入のご相談はもちろん、住宅ローンなど資金面でのご相談も受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。