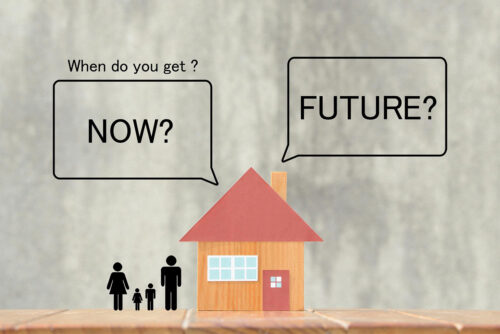不動産購入にかかる諸費用を安く抑えるポイントを解説

目次
一建設の分譲戸建住宅
一建設の分譲戸建住宅は年間約9,000棟以上を供給、国内トップクラスの販売戸数を誇ります。また住宅性能表示制度5分野7項目の最高等級取得を標準化。
お客さまとご家族に安心して住んでいただける住まいをお届けします。
土地や建物などの不動産を購入すると、物件価格以外にもさまざまな業者に支払う手数料や税金などの諸費用が発生します。
そこで今回は主にマイホームを検討される方に向けて、不動産購入にかかる諸費用の内訳や安く抑える方法を解説します。
1. 不動産購入にかかる諸費用
不動産購入では、業者に支払う手数料や税金などさまざまな諸費用が発生します。
そのなかでもマイホームの購入時に発生する諸費用の主な項目は以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 手付金
- ローン保証料
- 団体信用生命保険料
- 事務手数料
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
- 火災保険料・地震保険料
- 修繕積立金
- 水道加入負担金
ここからは上記の諸費用を「住宅の売買契約を結ぶとき」「住宅ローンを組むとき」「登記の登録をするとき」と支払いのタイミングで3つにわけて、それぞれの項目と金額の目安を解説します。
1.1. 住宅の売買契約を結ぶとき
住宅を購入する際、売り主は土地や建物の所有権を買い主に移し、買い主はその代金を支払うことを約束する売買契約を結びます。
住宅の売買契約締結時に発生する主な諸費用は以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 手付金
1.1.1. 仲介手数料
不動産会社の仲介で住宅を購入する場合は、売買契約が成立した際の成功報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産会社が自由に金額を設定できますが、宅地建物取引業法により以下のように上限額が定められています。
| 不動産の売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格の5.5%以内 |
| 200万円〜400万円以下 | 売買価格の4.4%以内 |
| 400万円超 | 売買価格の3.3%以内 |
実際に支払う仲介手数料の上限額は、物件の売買価格に応じて異なる計算式で算出します。
それぞれの分類方法で計算すると手間がかかりますが、以下の速算式という計算式を使用することで手軽に計算できます。
| 不動産の売買価格 | 仲介手数料の上限額(速算式) |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格(税抜)×5%+消費税 |
| 200万円〜400万円以下 | 売買価格(税抜)×4%+2万円 +消費税 |
| 400万円超 | 売買価格(税抜)×3%+6万円 +消費税 |
住宅金融支援機構が発表した「2023年度 フラット35利用者調査」の調査結果によると、建売住宅の平均購入価格は3,603万円です。このため住宅を購入する際の仲介手数料の目安は、売買価格(税抜)×3%+6万円 +消費税となります。
ただし、住宅を建築したハウスメーカーやビルダーなどの売り主から直接不動産を購入する場合、仲介手数料は発生しません。
>>建売住宅の購入には仲介手数料がかかる?無料?計算方法や抑え方も紹介
1.1.2. 印紙税
印紙税とは、契約書や領収書などの作成時にその文書に課税される税金です。
不動産の売買に必要となる不動産売買契約書も印紙税の課税対象であり、税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 軽減税率 |
|---|---|
| 100万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 5,000円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え億円以下のもの | 6万円 |
※100万円以下・5億円以上の場合は省略
平成26年(2014年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は軽減措置の対象となるため、本則税率の20〜50%となる上記の軽減税率が適用されます。
1.1.3. 手付金
手付金とは、購入意思があることを示すために売り主に対して物件価格の一部を先払いすることです。契約の証拠金のような意味合いがあるため、買い主が契約をキャンセルした場合は返還されませんが、無事売買契約が成立した場合は、家の購入費用の一部として充当されます。
手付金の金額は売り主・買い主双方の合意によって決められますが、売買価格の5〜10%が目安です。
1.2. 住宅ローンを組むとき
住宅を購入するには、住宅ローンを組んで金融機関から融資を受ける方がほとんどでしょう。
住宅ローンを組むときに発生する主な諸費用は以下のとおりです。
- ローン保証料
- 団体信用生命保険料
- 事務手数料
- 印紙税
1.2.1. ローン保証料
従来、住宅ローンを契約する際は万が一ローンの返済が困難になった場合に、契約者の代わりに返済の義務を負う連帯保証人を立てるのが一般的でした。
しかし、数千万円という高額なローンの連帯保証人になってくれる方を探すのは難しいことから、近年ではその代わりに保証会社の利用が増えています。
ローン保証料は、保証契約を保証会社と結ぶためにかかる費用です。契約者と保証契約を結んだ保証会社は、万が一契約者がローンの返済を続けられなくなった場合、契約者の代わりに金融機関にローンの残債を支払います。
住宅ローンの保証料は金融機関によって異なりますが、借入金額の0〜2%が相場です。0円の場合は金利に上乗せ、または事務手数料として相当額を支払うのが一般的となっています。
1.2.2. 団体信用生命保険料
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローン契約者に万が一のことがあったときに家族を守るための保険です。
加入は任意ですが、もし契約者が死亡または高度障害の状態となった場合、住宅ローンの返済が免除されるため、残された家族の金銭的な負担を減らせます。
基本的に団体信用生命保険の保険料は金融機関が負担しますが、実際はその相当額(年0〜0.3%程度)が住宅ローンの金利に上乗せされるのが一般的です。
1.2.3. 事務手数料
住宅ローンの手続きに関する事務費用として金融機関に支払う費用です。金融機関によって、融資手数料、融資事務手数料、事務取扱手数料など呼び方が異なる場合があります。
住宅ローンの事務手数料は、大きく分けて定率型と定額型の2種類があります。
定率型は、借入金額に対して一定の割合を手数料として支払う方法で、借入金額×2.2%が相場です。
借入金額に関係なく少額の手数料を支払う定額型の場合は、3万円~5万円が相場です。そのかわり定率型より金利が0.1〜0.2%高く設定されていたり、別途保証料が必要となったりする場合が多くなっています。
総支払額や毎月の返済負担を考慮して、より自分に合った方法を選択しましょう。
1.2.4. 印紙税
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
通常、住宅ローンの契約書は1枚ですが、固定金利と変動金利を組み合わせたミックスローンを選択した場合や、夫婦や親子で住宅ローン契約をするペアローンを選択した場合は、契約書を2通作成するため2通分の印紙代がかかります。
1.3. 登記の登録をするとき
購入や相続、新築などにより不動産を取得した場合は、登記が必要になります。
登記とは、どのような不動産が誰のものであるか、権利関係をはっきりさせるために、法務局が管理する登記簿に不動産やその所有者の情報を記録することです。
例えば新築の戸建てを購入した場合には、建物の表題登記や土地の所有権登記、建物の所有権保存登記をおこなう必要があります。
また、住宅ローンを利用する場合は、不動産を担保とするための抵当権設定登記もおこないます。
このような登記の申請をする際に発生する諸費用は以下のとおりです。
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
1.3.1. 登録免許税
登録免許税とは、資産の登録や移転など登記の手続きをするのにかかる税金のことです。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。新築でまだ建物に固定資産税評価額が付けられていない場合は、法務局が算出した価格が基準となります。
参照:不動産登記における評価額のない建物の課税標準について|東京法務局
税率は登記の種類によって異なりますが、新築住宅で所定の要件を満たす場合は軽減税率が適用され、土地の所有権登記は1.5%、建物の所有権保存登記は0.15%、抵当権設定登記は0.1%となります。建物の表題登記は非課税です。
| 登記の種類 | 本則 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 建物の表題登記 | 非課税 | |
| 土地の所有移転登記 | 2.0% | 1.5% ※1 |
| 建物の所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% ※2 |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1% ※2 |
※2 適用期限:令和9年(2027年)3月31日まで
参照:登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ|国税庁
1.3.2. 司法書士への報酬
登記の申請は専門的な知識が必要であることから、不動産や登記手続きの専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に支払う報酬は、物件の価格や司法書士事務所、登記の種類によって異なりますが、住宅購入の場合は総額4万円~20万円が相場です。
1.4. その他の費用
上記以外にも、住宅購入には以下のような諸費用が発生する場合があります。
- 火災保険料・地震保険料
- 修繕積立金
- 水道加入負担金
1.4.1. 火災保険料・地震保険料
法律で義務付けられているわけではありませんが、火災リスクから住宅や財産を守るためには、火災保険に加入しておくのが安心です。実際に持ち家の火災保険加入率は約8割と、多くの方が万が一に備えていることがわかります。また、加入している人の約7割が地震保険にも加入しています。
火災保険や地震保険の保険料は、戸建てかマンションか、家の構造や補償内容などによって大きく異なりますが、戸建ての場合は地震保険ありの場合年間約9万円〜11万円、地震保険なしの場合は年間約3万円〜5万円が目安です。
マンションの場合は、地震保険ありの場合年間1万円〜1万5,000円程度、地震保険なしの場合3,000円〜5,000円程度が相場となっています。
1.4.2. 修繕積立金
住宅購入後は、将来のメンテナンスや修繕に備えて費用を積み立てておく必要があります。
戸建ては各自で計画的に準備しますが、マンションの場合は修繕積立金の支払いが、購入時だけではなく毎月発生します。
修繕積立金の金額は物件や専有面積などによって異なりますが、国土交通省のデータによると、その平均額は月額1万1,243円となっています。
参照:平成 30 年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状|国土交通省
1.4.3. 水道加入負担金
水道加入負担金とは、新しく水道を引くときや水道の口径を増やすときに発生する費用です。建売住宅購入時や注文住宅建築時に支払いを求められることがあります。
水道加入負担金の金額は地域によって数万円〜数十万円と幅広く、自治体によってはかからないこともあります。
2. 購入後にかかる諸費用

住宅は購入時だけでなく、購入後にも以下のような諸費用が発生します。
- 不動産取得税
- 固定資産税、都市計画税
- 家具・家電費、引っ越し費
2.1. 不動産取得税
土地や建物を購入する、家屋を建築するなどして不動産を取得した場合に課せられるのが不動産取得税です。
納税額の計算式は、固定資産税評価額×4%(税率)ですが、土地と住宅には軽減税率の3%が適用されます。
2.2. 固定資産税、都市計画税
土地や建物などの不動産は長期にわたって保有する固定資産として、毎年固定資産税がかかります。
納税額は、固定資産税評価額×1.4%(税率)が標準ですが、自治体によって税率が異なる場合もあります。土地と建物それぞれに課税され、戸建ての場合は10万円〜15万円となるのが一般的です。
また、土地や建物が都道府県知事や国土交通大臣が指定する都市計画区域内にある場合、都市計画税も納税する必要があります。
納税額は、固定資産税評価額×0.3%(税率)が標準で、税率は自治体によって異なりますが、0.3%を超えることはありません。
住宅用地の場合、都市計画税の課税基準となる固定資産税評価額に関しては以下の軽減の特例が適用されます。
| 住宅用地 | 課税基準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税評価額 × 1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 固定資産税評価額 × 2/3 |
2.3. 家具・家電費、引っ越し費
購入した住宅に住む場合は、家具・家電の購入費用や引っ越しの費用も必要です。
新築購入時の家具・家電の購入費用の平均は152.8万円程度です。
引っ越しにかかる費用は、時期や旧居との距離、荷物の多さなどによって異なりますが、同じ市内で家族で引っ越す場合10万円前後が目安となります。
3. 不動産購入時にかかる諸費用の目安は?
- 住宅種別ごとの諸費用の有無
- 諸費用のシミュレーションをしておく
不動産購入時にかかる諸費用の目安は、条件によってかかったり、かからなかったりする項目もあるため、一概にはいえません。
しかし、住宅を購入する際は、注文住宅や新築マンションで物件価格の3〜6%、建売住宅や中古住宅の場合は物件価格の6〜10%程度が目安といわれています。
3.1. 住宅種別ごとの諸費用の有無
今まで紹介した諸費用の項目を、新築の建売住宅・注文住宅・マンション、中古の戸建て・マンションの5つの種類ごとに有無をまとめました。
| 新築 | 中古 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建売住宅 | 注文住宅 | マンション | 戸建て | マンション |
| 仲介手数料 | △ | × | × | ◯ | ◯ |
| 印紙税 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 手付金 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
| ローン保証料 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 団体信用生命保険料 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
| 事務手数料 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 登録免許税 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 司法書士への報酬 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 火災保険料・地震保険料 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
| 修繕積立金 | × | × | ◯ | × | ◯ |
| 水道加入負担金 | △ | △ | △ | × | × |
| 固定資産税 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 都市計画税 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 不動産取得税 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 家具・家電購入費用・引っ越し費用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
△・・・かからない場合もある
×・・・かからない
3.2. 諸費用のシミュレーションをしておく
上記のように、不動産を購入する場合にかかる諸費用は物件や地域によってさまざまです。このため諸費用の目安を知るには、自分のケースでは何の項目に、おおよそどのくらいの金額がかかるのか調べて計算する必要があります。
特にマイホームの購入を検討している場合、物件価格だけで考えていると予算オーバーになりやすいです。諸費用は現金での支払いが必要な項目が多いため、資金不足に陥らないよう注意しましょう。
また、住宅購入後は住宅ローンや修繕積立金など継続的に支払いが必要なものもあります。銀行や不動産会社のホームページにあるローンシミュレーションを活用し、月々の支払い負担が無理のない範囲で収まるよう予算を設定しましょう。
4. 諸費用を抑えるポイント
新居として住宅を購入する場合、諸費用を安く抑えるには以下のような方法があります。
- 引っ越し時期をずらす
- 火災保険や地震保険を長期契約で一括払いにする
4.1. 引っ越し時期をずらす
新年度に向けて引っ越しが集中する1〜4月は、繁忙期のため引っ越し費用が高くなります。
閑散期である6〜8月や11〜12月を選べば、ピーク時の20〜40%の料金に抑えられます。
また、荷物の量も価格に関係するため、布団や衣類は圧縮する、不用品は処分しておくなど、荷物を減らす工夫も心がけましょう。
4.2. 火災保険や地震保険を長期契約で一括払いにする
火災保険や地震保険は、保証開始から終了までの保証期間や、保険料の支払い方法を選択できます。
保証期間は1年間、5年間、10年間、保険料の支払い方法は月払い、年払い、一括払いをそれぞれ選択できるのが一般的です。
保険期間はなるべく5年や10年など長い期間を、そして支払い方法は一括や年払いなどなるべくまとめ払いする方法を選択することで、総支払額を安く抑えられます。
5. 現金で支払いができるよう準備しておく

不動産購入時の諸費用は現金払いが求められるものが多く、主な項目は以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 手付金
- ローン保証料
- 団体信用生命保険料
- 事務手数料
- 火災保険料・地震保険料
- 修繕積立金
- 水道加入負担金
- 税金
一つひとつは少額でも合計すると数百万円にものぼるため、資金不足に陥らないよう、あらかじめどのタイミングでどのくらいのお金がかかるのか目安を計算しておきましょう。
6. 不動産購入時の諸費用のポイントをおさえよう

土地や家屋など不動産の購入時には、不動産会社や金融機関に支払う手数料、登記費用や税金などさまざまな諸費用が発生します。
総額の目安は、注文住宅や新築マンションの場合物件価格の10~12%、建売住宅や中古住宅の場合は6〜10%程度といわれていますが、条件によってかかったり、かからなかったりする項目もあるため、自分のケースでは何にどのくらいの金額がかかるのか事前に把握しておきましょう。諸費用は現金での支払いが求められる項目がほとんどのため、資金不足に陥らないよう、計画的に準備しておく必要があります。
諸費用を含め、なるべく予算を抑えて住宅を購入したい方は、一建設が贈る戸建て分譲住宅の総合ブランド「リーブルガーデン」の住まいがおすすめです。
分譲戸建住宅のシェアNo.1(2023年4月1日~2024年3月31日住宅産業研究所調べ)のスケールメリットを活かして、高品質な住宅を低価格で提供しています。
「想いも価格も妥協したくない」「コストとクオリティのバランスがとれた住宅にしたい」方はぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。