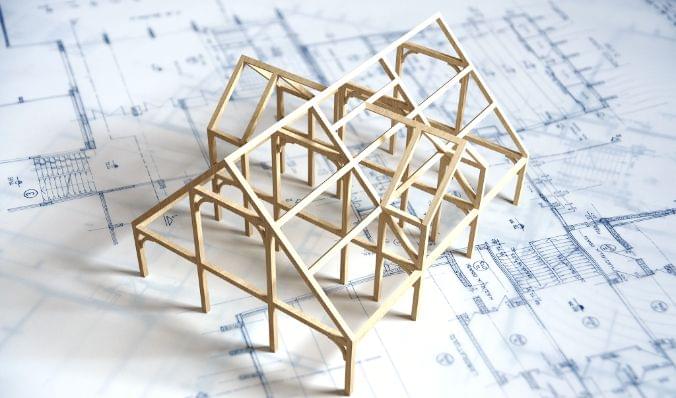2024.09.04 | 費用・制度
家を建てる費用はいくら?注文住宅に必要な資金と、コストを抑える方法を解説!

目次
はじめの費用・制度
家づくりを進めるうえでは、価格と品質のバランスが非常に重要です。
一建設では、年間約9,000棟超の供給実績を活かし、コストを抑えながらも高品質な注文住宅を実現しています。
建築に必要な工程をすべて含んだ安心のコミコミ価格に加え、着工金や中間金が不要な資金計画の立てやすさも魅力です。
自社一貫体制による中間マージンの排除など、低価格を支える仕組みについて、詳しくは価格ページをご覧ください。
家を建てるとなると、全部でいくらかかるのか想像がつかない方も多いでしょう。
そこで今回は、注文住宅の建築を検討している方向けに家を建てる費用の目安を解説します。
所要資金の内訳や資金計画の立て方、1,000万円台、2,000万円台、3,000万円台、4,000万円台と予算別に建てられる家のイメージとローンシミュレーションも紹介しますので、ぜひ家づくりの参考にしてください。
1. 家を建てる費用の目安
家を建てる費用は、土地を持っている場合と持っていない場合で大きく異なります。
そこでまずは、「土地ありの場合」「土地なしの場合」の費用の平均を、全国平均と主要エリアでみてみましょう。
1.1. 土地ありの場合
| 所要資金 | 頭金(自己資金) | 所要資金に占める頭金の割合 | |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 3,936万円 | 729.0万円 | 18.5% |
| 首都圏 | 4,264.9万円 | 992.4万円 | 23.3% |
| 近畿 | 4,118.6万円 | 776.7万円 | 18.9% |
| 東海 | 3,935.5万円 | 743.2万円 | 18.9% |
| その他地域 | 3743.6万円 | 593.0万円 | 15.8% |
2024年度フラット35利用者調査によれば、すでに土地がある状態で注文住宅を建てた方の平均所要資金は、3,936万円です。
頭金(自己資金)の平均金額は729.0万円となっており、所要資金に対して18.5%の割合となっています。
土地ありの場合は、土地の購入費用がほぼかからないため、所要資金の大部分を住宅の建設費が占める形になります。
>>家を建てる費用は土地ありだといくら?抑えるポイントも紹介
1.2. 土地なしの場合
| 所要資金 | 建設費 | 土地取得費 | 頭金(自己資金) | |
|---|---|---|---|---|
| 全国平均 | 5,007.1万円 | 3,512.0万円(70.1%) | 1,495.1万円(29.9%) | 460.7万円(9.2%) |
| 首都圏 | 5,790.6万円 | 3,505.6万 円(60.5%) | 2,285.0万円(39.5%) | 663.5万円(11.5%) |
| 近畿 | 5,192.7万円 | 3,366.7万円(64.8%) | 1,826.0万円(35.2%) | 512.5万円(9.9%) |
| 東海 | 4,975.5万円 | 3,615.7万円(72.7%) | 1,359.8万円(27.3%) | 372.6万円(7.5%) |
| その他地域 | 4,534.1万円 | 3,549.1万円(78.3%) | 985.0万円(21.7%) | 355.1万円(7.8%) |
2024年度フラット35利用者調査によれば、土地を持っていない状態で注文住宅を建てた方の平均所要資金は、5,007.1万円です。
所要資金の内訳は、住宅の建設費が3,512万円(70.1%)、土地取得費が1,495.1万円(29.9%)となっています。
土地取得費がかかるぶん総額が高くなるため、頭金(自己資金)に割ける金額は460.7万円(所要資金に対する割合は9.2%)と、土地ありの場合の729.0万円より少なくなっていることがわかります。
>>家を建てる費用は土地なしだといくら?抑えるポイントも紹介
2. 家を建てる前にかかる費用の目安
家を建てる際は、土地の購入や住宅の建設など、それぞれの工程でさまざまな費用が発生します。
ここでは「家を建てる前にかかる費用」について解説します。
2.1. 土地の購入費
土地を持っていない場合は、家を建てるための土地をまず購入する必要があります。
建設費用と土地取得費の割合は、6:4または7:3が一般的な比率です。
土地の購入費には、土地代だけでなく、仲介業者に支払う手数料や土地の売買契約書に貼る収入印紙代が含まれます。
仲介手数料は、土地代の3%+ 6万円が相場です。ただし、売り主から直接購入する場合は、仲介手数料を支払う必要はありません。
収入印紙代は、以下のように取引金額によって異なります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5,000円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
印紙税については、2014年(平成26年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は軽減措置の対象となり、20〜50%の軽減税率が適用されます。
2.2. 家の建築費
家の建築費は、大きく「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つで構成されます。木造・鉄骨造・RC造といった構造の違いや建てる家の坪数・仕様によって、総費用は大きく変動します。
建築費の内訳は、およそ下記のような割合になります。
本体工事費:約70%
付帯工事費:約20%
諸経費:約10%
それぞれについて詳しくみていきましょう。
2.2.1. 本体工事費
住宅の建設費用のなかでも、家本体にかかる費用を本体工事費といいます。
本体工事費は建設費全体の70〜80%と高い割合を占め、具体的には以下のような工事が含まれます。
- 基礎工事……地面と建物をつなぐ基礎(土台)をつくる工事
- 内装工事……建物の床・壁・天井などの工事
- 外装工事……外壁や屋根などの工事
- 設備工事……キッチン・浴室・トイレなどの工事
建築会社によって異なりますが、本体工事費を支払う一般的なタイミングや割合は以下のとおりです。
| 工事請負契約締結時 (建築会社との契約時) | 着手金10% |
|---|---|
| 着工時(工事開始時) | 着工金30% |
| 上棟時(建物の基本構造完成時) | 中間金30% |
| 引渡し時 | 残代金30% |
2.2.2. 付帯工事費
家の本体以外、主に屋外設備にかかる費用です。
建設費全体の15〜20%を占め、具体的には以下のような工事が含まれます。
- 土地の整備費用
- 外構工事(駐車場や庭など)
- 電気配線工事
- 排水工事
- ガスの引き込み工事
特に高額になりがちなのが、土地の整備費用です。
地盤改良や盛り土など、必要な工事や金額は土地の状態によって異なるため、事前に見積もりをとってどれくらいの金額がかかるのか確認しておきましょう。
2.2.3. 諸経費
家を建てるには、住宅の建設費や土地取得費以外にも以下のようにさまざまな諸経費がかかります。
- 印紙代
- 登記費用
- 火災保険料・地震保険料
- 家具・家電の購入費用
- 引っ越し費用
建築会社に正式に家の工事を発注するときに取り交わす工事請負契約書には、土地の購入時と同様、契約金額に応じて印紙代がかかります。
また、土地や建物の所有権を得るためにおこなう不動産登記や、住宅ローンに必要な抵当権設定登記には登録手数料が発生します。
登記は、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に登記業務を依頼する場合は、司法書士への報酬も登記費用に含まれます。
注文住宅の諸費用の内訳や相場の目安に関しては、こちらの記事で詳しく紹介していますのでご覧ください。
>>注文住宅の諸費用の内訳や相場の目安はいくら?シミュレーションや節約方法も紹介
2.3. エリアによる費用の差
家づくりの総費用は、建てるエリアによって大きく変わります。
特に影響が大きいのが「土地取得費」で、都市部ほど土地価格が高くなるため、総額も大きく上昇します。一方、地方は土地費用が抑えられるため、同じ家を建てても必要な資金に大きな差が生まれます。
「1.2.土地なしの場合」の表でわかるように全国平均と主要エリアを比較すると、首都圏は総額・土地取得費ともに最も高く、その他地域は最も低い傾向があります。
建設費そのものの差はエリア間で大きくはありませんが、土地代が総予算に強く影響します。
3. 家を建てたあとにかかる費用
家を建てると、土地や住宅に対してさまざまな税金が発生します。
家を建てたあとにかかる主な費用は以下のとおりです。
3.1. 不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋を購入する、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる地方税です。
不動産取得後6ヵ月から1年の間に納税通知書が届くため、記載された期限までに税金を納める必要があります。
不動産取得税の計算方法は、固定資産税評価額(不動産の評価額)×4%です。
ただし、土地と住宅には軽減税率として3%が適用されます。
3.2. 固定資産税
固定資産税とは、不動産などの固定資産に課せられる地方税です。
土地や家屋などの不動産を取得後、毎年4〜6月に送付される納税通知書に記載された金額を支払い続ける必要があります。
固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額×1.4%です。税率は地域によって変わりますが1.4%が標準です。
土地、建物それぞれに対して課税され、その平均額は一戸建ての場合10万円〜15万円ほどとなっています。
3.3. 都市計画税
都市計画税とは、都道府県知事や国土交通大臣が指定する都市計画区域内にある土地・建物に対して課せられる地方税です。固定資産税と一括で納税されます。
都市計画税の計算方法は、固定資産税評価額×税率(0.3%以内)です。
自治体によって異なりますが、税率の上限は0.3%でこの数字を超えることはありません。
また、住宅用地では都市計画税の課税基準となる固定資産税評価額に関して、以下の軽減の特例があります。
| 住宅用地 | 課税基準 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税評価額×1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 固定資産税評価額×2/3 |
軽減の特例に関しては市町村で適用の手続きをとってくれるため特に納税者側で申請する必要はありません。
4. 家を建てるための資金計画の立て方

家を建てたいと思っても、注文住宅の建築には多額の費用がかかるため「予算や資金計画の立て方がイメージできない」方も多いでしょう。
そこでここからは、注文住宅を建築する際の予算設定や資金計画のポイントを解説します。
4.1. 住宅ローンの借入額を決定
人生で大きな買い物となる住宅購入は、住宅ローンの利用が一般的です。
実際、国土交通省の「令和6年度 住宅市場動向調査報告書」では、新築の注文住宅を購入した世帯の78.8%が住宅ローンを利用しているというデータがあります。(※注文住宅の調査地域は全国での調査)
住宅ローンの審査では年収に加えて、返済負担率も判断基準となります。
返済負担率とは、年収に対する年間のローン返済額の割合のことで、「年間のローン返済額÷年収×100=返済負担率(%)」で求められます。
無理のない返済負担率といわれている年収の25%以内を目安に、住宅ローンの借入希望額を決定しましょう。
住宅ローンの事前審査を受けると、実際にいくらまで借りられるのか=借入可能額の目安を知ることができます。
4.2. 用意できる自己資金の金額を把握
家を建てる際は、住宅ローンとは別に「頭金」を用意できるのが理想です。
頭金とは、預貯金などの自己資金から、住宅購入費の一部を前払いすることです。
頭金を多く入れると住宅ローンの借入額を減らせるため、毎月のローン負担を軽減できます。
また、土地取得費や建設費以外の費用となる「諸経費」も、住宅建設中の段階で現金支払いが求められるため、自己資金での準備が必要です。
「諸経費」に必要な自己資金と、「頭金」にあてられる自己資金をそれぞれ計算しておきましょう。
>>家を建てるときに必要な頭金はいくら?頭金を用意するときの注意点を解説
>>家を建てるにはいくら貯金が必要?お金がないときの対応方法や注意点も紹介
4.3. 住宅ローン以外の支出を考慮
家を購入したあとも生活はずっと続いていきます。
このため生活費や病気・事故への備えを残しておくのはもちろん、介護費用や子どもの教育費用、修繕やメンテナンスにかかる費用なども考慮しておきましょう。
将来的な支出だけでなく、転職や再就職などで年収が変化する可能性も踏まえて、住宅ローンの借入額や頭金の額を決定することが大切です。
4.4. 自己資金が足りなければつなぎ融資を検討
通常、住宅ローンは住宅が完成したタイミングで融資が実行されます。
しかし、住宅購入ではその前にも土地の購入や工事の着手金、中間金などその都度支払わなければならない費用があるため、これらを自己資金で賄えない場合は、つなぎ融資を検討する必要があります。
つなぎ融資とは、これらの費用を立て替えるための融資です。つなぎ融資の元金は、住宅ローンの融資が実行されたらそのお金を利用して一括返済しますが、利息の支払い方法は金融機関によって異なります。
また、資金を受け取れる回数や融資の上限額なども各金融機関で異なるため、住宅ローン申し込みの際に事前に相談しておきましょう。
4.5. 資金計画で失敗しないポイント
注文住宅の資金計画では、「借りられる額」ではなく「返せる額」で考えることが鉄則です。 特に住宅ローンは長期にわたるため、毎月の支払いに無理がないかどうかを冷静に見極めることが重要です。以下のポイントを押さえておけば、資金計画で失敗する恐れが抑えられます。
まず、住宅ローンの返済比率は「年収の25%以内」に収めるのが安全ラインとされています。返済比率が高くなるほど家計の圧迫につながり、教育費・車の買い替え・生活費など日常の支出に余裕がなくなるため、無理のない設定が大切です。
また、頭金や諸経費にあてる自己資金は、総費用の20〜30%を目安に用意しておくと安心です。特に諸経費(設計料・登記費用・火災保険など)は現金払いが原則のため、早い段階から準備しておく必要があります。
さらに、住宅ローン返済だけでなく、毎月の生活費・固定費・将来の支出まで含めてシミュレーションすることも重要です。住宅は「買って終わり」ではなく、光熱費、メンテナンス費、税金など意外と見落としがちな支出も積み重なります。
こうしたポイントを押さえておくことで、負担の少ない資金計画を立てやすくなり、家づくり全体を安心して進められます。
5. 【費用別】建てられる家のイメージとローンシミュレーション

建設にかけられる予算によって、家づくりで叶えられる希望やローンの返済計画は変わってきます。
そこでここからは、1,000万円台、2,000万円台、3,000万円台、4,000万円台と費用別に建てられる家のイメージと簡易的なローンシミュレーションを紹介します。
5.1. 1,000万円台の家
1,000万円台の予算でも、いわゆるローコスト住宅と呼ばれる、事前にプランがある程度設定されている規格住宅を選べば家を建てることは可能です。
自由度は低くなりますが、一定の安全性は確保されているため「住まいへのこだわりが少ない」「家にあまりお金をかけたくない」方にはおすすめの選択肢です。
ただしローコスト住宅は、材料の大量発注や効率的な作業により低価格を実現しているため間取りやデザイン、設備などの標準仕様をオプションで変更する場合、高額な費用がかかる点に注意が必要です。
予算1,000万円台で家を建てる場合は、希望する条件の優先順位付けと、要望の取捨選択が重要だといえるでしょう。
<ローンシミュレーション>
- ローン借入額1,500万円
- 返済期間35年
- 元利均等方式で返済
- 固定金利 1.88%
- 頭金・ボーナス払いなし
フラット35を利用し、上記の条件で住宅ローンを借り入れた場合、月々の返済額は4万8,770円、総返済額は2,048万3,492円となります。
>>ローコスト住宅のデメリットは?メリットや注意点・向いてる方を紹介
>>ローコスト住宅はおすすめしないとされる理由は?おすすめの理由も紹介
5.1.1. 建築実例:ゆとりある2階建てプラン


全居室が南向きで明るいお部屋の2階建て4LDKで、シューズインクローゼット(SIC)や2帖のウォークインクローゼット(WIC)も備えた、ゆとりあるプランを実現しました。
5.2. 2,000万円台の家
予算が2,000万円台になると、1,000万円台よりも選択肢が広がります。
建設費の全国平均である3,000万円〜3,500万円には満たないため、希望の条件をすべて叶えるのは困難かもしれませんが、「浴室をグレードアップしたい」「オープンキッチンにしたい」など、特定の場所や設備であればある程度こだわりを反映できるでしょう。
<ローンシミュレーション>
- ローン借入額2,500万円
- 返済期間35年
- 元利均等方式で返済
- 固定金利 1.88%
- 頭金・ボーナス払いなし
フラット35を利用し、上記の条件で住宅ローンを借り入れた場合、月々の返済額は8万1,284円、総返済額は3,413万9,241円となります。
5.2.1. 建築実例:2世帯でもプライベートが守られるプラン


2世帯住宅でLDKや居室は世帯ごとで分け、部屋配置にも配慮しプライベートが守られる設計としました。世帯ごとに充実の収納スペースを設けながらもコンパクトな2世帯プランを実現しています。
5.3. 3,000万円台の家
建設費の全国平均は土地ありの場合3,717万円、土地なしの場合3,194.6万円です。
このため建設費の予算が3,000万円台であれば、比較的自由度の高い、自分好みの住宅が建てられます。
<ローンシミュレーション>
- ローン借入額3,500万円
- 返済期間35年
- 元利均等方式で返済
- 固定金利 1.88%
- 頭金・ボーナス払いなし
フラット35を利用し、上記の条件で住宅ローンを借り入れた場合、月々の返済額は11万3,798円、総返済額は4,779万4,965円となります。
5.4. 4,000万円台の家
建設費の予算が4,000万円台あれば、デザインや間取り、設備などほとんどの希望を叶え、ハイグレードな家を建てることができるでしょう。
<ローンシミュレーション>
- ローン借入額4,500万円
- 返済期間35年
- 元利均等方式で返済
- 固定金利 1.88%
- 頭金・ボーナス払いなし
フラット35を利用し、上記の条件で住宅ローンを借り入れた場合、月々の返済額は14万6,311円、総返済額は6,145万888円となります。
6. 家を建てる費用を安く抑える方法とは?

注文住宅は自由度が高いのが魅力ですが、こだわりすぎるとあっという間に予算オーバーしてしまうため注意が必要です。
家を建てる際は、主に以下のポイントを意識することで費用を安く抑えられます。
- 希望する条件に優先順位を付ける
- 床面積を狭くする
- 家の構造をシンプルにする
- 内装や設備のグレードを抑える
- 水回りを同じ場所にまとめる
- 複数のハウスメーカーで相見積もりを取る
- 減税制度や補助金を活用する
6.1. 希望する条件に優先順位を付ける
限られた予算内で理想の家をつくるには、希望条件に優先順位をつけることが大切です。
必要な機能や設備、家族の希望条件などをリストアップし、何にどれだけ費用をかけられるかあらかじめ予算配分を決めておきましょう。
6.2. 床面積を狭くする
住宅は床面積が大きくなるほど、より広い土地や多額の建築費用が必要になることからコストが高くなります。
このためあらかじめ自分たちにとって必要な家の広さを算出し、床面積を必要最低限に抑えれば、費用をカットできます。
国土交通省の資料では、世帯の人数別に、最低限必要な広さの基準となる「最低居住面積」、ライフスタイルに合わせてゆとりある暮らしができる広さの基準となる「誘導居住面積基準」について以下の目安を発表しています。
| 世帯人数別に面積(単位:㎡) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| 最低居住面積水準 | 25 | 30【30】 | 40【35】 | 50【45】 | |
| 誘導居住面積水準 | 都心とその周辺地域 | 40 | 55【55】 | 75【65】 | 95【85】 |
| 郊外や都市部以外 | 55 | 75【75】 | 100【87.5】 | 125【112.5】 | |
このように必要な家の広さは、家族構成や希望の暮らし方によって異なります。
イメージがつきづらい場合は、どのような用途の部屋がいくつ欲しいのか、部屋数や間取りから考えると具体的な数字が求めやすくなるでしょう。
6.3. 家の構造をシンプルにする
建物が複雑な形状だと、外壁や屋根の面積が広くなりコストが高くなります。
このためここ数年トレンドとなっているキューブ型住宅など、凹凸が少ない構造を選ぶと、柱や窓、外壁などの面積を減らして建築コストを抑えることが可能です。
その他1階と2階が同じつくりの総二階(そうにかい)建てにするなど、なるべくシンプルな構造を意識することで材料費、工事費の節約につながります。
6.4. 内装や設備のグレードを抑える
「予算オーバーしてしまったけど、どうしても叶えたい要望がある」場合は、優先順位が低い部分の費用を削るのも一つの手段です。
例えば内装・外装の装飾を抑える、こだわりが少ない設備のグレードを下げるなど、予算配分にメリハリを持たせることで、譲れない部分にお金をかけられます。
6.5. 水回りを同じ場所にまとめる
キッチン、浴室、トイレ、洗面所など水回りを分散させると給排水設備の設置が複雑になり、費用が高くなります。
このため水回りは一箇所にまとめるなど、可能な限り近い配置にすることで、配管の無駄を減らして費用を抑えることができます。
6.6. 複数のハウスメーカーで相見積もりを取る
同じグレードや希望条件でも、建築会社によって工事の得意・不得意は異なり金額にも違いがあります。
このためある程度希望がまとまったら、複数社に相見積もりを取って、内容や金額を比較、検討するのがおすすめです。
それぞれ得意とする領域やコストを確認し、予算内で自分たちの要望を叶えられそうな建築会社に依頼すると良いでしょう。
>>安く家を建てる方法は?注文住宅で費用を抑えるコツや注意点も紹介
6.7. 減税制度や補助金を活用する
家を建てる際は、使える減税制度や補助金を最大限活用することで、総費用を大きく抑えることができます。 国が用意している制度は毎年内容が変わることも多いため、早い段階で条件や対象になるかどうかを確認しておくことが重要です。
特に、住宅ローン利用者が対象となる「住宅ローン減税」、親や祖父母からの資金援助を受ける際に使える「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」、省エネ性能の高い住宅に適用される「子育てグリーン住宅支援事業」などは、家づくりの費用負担を減らせる代表的な制度です。
それぞれの特徴をおおまかに下の表にまとめています。
| 制度名 | 内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 住宅ローン減税 | 年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税が減額される制度 | 毎年の住宅ローン残高の0.7%を最長13年間、所得税から控除 |
| 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 | 父母・祖父母から住宅取得のために資金の贈与を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度 | 省エネ住宅等:1,000万円 一般住宅:500万円 |
| みらいエコ住宅2026事業 | 省エネ住宅の新築やリフォームに補助金を支給する制度(2025年の子育てグリーン住宅支援事業の後継制度) | 1戸あたり35~125万円 |
新築・注文住宅の補助金・減税制度・助成金については、こちらの記事で詳しく解説しているので是非ご覧ください。
>>2025年最新|新築・注文住宅の補助金・減税制度・助成金を詳しくご紹介!
>>【2025年最新】長期優良住宅の補助金・減税のメリットを徹底解説!
7. 家を建てる際の注意点
すでに土地を持っていることは、家を建てる際大きなアドバンテージとなります。
しかし、親や親戚から譲り受けた土地の場合は、相続税や贈与税などの税金が発生します。
また、譲り受けた土地の種類によっては、用途の変更手続きが必要なだけでなく、場合によっては家が建てられないこともあるため注意が必要です。
7.1. 相続や贈与された土地で家を建てる場合
親や親戚などから土地を譲り受けた場合、被相続人が亡くなったときは相続税、被相続人が存命中の場合は贈与税が発生します。
土地は相続時の評価額に対して課税されますが、基礎控除により3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)の範囲内であれば非課税となります。
一方、贈与税の場合は暦年課税制度または相続時精算課税制度のいずれかを選択できます。
暦年課税制度は、1年間に受けた贈与財産に応じて贈与税が課税される制度です。それに対して相続時精算課税制度とは、相続のときまで贈与税の支払いを先延ばしできる制度になります。
どちらの課税方法を選択したほうが良いかはケースによって異なるため、税理士への相談がおすすめです。
7.2. 地目が「宅地」以外の土地に家を建てる場合
土地には「地目」といって、不動産登記法によりそれぞれ主な用途が定められています。
このため地目が宅地以外の土地に家を建てる場合は、地目変更手続きが必要となります。
特に地目が田・畑の場合は、農地法で保護されているため、それぞれの自治体の条例に則って農地転用の手続きが必要です。
そもそも転用ができない場合もあるため、地目が田・畑となっている土地に家を建てたい場合は、まず地元の農業委員会に相談しましょう。
8. まとめ:家を建てる費用を知ろう
家を建てる費用は、「土地あり」「土地なし」「構造・地域・坪数」で大きく異なります。
事前に総費用と内訳、資金計画のポイントを押さえた資金計画を立てることで、理想のマイホーム実現と予算管理を両立しましょう。
住宅ローンの借入可能額や頭金などの自己資金や返済割合に基づいて、無理なく返済できる範囲内で予算を設定しましょう。
理想の家づくりのポイントは、希望条件に優先順位をつけることです。譲れないポイントにはお金をかける、反対にこだわりが少ない部分はコスト削減するなどして、お金の使い方にメリハリをつけると予算内で自分たちの要望を叶えることができます。
また、利用できる減税制度や補助金も忘れずに確認し活用しましょう。
コストとクオリティのバランスがとれた家づくりをご希望の方は、ぜひ「一建設」までご相談ください。
一建設は、飯田グループ傘下の中核企業です。圧倒的なスケールメリットを活かして、住宅の品質に影響しないコストカットを実現。高品質な住宅を低価格で提供しております。
「費用は抑えたいけど、家づくりは妥協したくない」方はぜひ候補の一つとしてご検討いただけますと幸いです。
一建設の注文住宅を見る
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
ご自宅の売却・引越し(住み替え)も一建設にお任せ
一建設の『ラクいえ売却』
住み替えによる不安を無くすために生まれた、一建設の『ラクいえ売却』。
住まいが売れるタイミングと新しい住まいが見つかるタイミングを合わせる必要がなく、
愛着のある住まいが高く売れるまで交渉する手間もありません。
ダブルローンをはじめとする自宅売却のお悩みを解消します。
- #売却後も1年間賃料無料で住み続けられるからゆとりをもった住み替えが可能
- #引越し費用を最大50万円一建設が負担で手厚くサポート
- #新生活に嬉しいキャッシュバック制度あり
- #一建設の取り扱い物件以外も売却可能
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
注文住宅のオプション53選!新築でやっておけばよかったと後悔しないための選び方や費用相場を紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅の費用相場は?価格帯・広さ別の相場と費用を抑えるコツを解説
「注文住宅を建てたいけど、一体どれくらいお金が必要なんだろう……。」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。そ...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

「平屋はやめたほうがいい?」平屋のメリット・デメリットを9つずつ解説
2024.09.24 | 平屋
おすすめ記事
-

2025.02.13 | 平屋
平屋とは?平屋のメリット・デメリットと建築実例をご紹介
戸建て住宅の一般的な階層構造としては、平屋と2階建て、3階建てがあります。これから家を建てる方のなかには、何階建てにす...
-

2024.03.15 | 注文住宅
注文住宅とは?メリット・デメリットや後悔しないためのポイントをわかりやすく解説
注文住宅は建売住宅(分譲住宅)に比べて間取りやデザインの自由度が高いのが魅力です。ただし、そのぶん建売住宅よりも費用が...
-

平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
2025.06.13 | 平屋
-

【違いを比較】注文住宅と建売(分譲)住宅はどっちがいい?価格差は?
2024.03.15 | 費用・制度
-

建ぺい率・容積率とは?家を建てる前に知っておきたい基礎知識
2025.03.10 | 費用・制度
新着記事
-

2026.01.19 | マイホーム
2階リビングの魅力とは?メリット・デメリットと後悔しないためのポイントを解説
立地条件によっては、1階にリビングを設けると、十分なスペースや日当たりを確保できないケースもあるでしょう。 その...
-

2025.12.12 | マイホーム
ウォークインクローゼット設置のおすすめの間取りとは?注意すべきポイントや建築実例を紹介
衣類や荷物が増えるほど、「スッキリ片づく収納がほしい」と感じる方は多いでしょう。そんな願いを叶えるのがウォークインクロ...
-

シューズインクローゼットとは?シューズクロークとの違いや種類、メリット・デメリットを解説
2025.12.12 | マイホーム
-

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
2025.12.12 | 注文住宅
-

家を建てるには何をすればいいのか。流れや費用などの基礎知識と4つの注意点!
2025.12.01 | マイホーム