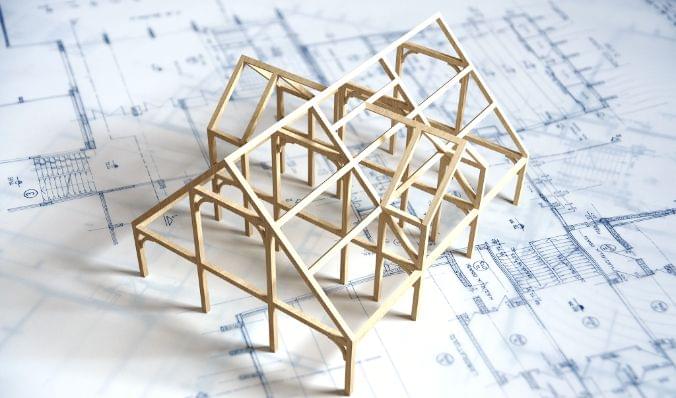家を建てるのにベストなタイミングとは?よくあるきっかけや必要な準備を解説|お役立ち情報|注文住宅・家を建てる・新築一戸建てのハウスメーカーなら一建設株式会社
2025.01.24 | マイホーム
家を建てるのにベストなタイミングとは?よくあるきっかけや必要な準備を解説

目次
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
家を建てるという選択は、人生のなかでも重要な決断の一つです。
このためマイホームの購入を検討しているものの「具体的にいつかは決めかねている」「本当に今がベストなのか自信がない」など、家を建てるタイミングで迷っている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、マイホーム購入時の年齢や平均年収などの世間の一般的な傾向や、家を建てるきっかけとなるタイミングを紹介します。ぜひ、自分たちにとってベストな時期を見極める参考にしてください。
1. 数字で見るみんなが家を建てるタイミング
まずは、政府の統計データから家を建てるタイミングに関する一般的な傾向を探ってみましょう。
国土交通省の「令和5年度市場動向調査報告書」によると住宅取得時の年齢、平均世帯年収、居住人数のデータは以下のとおりです。
- マイホーム購入時の年齢は30代が最も多い
- マイホーム購入時の平均世帯年収は約700万円~900万円ほど
- マイホーム購入時の平均居住人数は約3人
1.1. マイホーム購入時の年齢は30代が最も多い
注文住宅や分譲戸建て住宅、集合住宅の世帯主は30代が最も多く、マイホーム購入のメイン層であることがわかります。
その理由としては、結婚・出産などのライフイベントと経済的な事情が関係していると考えられます。
30代は、住宅購入のきっかけとなる結婚・出産などのライフイベントが集中しやすい傾向にあります。また、昇給などで年収が上がることが多く、20代からの貯蓄があれば経済的にもゆとりが生まれる時期です。
さらに住宅ローンの一般的な返済期間は30〜35年であることを考えると、30代で住宅ローンを組めば定年退職前に完済できる可能性が高いです。こういった事情から、多くの方にとって30代はマイホームを購入するのに最適なタイミングになっているのだと考えられます。
1.2. マイホーム購入時の平均世帯年収は約700万円~900万円ほど
次に、マイホーム購入時点の平均年収は一体どれくらいなのでしょうか?
同資料によると、住宅の一次取得者(住宅を初めて購入する人)の平均世帯年収は以下のとおりです。
注文住宅(全国平均):808万円
注文住宅(三大都市圏):924万円
分譲戸建住宅:721万円
参照:(2) 一次取得・二次取得別の世帯年収-令和5年度住宅市場動向調査報告書|国土交通省
上記を踏まえて考えると、マイホーム購入時の平均世帯年収は約700万円〜900万円程度といえます。
1.3. マイホーム購入時の平均居住人数は約3人
最後に、マイホーム購入時の居住人数をみてみましょう。
マイホーム購入時の平均居住人数は、注文住宅(全国平均)は3人(31.2%)です。次いで2人(25.9%)、僅差で4人(25.4%)の割合が多くなっています。
分譲戸建て住宅も同様に、最も割合が多い居住人数は3人(33.9%)です。しかし、次に割合が多いのは4人(33.3%)、3番目が2人(14.7%)で、注文住宅とは2番目と3番目が逆転した結果となっています。
いずれにせよ、上記のデータからマイホーム購入時の平均居住人数は約3人であり、夫婦+子一人の家族構成が多いと考えられます。
2. 家を建てるきっかけとなるタイミングをご紹介

家を建てようと考えるきっかけは人によってさまざまです。しかし、具体的なタイミングとしては主に以下が考えられます。
- 結婚したとき
- 子どもが生まれたとき
- 子どもが成長したとき
- 理想とする家で暮らしたくなったとき
- 年収が上がり、住宅ローンの見通しが立ったとき
2.1. 結婚したとき
多くの方にとって結婚は将来を意識する重要な節目となるため、家を建てるきっかけとなるタイミングの一つです。
パートナーと新たな家庭を築き、長期にわたって安心して暮らせる環境を求めたときに、持ち家という選択肢が思いつくのはごく自然なことです。
また、結婚によって転居が必要になる場合、賃貸で家賃を支払い続けるよりも経済的なメリットがあると考えて、マイホーム購入を検討する方もいるでしょう。
2.2. 子どもが生まれたとき
妊娠・出産も、マイホーム購入のきっかけとなる代表的なライフイベントです。
子どもができると学校や病院、公園などの周辺施設や、十分な広さのある住居など、今までとは異なる住環境が求められます。このことから、妊娠・出産を機に、子育てに適した地域で、子どもを育てやすい家を建てようと考える方は多いと考えられます。
2.3. 子どもが成長したとき
入園や入学、独立など子どもの成長の節目も、住宅購入のきっかけの一つです。
例えば、子どもが小さいうちは今の家で暮らし、子ども部屋が必要になった段階でマイホームを購入するのも選択肢の一つです。
転勤族の場合、子どもが幼稚園・保育園に入園したり、小学校に入学したりするタイミングで、子どもの転園や転校を回避するために、マイホームの購入を決意することもあるでしょう。
また、子どもが独立すると再び夫婦二人の暮らしが始まります。老後の生活を考えて、平屋への住み替えや、建て替えによるバリアフリー化などの形で住まいを見直すことも珍しくありません。
2.4. 理想とする家で暮らしたくなったとき
「今の家では住みにくい」「もっと広い家に住みたい」など、住居に対する不満や希望条件が出てきたときも家を建てようと考えやすいタイミングです。
賃貸の場合は既存の物件から選ぶ必要がありますが、注文住宅は間取りやデザインなどを自由に設計できるため、自分の理想とする生活空間を叶えやすいといえます。
また、賃貸物件はいくら家賃を支払い続けても自分のものにはなりませんが、マイホームは将来的に資産として残るのも大きな特徴です。このため今の家賃と住宅ローンの毎月の返済額を比べて金額がそれほど変わらないなら、マイホームを選ぶ方もいるでしょう。また、多少の差額があっても、金額に見合った価値を感じられるのであれば、それがマイホーム購入の決め手となります。
2.5. 年収が上がり、住宅ローン返済の見通しが立ったとき
住宅を購入する場合は住宅ローンを利用するのが一般的です。しかし、住宅ローンの借り入れは高額かつ返済期間が長期に及ぶことから、「審査に通るのか」「本当に毎月支払っていけるのか」などの不安を抱える方も多いでしょう。
金銭的な事情で家を建てる時期を迷っている場合は、昇進や昇格などで年収が上がったときや、ある程度まとまった貯蓄ができたときなど、資金に余裕が出てきたタイミングがおすすめです。
収入が安定してからのほうが、家計に負担のない住宅ローン借入額を検討しやすいため、返済の見通しも立ちやすくなります。
3. 住宅ローンを考慮したタイミングはいつ?

家を建てるタイミングを検討するうえで、知っておきたい住宅ローンの基礎知識は以下のとおりです。
- 住宅ローンの返済期間の考え方
- 住宅ローンの返済期間の目安
- 定年後も収入があれば家を建てるタイミングが遅くても問題ない
3.1. 住宅ローンの返済期間の考え方
住宅ローンの返済期間は30〜35年が一般的です。具体的な決め方としては、定年となる65歳までに完済できることが一つの目安となります。定年退職後は収入が下がることが多く、定年後も住宅ローンが残っていると支払いができなくなったり、老後の資金生活が苦しくなったりする可能性があるためです。
完済年齢は遅くとも定年までとし、毎月いくらなら返済が可能か、月々の返済額から逆算して借入額を決定すると、無理のない返済計画が立てやすいでしょう。
3.2. 住宅ローンの返済期間の目安は?
それでは、実際に最近家を建てた方の住宅ローンの返済期間はどれくらいなのでしょうか?
国土交通省の「令和5年度市場動向調査報告書」によると、住宅ローンの返済期間(全国平均)は、注文住宅や分譲戸建て住宅ともに35年以上が約7割、20年以上35年未満が約2割、10年以上20年未満と5年未満があわせて約1割でした。
マイホーム購入時の年齢は30代が最も多いことを考えると、65歳までの完済が理想とはいえ、現実にはそれ以上になる場合も多いようです。
3.3. 定年後も収入があれば家を建てるタイミングが遅くても問題ない
65歳以降も一定の収入が見込めるなど、住宅ローンの支払いに影響がないと考えられる場合は、完済時の年齢にあまり縛られる必要はありません。具体的には自営業の方や、高齢になっても収入が見込めるような職業の方が該当するでしょう。
特に自営業の方は、住宅ローンの審査が通りにくいため、会社員とは家を建てるタイミングも変わってきます。
金融機関によっては完済時の年齢を80歳までとしている場合もあるため、
審査を通過し、なおかつきちんと返済できる見通しがあれば、40代や50代など家を建てるタイミングが多少遅くなっても問題ないといえるでしょう。
4. 家を建てる前に準備しておきたいこと
住宅ローンの返済プランに無理があると、途中で返済が難しくなって生活が苦しくなるだけでなく、最悪の場合家を手放さざるを得ない可能性もあります。
そうならないためには、家を建てる前に可能な限り資金を蓄え、あらかじめ長期的な見通しを持って返済計画を立てることが重要です。
4.1. 貯金をしておく
住宅購入の際には、頭金といって建築費用の一部を自己資金から先払いするのが一般的です。
頭金なしでフルローンを組むことも可能ですが、頭金を多めに準備することで住宅ローンの借入額を減らし、返済負担を軽減できます。
副業を始める、固定費を見直すなどの方法で収入の増加または支出の削減を図り、頭金に回せる資金をしっかり蓄えておきましょう。
4.2. 住宅ローンの返済期間を考えておく
無理なく住宅ローンを返済するには、長期的な見通しで返済計画を立てることが重要です。
一般的には年齢とともに昇給や昇格などで年収はアップする傾向にありますが、転職で今よりも年収が低くなったり、病気や怪我などで休職し一時的に収入がなくなることも十分考えられます。また、セカンドキャリアで十分な収入が得られるかどうかを申し込み時点で予想するのはかなり難しいです。
上記の内容を考えると、住宅ローンは無理なく返済できる借入金額で、定年を迎えるまでに完済できる返済期間で組むのがおすすめです。
支払利息を抑えるためになるべく返済期間を短くしたいと考える方もいるかもしれませんが、資金に余裕ができたタイミングで、予定よりも前倒しで返済する繰り上げ返済も可能です。
5. 家を建てるときに知っておきたい制度
国は住宅の取得を支援するために、さまざまな補助金制度や税負担の軽減措置を用意しています。家を建てる前に自分が利用できそうな制度はないかチェックしておきましょう。
5.1. 住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅の取得や増改築をした場合の税負担を軽減する制度です。住宅ローンを利用して住宅を購入したり、100万円を超えるリフォームをした場合、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から最大13年間控除されます。(所得税から控除しきれない場合は住民税から控除)
新築住宅の主な適用条件は以下のとおりです。
- 引渡しから6ヵ月以内に居住を開始している
- 控除を受ける年末まで引き続き住んでいる
- 返済期間が10年以上である
- 床面積の1/2以上が居住用である
上記に加え、床面積が50m2以上の場合は、その年の所得額が2,000万円以下であること、40m2以上50m2未満の場合は1,000万円以下であることが条件になります。
控除が適用される期間や控除額の計算方法は、居住を開始した年によって異なりますので、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
参照:No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
5.2. ZEH支援事業
ZEH支援事業は、ZEHの新築住宅を購入・建築する方を対象とする補助金制度です。断熱性や省エネ性、創エネ性において国が定める一定の基準を満たしたZEH住宅の購入・新築を対象としています。
注文住宅・建売住宅などの戸建て住宅の場合は、戸建て住宅ZEH化等支援事業の対象となり、2025年4月1日以降ZEHの場合は55万円、ZEHよりさらに断熱性・省エネ性の高いZEH+の基準を満たす場合は90万円の補助が受けられます。 (2025年1月時点)
主な交付要件は、ZEH(またはZEH+)基準を満たしていること、ZEH支援事業の公募を執りおこなっている一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている事業者が住宅の取得に関与していることなどです。公募開始から先着順の受け付けとなるため、早めの申請をおすすめします。
>>2024年最新|注文住宅を建てるときに利用できる補助金・助成金、減税制度をご紹介!
6. 家を建てるタイミングを考えておこう

家を建てるのにベストなタイミングは人それぞれですが、政府の統計データによれば30代が最も多く、マイホーム購入のメイン層となっています。その背景としては、結婚・妊娠・出産などのライフイベントが集中しやすい時期である、収入も安定して住宅ローン返済の目処も立ちやすいなどの理由が考えられます。
また、老後の生活を考えると、収入が少なくなる定年退職前に住宅ローンを完済できるのが望ましいです。住宅ローンの返済期間は30〜35年が一般的であるため、30代で住宅ローンを組めば、定年退職までに完済できる可能性も高くなります。
コストとクオリティのバランスの取れた住宅をお求めの方には、一建設の注文住宅がおすすめです。分譲戸建て住宅のシェアNo.1(※)の飯田グループのグループ力を活かして、資材の大量発注や自社一貫体制など品質に影響しないコストカットが可能なため、高品質な住宅を低価格で提供しております。
注文住宅はもちろん、建売住宅や土地情報、リフォーム・リノベーションなど家に関することであれば何でもお気軽にご相談ください。
「間取り・家づくりのシミュレーション」や「ローンシミュレーション」など便利ツールもご用意しておりますので、少しでも住まいづくりのお役に立てれば幸いです。
※分譲戸建住宅市場におけるシェア(2023年4月1日~2024年3月31日住宅産業研究所調べ)
一建設で物件を探す
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
【新築でやっておけばよかった】注文住宅のオプションおすすめ一覧!|平均価格の相場や総額の費用も紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅を建てる際にかかる費用相場を価格・広さ別に解説
注文住宅の費用は多くの要素に影響され、予算の設定に悩む方は少なくありません。この記事では、注文住宅に係る費用の相場内訳...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

注文住宅(新築)のおしゃれなキッチン!後悔しない決め方や種類・価格相場を紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
おすすめ記事
-

2025.02.13 | 平屋
平屋とは?平屋のメリット・デメリットと建築実例をご紹介
戸建て住宅の一般的な階層構造としては、平屋と2階建て、3階建てがあります。これから家を建てる方のなかには、何階建てにす...
-

2024.03.15 | 費用・制度
【違いを比較】注文住宅と建売(分譲)住宅はどっちがいい?価格差は?
マイホームの取得を検討するなか、注文住宅にすべきか建売住宅(分譲住宅)にすべきかで迷う方は多いかと思います。設計の自由...
-

平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
2025.06.13 | 平屋
-

注文住宅とは?どのような意味?メリット・デメリットもわかりやすく解説
2024.03.15 | 注文住宅
-

家を建てるのに必要な期間は?家を建てる流れと最短で完成させるためのポイントを解説
2024.09.24 | 注文住宅
新着記事
-

2025.06.13 | 注文住宅
ハウスメーカーの選び方を知り、理想の住まいを実現しよう!
家づくりには、予算決めや土地探しなど多くの工程がありますが、そのなかでもハウスメーカー選びは家の完成度を左右する重要な...
-

2025.06.13 | 平屋
平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
家を建てるとき、誰もが一度は悩むのが「平屋にするか、2階建てにするか」の選択ではないでしょうか。それぞれにメリット・デ...
-

リビングに吹き抜けを設置するメリット・デメリットと注意するポイント
2025.06.13 | マイホーム
-

住宅ローンの平均は?みんなはいくら借りて、いくら返済しているのか解説
2025.05.19 | ローン
-

ウォークインクローゼット(WIC)とは?クローゼットとの違いとメリット・デメリットを解説!
2025.05.19 | マイホーム