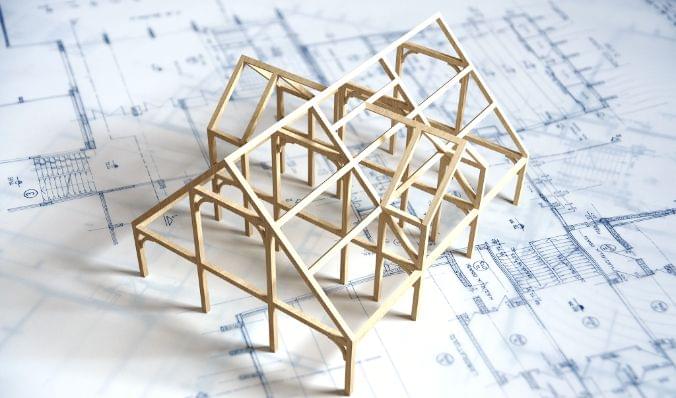2024年最新|注文住宅を建てるときに利用できる補助金・助成金、減税制度をご紹介!|お役立ち情報|注文住宅・家を建てる・新築一戸建てのハウスメーカーなら一建設株式会社
2024.11.18 | 費用・制度
2024年最新|注文住宅を建てるときに利用できる補助金・助成金、減税制度をご紹介!

目次
はじめの費用・制度
家づくりを進めるうえでは、価格と品質のバランスが非常に重要です。
一建設では、年間約9,000棟超の供給実績を活かし、コストを抑えながらも高品質な注文住宅を実現しています。
建築に必要な工程をすべて含んだ安心のコミコミ価格に加え、着工金や中間金が不要な資金計画の立てやすさも魅力です。
自社一貫体制による中間マージンの排除など、低価格を支える仕組みについて、詳しくは価格ページをご覧ください。
新築注文住宅の購入は大きな決断ですが、「マイホームを持つ夢を実現したいけれど、予算が気になる」という方も多いでしょう。そのようなとき、国や自治体の支援制度があなたの背中を押してくれるかもしれません。
そこでこの記事では、国や地方自治体が提供する補助金、助成金、そして減税制度をまとめました。各制度の適用条件や申請期限を詳しく記載しているので、ぜひ参考にしてください。
1. 注文住宅建築時に利用できる補助金はあるの?
新築住宅の建設を支援する制度は大きく分けて3つあります。
- 国からの補助金・助成金・給付金
- 自治体からの補助金・助成金
- 減税制度
国からの補助金・助成金・給付金は、全国規模で適用される支援制度です。例えば、省エネ性能の高い住宅を建てる際に利用できる「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業」や、長期優良住宅の認定を受けた住宅に対する補助金などがあります。
一方で自治体からの補助金・助成金は、地域特有のニーズや政策目標に基づいて計画されています。例えば、地元産材を使用した住宅建設への補助や、若年世帯・子育て世帯向けの住宅支援など、地域の実情に応じた制度が特徴です。
そして減税制度は、住宅取得にともなう税負担を軽減する制度です。代表的な制度には、住宅ローン減税や投資型減税、省エネリフォーム税制などがあります。
これらの制度を組み合わせることで、注文住宅の建設コストを軽減できます。ただし、制度の内容は年度ごとに変更されるケースもあるため、最新情報を確認しましょう。
2. 補助金を利用するメリットとデメリット
注文住宅づくりで補助金を活用するメリットとデメリットを解説します。
まずメリットは、補助金が原則的に返済不要であることです。これにより建築費用を抑えられます。補助金の額は制度によって異なりますが、例えば子育てエコホーム支援事業のように、最大100万円相当の金額補助を受けられることがあります。補助金の活用で、より高品質なマイホームを手の届く範囲で建てられるでしょう。
一方で、デメリットも存在します。補助金を受け取るためには一定の要件を満たす必要があり、その分の建築費用がかさんでしまうかもしれません。
例えば、長期優良住宅やZEH住宅などでは、断熱性や耐久性を高める必要があり、結果として初期投資が大きくなる傾向があります。
しかし、このデメリットは長期的な視点で見ると必ずしもマイナスとはいえません。住宅性能を高めることで日々の生活が快適になり、光熱費の削減ができ経済的メリットが得られます。つまり長く暮らすほど投資の価値が高まり、結果的にお得になる可能性が高いのです。
3. 国からの新築住宅の補助金・助成金制度

2024年に実施、または2024年も継続される国からの補助金・助成金には、次のような項目があります。下記でそれぞれ詳しく解説します。(予算に上限がある制度もあるため、必ず最新情報をご確認ください。)
- 子育てエコホーム支援事業
- 給湯省エネ2024事業
- LCCM住宅整備推進事業
- ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業
3.1. 子育てエコホーム支援事業
子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とした住宅支援制度です。この事業は対象世帯が新築住宅を取得する際や既存住宅の省エネ改修をおこなう場合に、経済的支援を提供することを目的としています。
| 対象者 | <子育て世帯> ・申請時点で2005年4月2日以降に出生した子がいる世帯 ※2024年3月31日までに建築着工する場合は2004年4月2日以降 <若者夫婦世帯> ・申請時点で夫婦どちらかが1983年4月2日以降に生まれた世帯 ※2024年3月31日までに建築着工する場合は1982年4月2日以降 |
|---|---|
| 対象となる新築住宅 | ・証明書等により、長期優良住宅に該当している ・証明書等により、ZEH水準住宅に該当している ※条件に関してはホームページ参照 |
| 補助金額 | 長期優良住宅:1住戸につき100万円 ZEH水準住宅:1住戸につき80万円 |
| 公式サイト | https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/ |
| 申請方法 | エコホーム支援事業者(ハウスメーカーや工務店などの住宅事業者)が建築主に代わって申請 |
| 申請期間 | 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日) |
申請は住宅事業者が建築主に代わっておこなうため、利用者の手続き負担が軽減されます。
3.2. 給湯省エネ2024事業
国が実施する省エネルギー促進のための補助金制度です。この事業は、家庭のエネルギー消費のなかで大きな割合を占める給湯分野に焦点を当てており、高効率な給湯器の導入を経済的に支援することを目的としています。
| 支援対象 | ・新築注文住宅または既存住宅の建築主 ・購入・リフォームを考えている |
|---|---|
| 補助金額 | <基本補助金額> ・ヒートポンプ給湯機:8万円/台 ・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式:10万円/台 ・家庭用燃料電池:18万円/台 <追加補助金額> ・ヒートポンプ給湯機、電気ヒートポンプ・ガス瞬間式:最大5万円/台の加算あり(性能による) ・家庭用燃料電池:2万円/台の加算あり ・上記のいずれかを購入+蓄熱暖房機の撤去:10万円/台の加算 ・上記のいずれかを購入+電気温水器の撤去:5万円/台の加算 |
| 公式サイト | https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/ |
| 申請期間 | 2024年3月29日~予算上限に達するまで(最長2024年12月31日) |
この事業を利用する際は、新築か既存か、どの種類の給湯器を導入するかなど、自身の状況を考慮し、最適な選択をすることが大切です。また、補助金額や条件の詳細は、公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
3.3. LCCM住宅整備推進事業
2024年度サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建て住宅部門は、日本政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、住宅分野の脱炭素化を推進するための施策です。
| 支援対象 | ・戸建て住宅の新築 ・強化外皮基準を満たす ・再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から25%以上の一次エネルギー消費量削減するもの ・再生可能エネルギーの導入 ・再生可能エネルギー等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上の一次 エネルギー消費量削減するもの など |
|---|---|
| 補助金額 | 設計費、建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の合計額の1/2(上限:1住戸につき140万円) |
| 公式サイト | https://www.kkj.or.jp/sustainable/lccm/lccm-gaiyo.html |
| 申請期間 | 2024年5月17日〜2025年1月20日まで(予算により早期終了の可能性あり) |
この事業は、環境負荷の少ない持続可能な住宅の普及促進を目的としています。
3.4. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)補助事業
“戸建住宅ZEH化等支援事業”は高性能な省エネ住宅の普及を目指す国の補助金制度です。この制度により高性能な住宅を手に入れやすくなり、同時に国全体の省エネ目標達成にも貢献できます。
| 支援対象 | ・新築住宅を建築・購入する個人 ・注文・建売のZEH住宅 |
|---|---|
| 補助金額 | ZEH:1住戸につき55万円 ZEH+:1住戸につき100万円/戸 |
| 公式サイト | https://zehweb.jp/ |
| 申請期間 | 単年度事業:2024年4月26日~2025月1月7日 複数年度事業:2024年11月5日~2025年1月7日 ※先着順、予算に達した時点で終了 |
ZEHは断熱性能と省エネ設備、そして太陽光発電などの再生可能エネルギー技術を組み合わせた住宅です。住宅で使用するエネルギーの削減で、光熱費も大きく抑えられます。
4. 新築住宅の購入時に利用できる減税制度

新築住宅を購入する際に利用できる減税制度はいくつか挙げられます。それぞれどのような内容かを見ていきましょう。
- 住宅ローン控除(減税)
- 住宅取得資金等の贈与税の軽減
- 不動産取得税の軽減措置
- 固定資産税の軽減措置
- 印紙税の特例措置
- 登録免許税の軽減措置
4.1. 住宅ローン控除(減税)
住宅ローン控除は、個人の住宅取得を支援する税制優遇措置です。主な目的は、国民が無理なく自身のニーズに合った住宅を手に入れられるようあと押しすることです。
この制度は、住宅ローンを利用して新築・購入・増改築をおこなったときに適用され、年末のローン残高の0.7%を所得税から最長13年間控除できます。控除しきれなかった分は翌年の住民税からも一部控除します。
2024年度税制改正後の住宅ローン減税の概要は以下のとおりです。
| 適用条件 | ・認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかで、床面積は50㎡以上 ※2024年末までの所得額が1,000万円以下の場合、床面積要件は40㎡以上 ・合計所得額が2,000万円以下 ・住宅ローンの借入期間が10年以上 ・引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居している ・昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合している |
|---|---|
| 控除金額 | ・長期優良住宅・低炭素住宅:最大31.5万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯は最大35万円) ・ZEH水準省エネ住宅:最大24.5万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯は最大31.5万円) ・省エネ基準適合住宅:最大21万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯は最大28万円) ・その他の住宅:控除は適用されない |
| 控除期間 | 最大13年間 |
| 手続き方法 | 確定申告時 |
4.2. 住宅取得資金等の贈与税の軽減
この制度は2022年1月1日から2023年12月31日までの期間に適用される特例措置でしたが、3年間(2024年〜2026年)延長されました。父母や祖父母などから、自身が居住するための住宅の新築、取得、または増改築などに充てる資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、定められた非課税限度額までの金額に関して贈与税が非課税となります。
| 適用条件 | ・断熱等性能等級が4以上または一次エネルギー消費量等級が4以上 ・耐震等級が2以上または免震建築物 ・高齢者等配慮対策等級が3以上 |
|---|---|
| 非課税になる金額 | ・省エネ等住宅の場合は最大1,000万円まで ※その他の住宅は最大500万円まで |
| 特例期間 | 2026年12月31日まで |
| 手続き方法 | ・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類を添えて申告 ・申告書と添付書類は、納税地を管轄する税務署に提出 |
参照:国税庁|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
4.3. 不動産取得税の軽減措置
住宅取得を促進するための税制優遇策です。通常、不動産取得税の税率は4%ですが、この特例措置により、住宅を取得した場合は3%に軽減されます。住宅購入者の経済的な負担を軽減し、住宅の取得や流通の促進を目的としています。
| 軽減される税率・金額 | ・住宅を取得した場合の税率:4%から3%に軽減 ・住宅を新築した場合の控除額:課税標準から最大1,200万円 ・住宅を建築した土地:評価額の軽減と減税 |
|---|---|
| 特例期間 | 2027年3月31日まで |
| 手続き方法 | 不動産が所在する都道府県税事務所に申告 |
| 手続き期限 | ・取得の日から60日以内(自治体による) ・還付申請可(但し登記翌日から5年以内) |
4.4. 固定資産税の軽減措置
この制度は居住水準の向上と質の高い住宅の促進が主な目的です。2024年度の税制改正により、固定資産税の軽減措置が2年間延長されました。条件を満たせば、固定資産税が通常の半額に軽減されます。この期間が経過したあと、通常の税額に戻るのが一般的です。
なお、固定資産税の軽減措置は、新築住宅だけでなく既存住宅の改修にも適用されます。例えば、耐震、バリアフリー、省エネなどの改修、長期優良住宅化リフォームをおこなった際は、翌年度の固定資産税が一定の割合で減額されます。
| 軽減される税率・金額 | ・新築住宅にかかる固定資産税:3年間2分の1に減額 ※マンションは5年間 ・新築の認定長期優良住宅にかかる固定資産税:5年間2分の1に減額 ※マンションは7年間 ・住宅用地(小規模住宅):価格×1/6 ・一般住宅用地:価格×1/3 |
|---|---|
| 特例期間 | ・新築住宅を建てた場合:2026年3月31日まで ・土地:特に期限なし |
| 手続き方法 | ・一般住宅:各自治体に申告 ・長期優良住宅:所管行政庁に申告 ・住宅用地:各自治体に申告 |
| 手続き期限 | 住宅を新築した年の翌年1月31日まで |
4.5. 印紙税の特例措置
この制度は、2014年4月1日から2027年3月31日までの期間に作成される特定の契約書に適用されます。土地建物売買契約書や建物建築工事請負契約書に対して印紙税の税額が軽減されます。
| 軽減される金額 | 最大50% |
|---|---|
| 特例期間 | 2027年3月31日までに契約締結分 |
| 手続き方法 | 手続きは特になし ※課税文書に対し、印紙税額相当の収入印紙を添付するのみ(特例あり) |
参照:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
参照:国税庁|No.7129 印紙税の納付方法
4.6. 登録免許税の軽減措置
新築住宅や土地の購入・取得に関する登録免許税には、一定期間に限り軽減措置が適用されています。この特例により、通常よりも低い税率で登記が可能となります。措置の適用には条件があるため、制度を受ける際は最新の内容と適用期間を確認することが大切です。
| 適用条件 | ・床面積50㎡以上の家屋 ・自宅として住んでいる ・取得から1年以内の登記 |
|---|---|
| 軽減される税率 | ・所有権の保存登記:0.4%から0.15% ・所有権の移転登記:2.0%から0.3% ・抵当権の設定登記:0.4%から0.1% |
| 特例期間 | ・家屋・抵当権:2027年3月31日まで ・土地:2026年3月31日まで |
| 手続き方法 | 登記時に軽減措置の適用条件を満たす証明書を提出 |
| 手続き期限 | 新築住宅・土地の購入から1年以内 |
参照:国税庁|登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
参照:財務省|登録免許税に関する資料
5. 自治体からの補助金・助成金制度

ここからは自治体で実施されている補助金・助成金制度の実例を紹介します。
- 北海道札幌市|札幌版次世代住宅補助制度
- 岩手県|住みたい岩手の家づくり促進事業
- 東京都|「東京ゼロエミ住宅」の新築等に対する助成事業
- 千葉県市川市|住宅の耐震診断・耐震改修に関する補助制度
- 静岡県藤枝市|子育てファミリー移住定住促進事業
- 愛知県|愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)
- 兵庫県神戸市|老朽空家等解体補助制度
5.1. 北海道札幌市|札幌版次世代住宅補助制度
断熱等基準の等級がシルバー以上の札幌版次世代住宅基準を満たす新築住宅を建てる方に対して、建築費用の一部を補助する制度です。環境に配慮した高性能住宅の普及を図り、札幌市の住環境の向上と省エネルギー化を推進しています。
| 対象 | ・札幌市内に新築する一戸建ての住宅 ・札幌市が設定したサステナブル要件を満たす新築住宅 |
|---|---|
| 補助金額 | ・プラチナ:220万円 ・ゴールド:180万円 ・シルバー:60万円 |
5.2. 岩手県|住みたい岩手の家づくり促進事業
岩手県では、良質な住環境の創出と岩手型住宅の普及を目指す制度です。具体的には、いわて木づかい住宅普及促進事業の補助を受けた県産木材を使用し、省エネやバリアフリー性能を証明する住宅に対して助成をおこないます。この取り組みは快適な暮らしの実現と同時に、地域資源の活用や環境配慮を促進します。
| 対象 | <新築住宅> ・木造一戸建ての新築住宅 ・住宅部分の面積が75㎡以上 ・住宅部分の15立方m以上県産木材を使用していること ・省エネ基準(断熱等対策等級4)以上であること ・2025年年3月15日までに工事が完了すること ・県内の建築業者が施工すること <リフォーム> ・建築基準に適合する住宅であること ・耐震基準を満たしている住宅であること ・省エネ基準(断熱等対策等級4)以上であること ・2025年年3月15日までに工事が完了すること |
|---|---|
| 補助金額 | ・断熱等対策等級4に適合:10万円 ・高齢者等配慮等級3に適合:10万円 ※どちらも性能証明書を取得した場合 |
参照:岩手県|令和6年度「住みたい岩手の家づくり促進事業」のご案内
5.3. 東京都|「東京ゼロエミ住宅」の新築等に対する助成事業
東京都は家庭部門の省エネ対策を強化するため、2019年度から新築でゼロエミ住宅を建てる建築主に対し、建築費用の一部を助成しています。地域特性に適した高い省エネ性能を持つ住宅の普及を目指しています。
| 対象 | 都内に新築する住宅の建築主(個人・事業者) |
|---|---|
| 補助金額 | ・戸建て住宅:30万〜210万円/戸 ・集合住宅等:20万〜170万円/戸 |
参照:クール・ネット東京 東京都地球温暖化防止活動推進センター|東京ゼロエミ住宅導入促進事業
参照:リーフレット(概要)
5.4. 千葉県市川市|住宅の耐震診断・耐震改修に関する補助制度
市川市は2018年4月1日より「市川市耐震改修促進計画」を策定し、建物の地震被害軽減に取り組んでいます。災害に強い安全で安心な街づくりを実現させるのが目的です。計画に基づいて既存建築物の耐震診断と耐震改修を推進しています。
| 対象 | 2000年5月31日以前に着工し、所有者または親族(一親等以内)が居住する2階建て以下の木造住宅 |
|---|---|
| 補助金額 | ・耐震診断:最大8万円 ・耐震改修 ∟1981年5月31日以前に着工した住宅:最大100万円 ∟1981年6月1日~2000年5月31日までに着工した住宅:最大50万円 |
5.5. 静岡県藤枝市|子育てファミリー移住定住促進事業
藤枝市は子育て世帯の定住促進と支援を目的とした補助金制度を導入しています。この制度は子育て世帯が市内で新築住宅を取得する際、最大130万円の補助金が受けられます。若い世代の住宅取得をあと押しし、同時に市の人口増加と地域活性化を図る取り組みです。
| 対象 | 新築住宅を購入し、18歳以下の子どもがいる世帯 ※年度の末日時点で満18歳以下 |
|---|---|
| 補助金額 | ・市外から転入した子育て世帯:50万円 ・市内で転居した子育て世帯:30万円 |
5.6. 愛知県|愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)
愛知県は東京一極集中の是正と地方の人材確保を目的とした移住支援事業を実施しています。東京23区から愛知県内へ移住する方に対し、県と市町村が協力して「移住支援金」を支給する制度です。移住にともなう経済的負担を軽減し、UIJターンの促進を目指しています。
| 対象 | ・東京23区に在住、または東京圏に在住し東京23区へ通勤したことのある方 ・移住支援金の申請日から継続して5年以上居住の意思がある方 など |
|---|---|
| 補助金額 | ・世帯の場合:1世帯につき100万円 ・単身の場合:1人につき60万円 |
参照:愛知県|愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について
5.7. 兵庫県神戸市|老朽空家等解体補助制度
神戸市では地域の安全性と景観の向上を目的とした取り組みを実施しています。老朽化や管理不足により危険な状態にある空き家の所有者に対して、解体費用の一部を補助する制度です。所有者の経済的な負担を減らし、危険な空き家の除去を促進します。
| 対象 | 1981年5月31日以前に着工した倒壊する恐れのある建物を解体する所有者 |
|---|---|
| 補助金額 | ・解体工事にかかった費用:最大60万円 ・延床面積100㎡以上かつ3戸以上の寄宿舎または共同住宅:最大100万円 |
6. 注文住宅建築時に利用できる補助金を確認しましょう
注文住宅を建築する際には、国や地方自治体が提供する省エネ住宅やZEHへの補助金、地域産材使用に対する助成、子育て世帯向けの住宅取得支援などの補助金を受けるのがおすすめです。
また、バリアフリー改修や再生可能エネルギー設備の導入に関する補助金も検討しましょう。ただし、これらの制度は地域や時期により変更される場合があるため注意が必要です。最新の情報を自治体のWebサイトや施工会社に確認しましょう。
一建設では注文住宅の補助金に関連するご相談も受け付けています。「資金計画に不安がある」「申請手続きの方法がわからない」という方でもお気軽にお問い合わせください。
>>一建設の注文住宅「はじめのまじめな注文住宅」
>>家を建てる費用の目安は?資金計画の建て方、費用を安く抑える方法を解説!
>>家を建てる前に知っておきたい、基礎知識と4つの注意点!
一建設で物件を探す
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
【新築でやっておけばよかった】注文住宅のオプションおすすめ一覧!|平均価格の相場や総額の費用も紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅を建てる際にかかる費用相場を価格・広さ別に解説
注文住宅の費用は多くの要素に影響され、予算の設定に悩む方は少なくありません。この記事では、注文住宅に係る費用の相場内訳...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

注文住宅(新築)のおしゃれなキッチン!後悔しない決め方や種類・価格相場を紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
おすすめ記事
-

2024.09.24 | 注文住宅
家を建てるのに必要な期間は?家を建てる流れと最短で完成させるためのポイントを解説
家を建てようと決めてから、実際に注文住宅が完成するまでには、一体どのくらい期間がかかるのでしょうか? 「そろそろ...
-

2025.06.13 | 平屋
平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
家を建てるとき、誰もが一度は悩むのが「平屋にするか、2階建てにするか」の選択ではないでしょうか。それぞれにメリット・デ...
-

平屋とは?平屋のメリット・デメリットと建築実例をご紹介
2025.02.13 | 平屋
-

【違いを比較】注文住宅と建売(分譲)住宅はどっちがいい?価格差は?
2024.03.15 | 費用・制度
-

注文住宅とは?どのような意味?メリット・デメリットもわかりやすく解説
2024.03.15 | 注文住宅
新着記事
-

2025.06.13 | 注文住宅
ハウスメーカーの選び方を知り、理想の住まいを実現しよう!
家づくりには、予算決めや土地探しなど多くの工程がありますが、そのなかでもハウスメーカー選びは家の完成度を左右する重要な...
-

2025.06.13 | 平屋
平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
家を建てるとき、誰もが一度は悩むのが「平屋にするか、2階建てにするか」の選択ではないでしょうか。それぞれにメリット・デ...
-

リビングに吹き抜けを設置するメリット・デメリットと注意するポイント
2025.06.13 | マイホーム
-

住宅ローンの平均は?みんなはいくら借りて、いくら返済しているのか解説
2025.05.19 | ローン
-

ウォークインクローゼット(WIC)とは?クローゼットとの違いとメリット・デメリットを解説!
2025.05.19 | マイホーム