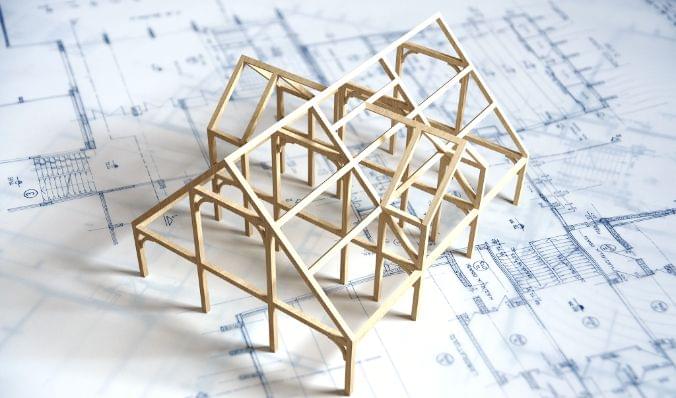2024.11.18 | 費用・制度
住宅性能評価とは?メリットから評価項目、申請方法まで詳しく紹介!

目次
はじめの費用・制度
家づくりを進めるうえでは、価格と品質のバランスが非常に重要です。
一建設では、年間約9,000棟超の供給実績を活かし、コストを抑えながらも高品質な注文住宅を実現しています。
建築に必要な工程をすべて含んだ安心のコミコミ価格に加え、着工金や中間金が不要な資金計画の立てやすさも魅力です。
自社一貫体制による中間マージンの排除など、低価格を支える仕組みについて、詳しくは価格ページをご覧ください。
住宅の購入を検討している方のなかには「住宅に関する知識がないため、良し悪しがわからない」と不安に思う方もいるでしょう。
そのような悩みを解決するのが住宅評価制度です。一般消費者でも住宅の性能が判断できるよう、専門機関が家の構造や劣化対策、火災時の安全性などそれぞれの項目を数値や等級で評価します。
この記事では、そんな住宅性能評価とは?について、その評価項目や住宅性能評価書を取得するメリット、住宅性能評価を受けるための申請方法などを解説します。
1. 住宅性能評価とは?
住宅性能評価とは、公平な立場にある第三者機関が住宅の性能を評価する制度です。
平成12年(2000年)4月1日施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められた「住宅性能表示制度」の基準に従って、国に登録された第三者機関が客観的に住宅の性能を評価します。
1.1. 品確法とは?
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)は、住宅の購入者が安心して良質な住宅を取得できるよう、住宅の品質確保に関するルールを定めた法律です。
品確法は、住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示」と「新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を10年間義務化」「トラブルを迅速に解決するための指定住宅紛争処理機関の整備」の3本柱で構成されています。
1.2. 住宅性能評価書の種類
住宅性能評価書とは、第三者機関が客観的に住宅の性能を評価した結果を表示した書面のことです。
住宅性能評価書は「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。
設計住宅性能評価書とは、住宅の設計段階で設計図書などをもとに住宅の性能を評価した結果をまとめたものです。
その後、住宅の建設・完成時に現場検査で設計住宅性能評価に表示された性能の基準を満たしているかどうかチェックし、その評価結果を建設住宅性能評価書にまとめます。
2. 住宅性能評価書の7つのメリット

住宅性能評価の取得は必須ではなく任意です。
取得に費用がかかることから不要だと考える方もいますが、住宅性能評価書を取得すると以下のようなメリットが得られます。
- 建物の性能がわかりやすい
- 専門家に確認してもらえる
- 資産価値が上がる
- トラブル時に紛争処理対応を受けられる
- 住宅ローン金利が優遇される場合がある
- 保険料が優遇される場合がある
- 優遇措置を受けられる場合がある
ここからはそれぞれの詳細を解説します。
2.1. 建物の性能がわかりやすい
住宅の性能は、耐震性や省エネ性、耐久性など目に見えない要素も多いです。
本来であれば、こういった住宅の性能は一般消費者にはよくわかりませんが、住宅性能評価を受ければ10分野33項目の評価項目がそれぞれ数値や等級で表示されるため、良し悪しが判断しやすくなります。
2.2. 専門家に確認してもらえる
住宅を公平な立場である第三者の専門家に確認してもらえるのは、住宅性能評価を受ける大きなメリットです。
特に、耐震性や耐久性など安全面に関わる部分をその道のプロに見てもらえる安心感は大きいでしょう。
それだけでなく、新築の場合は希望の性能が設計に反映されているか、設計どおりに施工されているかなどもチェックしてもらえるため安心です。
2.3. 資産価値が上がる
住宅性能評価書は、一定の基準を満たさない住宅には交付されません。
住宅性能書を取得した住宅は、国土交通省が定める一定の基準を満たしているという資産価値を証明できるため、売却の際に高い値段で売れる可能性があります。
また、性能の高さをアピールできる、専門的な知識がなくても住宅の性能を判断できるなどの点も将来売れやすさにつながることが期待できます。
2.4. トラブル時に紛争処理対応を受けられる
建売住宅の購入や注文住宅の建築などの家づくりでは、設計面や金銭面のトラブルが起きることも珍しくありません。
そのような場合、住宅性能評価書を取得した住宅であれば、指定住宅紛争処理機関を利用できます。
指定住宅紛争処理機関とは、裁判に頼らず住宅のトラブルを解決するために国土交通大臣から指定を受けた機関です。
住宅の性能評価に関わる問題だけでなく、請負契約、売買契約に関するすべての紛争処理を1件あたり1万円の手数料で依頼できます。
2.5. 住宅ローン金利が優遇される場合がある
住宅性能評価書を取得すると、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの金利優遇を受けられる場合があります。
また、住宅金融支援機構提携フラット35を利用する場合、一定の条件を満たす住宅は手続きの一部を省略してもらえます。
2.6. 保険料が優遇される場合がある
| タイミング | 保険始期 2014年6月30日以前 |
保険始期 2014年7月1日以降 |
|
|---|---|---|---|
| 免震建築物割引 | ▲30% | ▲50% | |
| 耐震等級割引 (構造躯体の倒壊等防止) |
耐震等級3 | ▲30% | ▲50% |
| 耐震等級2 | ▲20% | ▲30% | |
| 耐震等級1 | ▲10% | ||
引用:制度のメリット | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
地震保険とは、地震を原因とする火災や損壊などによる建物や家財の損害を補償する保険です。 特約など、火災保険に付帯する形で契約できます。
2.7. 優遇措置を受けられる場合がある
住宅性能表示制度と類似した制度としては、長期優良住宅認定制度があります。
長期優良住宅制度とは、劣化対策や耐震性、省エネ性など所定の基準を満たした住宅を「長く良好な状態で住み続けるための措置が講じられた性能の高い住宅」として認定することで、住宅ローンの減税や住宅資金贈与の非課税枠などの優遇が受けられる制度です。
住宅性能評価と長期優良住宅の評価基準は異なりますが、劣化対策や耐震性、温熱環境など重なる項目も多いため、住宅性能評価書と長期優良住宅の認定の両方を取得することで、税金や住宅ローンに関する優遇措置が受けられます。
3. 住宅性能の評価項目
新築住宅の住宅性能表示は、以下10分野に区分された33項目が定められています。
- 構造の安定
- 火災時の安全
- 劣化の軽減
- 維持管理・更新への配慮
- 温熱環境・エネルギー消費量
- 空気環境
- 光・視環境
- 音環境
- 高齢者等への配慮
- 防犯
赤字で表した4分野のうち10項目が必須分野として定められており、その他の評価項目は任意です。住宅性能評価機関に評価申請をする際に、評価を受けるかどうか自由に決められます。
ここからは、分野ごとの評価項目を詳しく解説します。
3.1. 構造の安定
住宅の基本構造となる柱や梁、壁などの基礎が、地震や暴風、積雪などの自然災害にどこまで耐えられるかを評価する分野です。
具体的には以下7つの評価項目が定められています。(赤は必須項目)
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを等級で表示 | ◯ ※免震建築物以外 |
◯ ※免震建築物以外 |
| 2 | 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 地震に対する構造躯体の損傷の生じにくさを等級で表示 | ◯ ※免震建築物以外 |
◯ ※免震建築物以外 |
| 3 | その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 免震建築物であるか否かを表示 | ◯ | ◯ |
| 4 | 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊等及び損傷の生じにくさを等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 5 | 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 屋根の積雪に対する構造躯体の倒壊、崩壊等及び損傷の生じにくさを等級で表示 | ◯ ※多雪区域のみ |
◯ ※多雪区域のみ |
| 6 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤又は杭の耐力及び地盤に見込んでいる耐力の根拠を表示 | ◯ | ◯ |
| 7 | 基礎の構造方法及び形式等 | 直接基礎の構造及び形式又は杭基礎の杭種、杭径及び杭長を表示 | ◯ | ◯ |
地震に対する住宅本体の倒壊、崩壊、損傷のしにくさを評価する耐震等級は1級〜3級までの等級で表示されます。
また、暴風や積雪に対する住宅本体の崩壊、倒壊、損傷のしにくさを評価する耐風等級と積雪等級は、ともに1〜2までの等級で表示されます。
等級は、数字が大きいほど性能が高いことを表します。
3.2. 火災時の安全
住宅内や近隣の住宅などで火災が発生した際に、人命や身体、財産を守るための安全対策を評価する分野です。
具体的には以下7つの評価項目が定められています。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) | 評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさを等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 2 | 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時) | 評価対象住戸の同一階又は直下の階にある他住戸等の火災時における避難のための共用廊下の対策について3項目で表示 | ◯ | |
| 3 | 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下) | 通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策を表示 | ◯ | |
| 4 | 脱出対策(火災時) | 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さを等級で表示 | ◯ ※地上3階以上 | ◯ |
| 5 | 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部)) | 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さを等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 6 | 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 延焼のおそれのある部分の外壁等(開口部以外)に係る火災による火熱を遮る時間の長さを等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 7 | 耐火等級(界壁及び界床) | 住戸間の界壁及び界床に係る火災による火熱を遮る時間の長さを等級で表示 | ◯ |
住宅や近隣の住宅から発生した火災を早期発見できるかを評価する感知警報装置設置等級や、住宅の防火性能を表す耐火等級は1〜4までの等級で表示されます。
3.3. 劣化の軽減
建物の劣化の進行を遅らせるための対策がどのくらい講じられているかを評価する分野です。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劣化対策等級(構造躯体等) | 構造躯体等の大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策の程度を等級で表示 | ◯ | ◯ |
劣化の軽減に関する評価項目は、必須項目である劣化対策等級(構造躯体等)のみです。
住宅が大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策が講じられているか1〜3の等級で表示します。
3.4. 維持管理・更新への配慮
給排水管やガス管の維持管理(清掃、点検、補修)のしやすさを評価する分野です。
具体的には以下4つの評価項目が定められています。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 維持管理対策等級(専用配管) | 専用の給排水管・給湯管及びガス管の清掃、点検及び補修を容易とするため必要な対策の程度を等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 2 | 維持管理対策等級(共用配管) | 共用の給排水管・給湯管及びガス管の清掃、点検及び補修を容易とするため必要な対策の程度を等級で表示 | ◯ | |
| 3 | 更新対策(共用排水管) | 共用排水管の更新を容易とするための必要な対策について2項目で表示 | ◯ | |
| 4 | 更新対策(住戸専用部) | 住戸専用部の間取りの変更を容易とするため必要な対策について2項目で表示 | ◯ |
共用配管や専用配管の清掃、点検、補修のしやすさを評価する維持管理対策等級は、1〜3の等級で表示されます。
3.5. 温熱環境・エネルギー消費量
なるべく少ない冷暖房で、室内を快適な温度環境を保つための対策がどのくらい講じられているかを評価する分野です。
具体的には以下2つの評価項目に分かれ、どちらも住宅性能評価の必須項目となっています。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 断熱等性能等級 | 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度を等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 2 | 一次エネルギー消費量等級 | 一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度を等級で表示 | ◯ | ◯ |
住宅の断熱性能(室内と外気の熱の出入りのしやすさ)を評価する断熱等性能等級は、1〜7級の等級で表示されます。
一次エネルギーとは、冷暖房や換気、給湯、照明など住宅内で消費されるエネルギーのことです。その消費量を削減するための対策がどのくらい講じられているか、いわゆる住宅の省エネ性能を評価する一次エネルギー消費量等級は1〜7までの等級があります。
3.6. 空気環境
住宅内の空気環境を評価する分野です。
健康障害を引き起こすホルムアルデヒドや室内の換気などへの対策を、以下3つの項目で評価します。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等) | 居室の内装の仕上げ及び天井裏等の下地材等からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策を等級で表示 | ◯ | ◯ |
| 2 | 換気対策 | 室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するための必要な換気対策について2項目で表示 | ◯ | ◯ |
| 3 | 室内空気中の化学物質の濃度等 | 評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法を表示 | ◯ | ◯ |
住宅の内装仕上げや天井裏などのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策を評価するホルムアルデヒド対策は、1〜3の等級で表示されます。
3.7. 光・視環境
住宅の光・視環境を評価する分野です。日照や採光など、視界に負担をかけない明るさが確保できているかを、以下の2項目で評価します。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 単純開口率 | 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の床面積に対する割合の大きさを表示 | ◯ | ◯ |
| 2 | 方位別開口比 | 居室の外壁又は屋根に設けられた開口部の面積の各方位毎の比率の大きさを表示 | ◯ | ◯ |
3.8. 音環境
話し声や足音など騒音の伝わりにくさを評価する分野です。
具体的には以下4つの評価項目が定められています。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重量床衝撃音対策 | 居室に係る上下階との界床の重量床衝音を遮断する対策について、等級または相当スラブ厚を表示 | ◯ | |
| 2 | 軽量床衝撃音対策 | 居室に係る上下階との界床の軽量床衝撃音を遮断する対策について、等級または軽量床衝撃音レベル低減量を表示 | ◯ | |
| 3 | 透過損失等級(界壁) | 居室の界壁の構造による空気伝搬音の遮断の程度を等級で表示 | ◯ | |
| 4 | 透過損失等級(外壁開口部) | 居室の外壁に設けられた開口部に方位別に使用するサッシによる空気伝搬音の遮断の程度を等級で表示 | ◯ | ◯ |
壁やサッシなどがどのくらい音を遮断できるか評価する透過損失等級は、1〜4級までの等級で表示されます。
3.9. 高齢者等への配慮
高齢者や障がい者が生活しやすいよう、部屋の配置や廊下の広さなど、身体の負担を軽減する工夫がされているかを評価する分野です。以下2つの評価項目で、それぞれ1〜5級の等級で表示されます。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分) | 住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を等級で表示 | ◯ | |
| 2 | 高齢者等配慮対策等級(共用部分) | 共同住宅等の主に建物出入口から住戸の玄関における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を等級で表示 | ◯ |
3.10. 防犯
住宅の防犯面を評価する分野です。
| 評価項目 | 概要 | 戸建て | マンションなどの共同住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 開口部の侵入防止対策 | 通常想定される侵入行為による外部からの侵入を防止するための対策を講じているか否かを表示 | ◯ | ◯ |
評価項目は、開口部の侵入防止対策のみで、窓やドアなどの開口部からの侵入防止対策がどのくらい講じられているかを評価します。
4. 住宅性能評価書の申請の仕方

住宅性能評価の申請は、国土交通省に登録されている住宅性能評価機関におこないます。
以下のリンクから、住宅の所在地を業務エリアとしている評価機関を検索可能です。
>>登録住宅性能評価機関の検索|一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
住宅性能評価の申請は、売り主、買い主、仲介人の誰でも可能ですが、新築の場合は、事前に建築会社に相談するのがおすすめです。計算書や設計図書など必要書類を揃えるサポートをしてくれるほか、申請を代行してくれるケースもあります。
住宅性能評価がおこなわれるタイミングは、新築の場合、設計段階と建物完成時です。着工前に設計住宅性能評価書が、引渡し前に建設住宅性能評価書がそれぞれ交付されます。
原則4回おこなわれる現場検査のタイミングは以下のとおりです。
- 基礎配筋工事
- 躯体工事の完了時
- 下地張り直前の工事の完了時
- 竣工時
中古住宅などの既存住宅の場合は、住まいの劣化や不具合を目視で確認する現況検査のみがおこなわれます。
5. 住宅性能評価にかかる費用はいくら?

住宅性能評価書を取得するためにかかる費用は、戸建てかマンションかなどの住宅の種類や、評価を依頼する項目数によって異なります。
地域や評価機関によっても異なりますが、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書、それぞれの取得で10万円〜20万円程度かかるのが一般的です。
つまり、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書を合わせて取得する場合、30万円前後の費用がかかります。
6. 評価書取得で注意するポイント
住宅性能評価書の取得にはさまざまなメリットがありますが、以下のように注意すべきポイントもあります。
- 等級に関して総合的な判断が必要
- 工事費が上がる
- トラブルの可能性はある
それぞれの詳細を解説します。
6.1. 等級に関して総合的な判断が必要
「せっかく家を建てるなら、すべての項目で等級を高くしたい」と思う方もいるかもしれません。
しかし、評価項目には相反する関係のものがあるためそれは困難です。例えば、採光性を高めようと窓を大きくした結果、断熱性能が低下するなどの場合があります。
住宅は全体のバランスが重要です。すべての項目で等級を高くしようとするのではなく、住宅に求める性能の優先順位や周辺環境を考慮して総合的に判断しましょう。
6.2. 工事費が上がる
住宅性能評価で高い評価や等級を取得するには、住宅性能を上げる必要があります。
住宅性能を上げるには質の良い材料や高い技術が求められるため、その分工事費用は高くなります。
別途追加工事が必要になる場合もあるため、予算との兼ね合いも考えなくてはなりません。
6.3. トラブルの可能性はある
設計住宅性能評価書、建設住宅性能評価書を取得した住宅は、専門機関によるチェックが入っていることから、一般的な住宅よりトラブルが起きる可能性が低いといえます。また、もし何かトラブルが発生した場合でも、1件あたり1万円の手数料で指定住宅紛争処理機関を利用できるのも魅力です。
しかし、だからといってトラブルが発生しないわけではありません。評価対象以外の箇所はチェックされません。住宅性能評価を取得するからといって油断せず、施工実績が豊富で信頼できる建築会社を選ぶことが重要です。
7. 住宅性能評価を知ろう
住宅性能評価とは、第三者機関に住宅の性能を法律の基準に則って評価してもらうことです。
耐震性や耐久性など目に見えない住宅の性能を専門家に確認してもらえることから、安心して暮らせる、売却する際に高く売れる可能性があるなどのメリットがあります。住宅性能評価書の取得は必須ではなく任意のため「長く安心して快適な家づくりがしたい」方は検討してみると良いでしょう。
一建設は、分譲住宅年間販売棟数日本一の飯田グループの傘下にある中核企業です。分譲戸建てで培ったノウハウを活かし、高品質な住宅を低価格で提供しています。
住宅性能評価でも、以下4分野6項目での最高等級取得を標準化しているため、長く安心して快適に住み続けられる家づくりが可能です。
| 構造の安全性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 3級 |
| 耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 3級 | |
| 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止) | 2級 | |
| 劣化の軽減 | 劣化対策等級(構造躯体等) | 3級 |
| 維持管理・更新への配慮 | 維持管理対策等級(専用配管) | 3級 |
| 空気環境 | ホルムアルデヒド発散等級 | 3級 |
「コストとクオリティのバランスがとれた家を建てたい」「想いも価格も妥協したくない」方はぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。
一建設の注文住宅を見る
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
ご自宅の売却・引越し(住み替え)も一建設にお任せ
一建設の『ラクいえ売却』
住み替えによる不安を無くすために生まれた、一建設の『ラクいえ売却』。
住まいが売れるタイミングと新しい住まいが見つかるタイミングを合わせる必要がなく、
愛着のある住まいが高く売れるまで交渉する手間もありません。
ダブルローンをはじめとする自宅売却のお悩みを解消します。
- #売却後も1年間賃料無料で住み続けられるからゆとりをもった住み替えが可能
- #引越し費用を最大50万円一建設が負担で手厚くサポート
- #新生活に嬉しいキャッシュバック制度あり
- #一建設の取り扱い物件以外も売却可能
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
注文住宅のオプション53選!新築でやっておけばよかったと後悔しないための選び方や費用相場を紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅の費用相場は?価格帯・広さ別の相場と費用を抑えるコツを解説
「注文住宅を建てたいけど、一体どれくらいお金が必要なんだろう……。」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。そ...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

「平屋はやめたほうがいい?」平屋のメリット・デメリットを9つずつ解説
2024.09.24 | 平屋
おすすめ記事
-

2025.12.12 | 注文住宅
カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
家づくりの際は、敷地面積に対して建物が占める割合を示す「建ぺい率」が建物の大きさや形、配置に大きく影響します。 ...
-

2025.03.10 | 費用・制度
建ぺい率・容積率とは?家を建てる前に知っておきたい基礎知識
広い土地と十分な資金さえあれば、大きな家が建てられると思っていませんか?実は、建てられる建物の大きさは、自治体によって...
-

注文住宅とは?メリット・デメリットや後悔しないためのポイントをわかりやすく解説
2024.03.15 | 注文住宅
-

家を建てるのに必要な期間は?家を建てる流れと最短で完成させるためのポイントを解説
2024.09.24 | 注文住宅
-

【違いを比較】注文住宅と建売(分譲)住宅はどっちがいい?価格差は?
2024.03.15 | 費用・制度
新着記事
-

2026.01.19 | マイホーム
2階リビングの魅力とは?メリット・デメリットと後悔しないためのポイントを解説
立地条件によっては、1階にリビングを設けると、十分なスペースや日当たりを確保できないケースもあるでしょう。 その...
-

2025.12.12 | マイホーム
ウォークインクローゼット設置のおすすめの間取りとは?注意すべきポイントや建築実例を紹介
衣類や荷物が増えるほど、「スッキリ片づく収納がほしい」と感じる方は多いでしょう。そんな願いを叶えるのがウォークインクロ...
-

シューズインクローゼットとは?シューズクロークとの違いや種類、メリット・デメリットを解説
2025.12.12 | マイホーム
-

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
2025.12.12 | 注文住宅
-

家を建てるには何をすればいいのか。流れや費用などの基礎知識と4つの注意点!
2025.12.01 | マイホーム