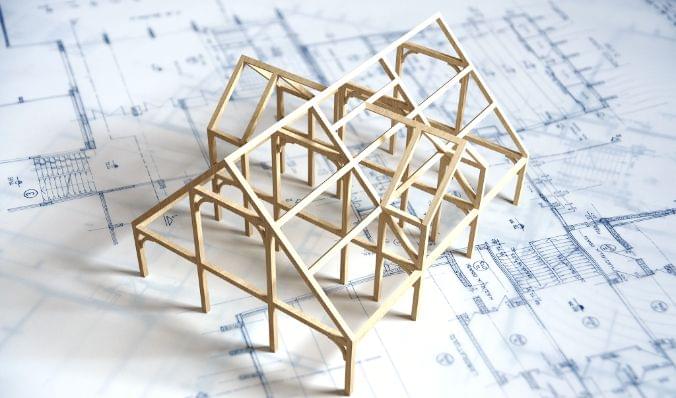耐震等級とは?等級1~3の違いや等級の調べ方、等級を上げる方法を解説!|お役立ち情報|注文住宅・家を建てる・新築一戸建てのハウスメーカーなら一建設株式会社
2024.11.18 | 費用・制度
耐震等級とは?等級1~3の違いや等級の調べ方、等級を上げる方法を解説!

目次
はじめの費用・制度
家づくりを進めるうえでは、価格と品質のバランスが非常に重要です。
一建設では、年間約9,000棟超の供給実績を活かし、コストを抑えながらも高品質な注文住宅を実現しています。
建築に必要な工程をすべて含んだ安心のコミコミ価格に加え、着工金や中間金が不要な資金計画の立てやすさも魅力です。
自社一貫体制による中間マージンの排除など、低価格を支える仕組みについて、詳しくは価格ページをご覧ください。
世界の面積に占める日本の国土の割合は0.25 %ですが、それに対してマグニチュード(M)6以上の地震回数は20.8%と高い発生割合を占めています。
近年では、M7.3を記録した2016年の熊本地震、M7.6を記録した2024年の能登半島地震が記憶に新しいことでしょう。
このように近年頻発する大地震を踏まえて、地震に強い家を建てたいと考えている場合は、住宅の耐震性を評価する「耐震等級」という指標が重要です。
そこでこの記事では、住宅の性能を評価する項目の一つである耐震等級とは?を解説します。
耐震等級1〜3の基準の違いや自宅の耐震等級の調べ方、耐震性の高い家づくりのポイントなどを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 耐震等級とは
耐震等級とは、住宅の性能を表す「住宅性能表示」の項目の一つで、地震に対する耐震性(建物の強さ)を示す指標です。
住宅性能表示のなかでも「構造の安定に関すること」の評価分野に含まれ、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)と耐震等級(構造躯体の損傷防止)の2項目をそれぞれ1〜3の等級で評価します。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)は、地震に対する住宅本体の倒壊、崩壊のしにくさを、耐震等級(構造躯体の損傷防止)では、地震による損傷の生じにくさがそれぞれ評価されます。
1.1. 制震と免震との違い
耐震と似ている言葉としては、制震や免震などが挙げられます。
制震は地震による振動を吸収する制震部材を建物に組み込むことで、地震の揺れを軽減する仕組みを指します。
一方、免震は、地盤からの影響を抑えて建物へのダメージを軽減する仕組みです。
このように耐震と免震はそれぞれ手法は異なるものの、どちらも地震による揺れを軽減し、建物へのダメージを減らす仕組みです。
1.2. 耐震基準との違い
一方、耐震とは、地震に対する建物自体の強度を表す言葉です。
耐震性能を示す主な指標は、耐震等級と耐震基準の2つがあります。
耐震基準は、1950年に制定された建築基準法によって人命を守ることを目的に定められました。直近では2000年に改正がおこなわれています。
それに対して耐震等級は、2000年に制定された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって定められたものです。人命を守ることに加えて建物そのものを守る目的があります。
どちらも耐震性に関わる基準ですが、異なる法規によって定められているため両者に連動性はありません。
2. 耐震等級1、等級2、等級3の違い

耐震等級では、地震に対する建物の強度(崩壊、倒壊、損傷のしにくさ)を以下の1〜3の等級で評価します。
住宅性能表示の評価では、等級の数字が大きいほど性能は高くなります。
ここからは、耐震等級1〜3の評価基準や違いを解説します。
2.1. 耐震等級1
耐震等級のなかでは最も低い等級で、建築基準法で定められている耐震基準と同等の性能です。
これから建物を建てる場合、最低でも耐震等級1の基準を満たす必要があります。
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の項目では、建築基準法で定められている「極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震力」に耐えられるものが等級1の評価基準です。
それに対して、耐震等級(構造躯体の損傷防止)の項目では、建築基準法で定められている「希に(数十年に一度程度)発生する地震力」に耐えられるものを等級1として表示します。
建築基準法で震度は明記されていませんが、極めて希に発生する地震=震度6強〜7程度、希に発生する地震=震度5強程度と想定すると理解しやすいでしょう。
参照:地震などに対する強さ(構造の安定)|一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
2.2. 耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性能です。
具体的には、等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度、損傷を生じない程度を示します。
災害時の避難所として指定される学校などの公共施設や、長く安心して暮らせる住宅として認定された「長期優良住宅」では、耐震等級2以上の強度が定められています。
2.3. 耐震等級3
耐震等級のなかで最も高い等級です。
等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に対して倒壊や崩壊しない程度、損傷を生じない程度の耐震性能があります。
消防署や警察署など防災拠点となる施設に採用されている基準で、震度6〜7の地震でも倒壊・崩壊しないレベルの性能です。
近年では大地震の際、耐震等級1、等級2の住宅が複数全壊または倒壊する被害が多く報告されています。
そのような状況でも、耐震等級3の住宅は震源地周辺にあるものを含めてもほぼ無被害、あっても軽微な被害にとどまったという報告が注目を集め、最近は「将来起こりうる大地震に備えて耐震等級3を取得しよう」との考え方が広まりつつあります。
参照:「熊本地震における建築物被害の原因 分析を行う委員会」報告書のポイント|国土交通省
2.4. 耐震等級3“相当”とは
耐震等級の認定には、国土交通省に認定された登録住宅性能評価機関による評価が必要です。
しかし、建築会社のなかにはこの評価を受けずに、耐震等級3と同等の材料・技術を使用している住宅を耐震等級3“相当”として表現する場合があります。第三者機関が検査して認定したわけではないため、あくまでも目安程度に考えましょう。
また、後述する地震保険料の割引、住宅ローンの金利優遇なども受けられないため注意が必要です。
3. 耐震性が高い家を建てるメリットとデメリット
耐震等級2や等級3など、耐震性が高い家を建てる主なメリット・デメリットは以下のとおりです。
<メリット>
<デメリット>
それぞれの詳細を解説します。
3.1. メリット①地震時の被害が少なくなる
耐震等級3などの耐震性が高い家は、等級1、等級2の家と比較して地震に耐えうる構造であることから、地震の被害が少なくなります。
命を守れる、地震による怪我を防げるなど安全性の確保はもちろん、避難生活のリスクを減らせる、地震後の補修費用を抑えられるなど、経済的・精神的なメリットがあります。
3.2. メリット②低金利でローンを借り入れられる
耐震等級が2以上になると、金融機関によっては住宅ローンの金利優遇が受けられる場合があります。
例えば、新築住宅で住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供するフラット35を利用する場合、耐震等級3の住宅は最初の5年間0.5%金利が低くなる【フラット35】S(金利Aプラン)、耐震等級2の住宅は0.45%金利が低くなる【フラット35】S(金利Bプラン)が適用されます。(2024年10月現在)
【フラット35】S:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】|住宅金融支援機構】
3.3. メリット③地震保険料の割引を受けられることがある
住宅性能評価を受けると、評価された耐震等級に応じて地震保険料の割引が受けられます。
| 耐震等級 | 保険始期 2014年6月30日以前 |
保険始期 2014年7月1日以降 |
|
|---|---|---|---|
| 耐震等級割引 (構造躯体の倒壊等防止) |
耐震等級3 | ▲30% | ▲50% |
| 耐震等級2 | ▲20% | ▲30% | |
| 耐震等級1 | ▲10% | ||
地震保険とは、火災保険のオプションや特約として契約できる保険です。地震や津波、地震を原因とする火災など、火災保険の適用外となる被害が補償されるため加入しておくと安心です。
3.4. デメリット①コストがかかる場合が多い
耐震性を高めるには、耐力壁など質の良い材料を使用する、耐震金物などで補強する、建物内の柱や壁を増やすなどの方法があります。
このように耐震等級を上げようとすると材料費や工事費がかかるため、建築コストが上がります。
3.5. デメリット②間取りの自由度が下がる可能性がある
耐震性には、間取りが大きく影響します。
例えば、上下階の天井と床を設けずにつなげることで、開放感のある空間を演出できる「吹き抜け」をつくると、柱が少なくなるため耐震性が低くなる可能性があります。また、耐震性には柱や壁の数が関係しているため、大きな窓や広いリビングルームなども、耐震性が低くなる原因です。
このように住宅の耐震性を上げようとすると、間取りの自由度が下がる、希望している条件が実現できない場合があるなどのデメリットがあります。
4. 自宅の耐震等級の調べ方
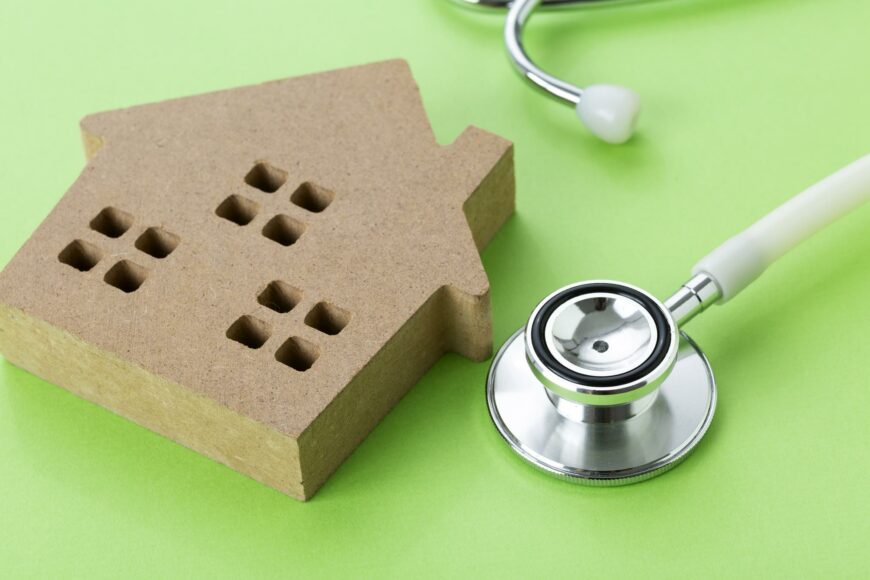
自宅や中古住宅などすでに建てられている建物の耐震等級を調べるには、主に以下の方法があります。
ここからは、それぞれの方法を解説します。
4.1. 住宅性能評価書を確認する
すでに住宅性能評価を受けている場合は、住宅性能評価書で住宅性能を確認できます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が制定された2000年以降の建物で住宅性能評価を受けているかわからない場合は、管理会社や不動産業者、建築会社などに問い合わせると良いでしょう。
4.2. 登録住宅性能評価機関に評価を依頼する
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が制定される前の建物や、住宅性能評価を受けていない場合は、住宅性能評価を受ける必要があります。
住宅の所在地を対応エリアとしている登録住宅性能評価機関を以下のリンクから検索し、評価を依頼しましょう。
>>登録住宅性能評価機関の検索|一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
住宅性能評価書を取得するためにかかる費用は、地域や住宅の種類(戸建てかマンションか)、評価機関や評価する項目数によって異なりますが、およそ10万円〜20万円程度となるのが一般的です。
4.3. 専門家の耐震診断を受ける
住宅性能評価以外で耐震性を調べるには、耐震診断という方法もあります。
耐震診断とは、1981年5月31日までの旧耐震基準で建てられた建物の耐震性の有無を、1981年6月1日以降から適用されている新耐震基準で確認することです。
旧耐震基準の建物は震度6以上の地震で倒壊してしまう可能性が高いため、耐震診断を受けることで自宅の耐震性や耐震改修の目安がわかるなどのメリットがあります。
耐震診断にかかる料金の目安は以下のとおりです。
| 構造 | 延床面積 | 料金 |
|---|---|---|
| RC造(鉄筋コンクリート造) | 1,000㎡~3,000㎡ | 約2,000円/㎡~約3,500 円/㎡ |
| S造(鉄骨造) | 1,000㎡~3,000㎡ | 約2,500円/㎡~4,000円/㎡ |
| 木造住宅 | 120㎡程 | 60万円~100万円 |
5. 耐震等級の高い家にする方法
最低限の耐震性能である耐震等級1ではなく、耐震性の高い等級2、等級3の家を建てるためには主に以下のような方法があります。
それぞれの方法を詳しく解説します。
5.1. 建物を軽量化する
軽いものより重いもののほうが、地震の力はより大きく伝わります。
このため耐震性においては、建物の重量が軽いほど有利です。
特に屋根が重いと、建物の重心の位置が高くなって揺れの影響がより大きくなります。例えば、陶器瓦やセメント瓦などの重い屋根材ではなく、スレート瓦、金属屋根材など軽量の屋根材を使用するのが効果的です。
5.2. 耐力壁の配置バランスを考慮する
耐力壁とは、地震や風など横方向に揺れる力に耐えるための建築材料です。
通常より頑丈な壁であるため、建物の強度を高めるために使用されます。
耐震性の向上には、耐力壁の数だけでなく配置も重要です。配置がアンバランスだと、地震時に変形やねじれが発生し、建物が倒壊する恐れがあります。基本的には間取りを四角形に分割し、コーナーを固めていくようにバランスよく配置することが重要です。
5.3. 柱の数を増やす
柱や梁には、壁や屋根など建物の重さを支える役割があります。
このため柱を増やす、補強材料を巻きつけて柱を補強するなどの方法で、建物の耐震性や耐久性を高められます。
5.4. 基礎・床の耐震性をあげる
耐震性の向上には、壁や柱だけでなく、建物の下部構造である基礎や床も重要です。
基礎は、その上に載っている建物を一体化して支える役割があるため、どのように上の構造がしっかりしていても基礎が脆弱だと、地震の際に建物の構造部がバラバラになってしまいます。
また、床に強度がないと、耐力壁が本来の効力を発揮できず、地震時に変形やねじれが起きる可能性があります。
このため基礎や床部分も建築段階でしっかり補強することが重要です。
6. 住宅購入時に注意するポイント
住宅を購入する際、耐震等級に関して注意すべき主なポイントは以下のとおりです。
それぞれの詳細を解説します。
6.1. 耐震等級の取得は必須ではない
耐震等級を含む住宅性能評価の取得は任意です。
住宅性能評価を受けなくても、建築基準法を遵守していれば建築許可は下りるため、住宅性能評価を受けるかどうかの判断は施主に委ねられます。
住宅に求める性能や予算との兼ね合い、将来売却する可能性などを考慮して、住宅性能評価を受けるかどうか判断しましょう。
6.2. 耐震等級は自分で決めることができる
注文住宅の場合は、建築基準法を満たす耐震等級1以上を前提に、施主が希望する耐震等級で家を建てられます。
住宅に求める性能や間取りなどの希望条件、予算との兼ね合いを考えて等級を決定すると良いでしょう。
ただし、建築会社で自社の基準を定めている場合も多いため、事前に相談するのがおすすめです。間取りが決まってから耐震等級を上げようとすると、壁や柱の問題でその他の希望条件が叶わなくなってしまう可能性もあるため早い段階で要望を伝えておきましょう。
6.3. 建売住宅は築年数をチェック
住宅性能評価は義務ではありません。このため建売住宅や中古住宅を購入する場合、耐震等級がわからないこともあるでしょう。
その場合は、不動産会社の担当者に建物の耐震性を確認するのが一番ですが、築年数も耐震性をチェックする目安の一つです。
品確法が制定された2000年以降の建築物であれば、少なくとも建築基準法の基準である耐震等級1はクリアしていることになります。
7. 耐震等級を理解し安心して暮らせる家に住もう

耐震等級とは、2000年に制定された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく「住宅性能表示制度」の項目の一つです。
地震に対する崩壊、倒壊のしにくさを表す耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)と、地震に対する損傷の生じにくさを表す耐震等級(構造躯体の損傷防止)の2項目に分けられ、それぞれ1〜3の等級で評価されます。
耐震等級のなかで最も低い耐震等級1でも、命を守るために最低限の安全性が確保されるよう建築基準法で定められていますが、万全な備えとは言い難いのが現状です。
実際に、大きな地震が増えた近年では、震災で耐震等級1や等級2の建物が崩壊、倒壊したという報告も多く寄せられています。
このため、これから家を建てる場合は万が一に備えて耐震等級3を取得するのが安心でしょう。
一建設の住宅では、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)、耐震等級(構造躯体の損傷防止)ともに最高等級の取得を標準化。追加費用なしで耐震等級3の住宅が建てられます。
暴風に対する住宅の崩壊、倒壊、損傷のしにくさを表示する耐風等級も、最高等級である等級2を取得しているため防災機能の高い家づくりが可能です。
「災害に強い家で安心安全に暮らしたい」「価格は抑えたいけど住宅の機能は妥協したくない」方はぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。
一建設で物件を探す
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
【新築でやっておけばよかった】注文住宅のオプションおすすめ一覧!|平均価格の相場や総額の費用も紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅を建てる際にかかる費用相場を価格・広さ別に解説
注文住宅の費用は多くの要素に影響され、予算の設定に悩む方は少なくありません。この記事では、注文住宅に係る費用の相場内訳...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

注文住宅(新築)のおしゃれなキッチン!後悔しない決め方や種類・価格相場を紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
おすすめ記事
-

2024.03.15 | 費用・制度
【違いを比較】注文住宅と建売(分譲)住宅はどっちがいい?価格差は?
マイホームの取得を検討するなか、注文住宅にすべきか建売住宅(分譲住宅)にすべきかで迷う方は多いかと思います。設計の自由...
-

2025.02.13 | 平屋
平屋とは?平屋のメリット・デメリットと建築実例をご紹介
戸建て住宅の一般的な階層構造としては、平屋と2階建て、3階建てがあります。これから家を建てる方のなかには、何階建てにす...
-

注文住宅とは?どのような意味?メリット・デメリットもわかりやすく解説
2024.03.15 | 注文住宅
-

建ぺい率・容積率とは?家を建てる前に知っておきたい基礎知識
2025.03.10 | 費用・制度
-

平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
2025.06.13 | 平屋
新着記事
-

2025.06.13 | 注文住宅
ハウスメーカーの選び方を知り、理想の住まいを実現しよう!
家づくりには、予算決めや土地探しなど多くの工程がありますが、そのなかでもハウスメーカー選びは家の完成度を左右する重要な...
-

2025.06.13 | 平屋
平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
家を建てるとき、誰もが一度は悩むのが「平屋にするか、2階建てにするか」の選択ではないでしょうか。それぞれにメリット・デ...
-

リビングに吹き抜けを設置するメリット・デメリットと注意するポイント
2025.06.13 | マイホーム
-

住宅ローンの平均は?みんなはいくら借りて、いくら返済しているのか解説
2025.05.19 | ローン
-

ウォークインクローゼット(WIC)とは?クローゼットとの違いとメリット・デメリットを解説!
2025.05.19 | マイホーム