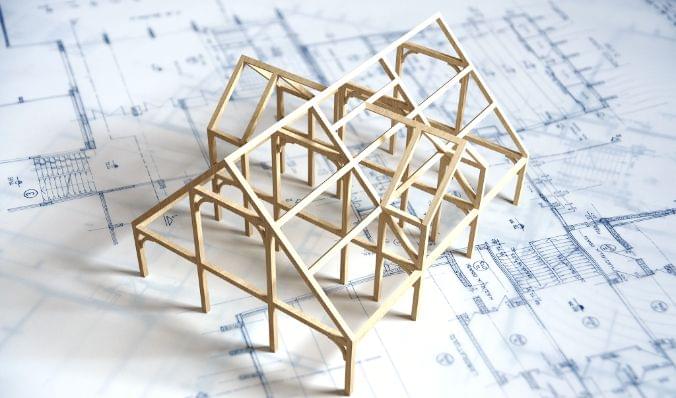2025.04.10 | 間取り
1坪は何平米で何畳?家や土地の広さの単位、快適に暮らす広さの目安を解説

目次
はじめの間取り
家づくりを検討する中で、理想の間取りや具体的なプランのイメージがなかなか湧かないという方も多いかもしれません。
一建設では、ご希望のエリア、フロア数、間取りを選択するだけで、条件に合った実例プランをご覧いただけるシミュレーション機能をご用意しています。
土地や家族構成、ライフスタイルに合わせた住まい探しを、簡単な操作でサポート。
理想の住まいづくりに向けて、ぜひシミュレーションページをご活用ください。
不動産業界では、土地や建物の広さを表す場合は「平米(㎡)」や「坪」、部屋の広さを表す場合は「畳」など、さまざまな単位が用いられます。このため「何がどのくらいの広さを表しているかわからない」「比較する際に混乱する」などでお悩みの方も多いでしょう。
そこでこの記事では、1坪は何平米?何畳?など、住まいの広さを表す単位が示す面積や、他の単位への換算方法を解説します。居住人数に応じた適切な家の広さなども解説しますので、住宅の購入や建築を検討している方はぜひ参考にしてください。
1. 1坪は何平米?何畳?< 早見表付き>
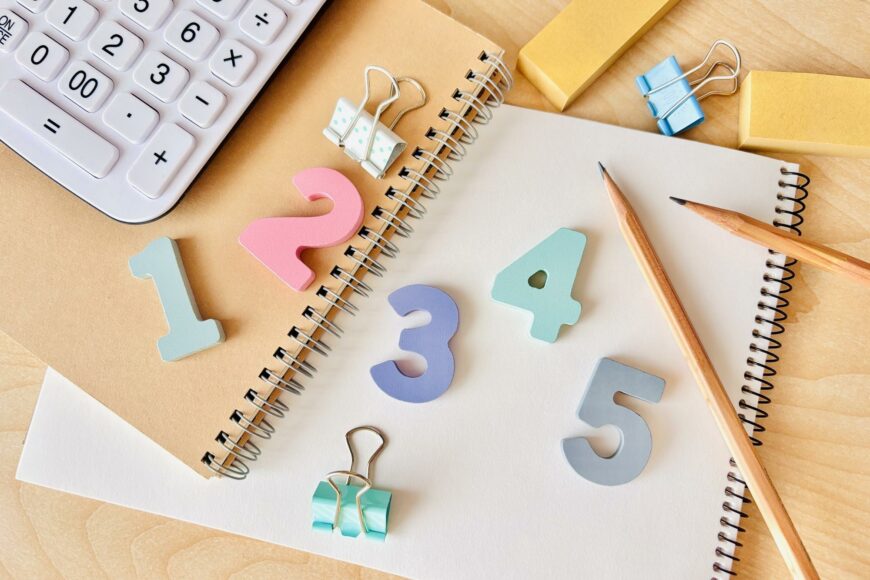
現在、日本で面積を表す公的な単位は「平方メートル(㎡)」です。しかし、不動産業界では住まいの広さを表す単位として、「平米」「坪」「畳」の3つが多く使われています。
「平米(へいべい)」は、「平方メートル(㎡)」の漢字表記である「平方米」の略記です。このため平米は平方メートルと同義であり、1平米は1㎡と同じ1m×1mの正方形の面積を表します。
一方、「坪(つぼ)」は、日本で古くから使われてきた面積を表す単位で、現在では主に土地の広さを表す際に用いられます。「平方メートル(㎡)」より、日本で長く親しまれてきた「坪」のほうが、感覚的に広さを理解しやすい方も多いことから、不動産広告などの単位表記に用いられています。
「畳(じょう)」は、部屋あたりの広さを表す単位です。文字どおり畳の枚数を基準とした単位で、坪と同様に直感的に広さをイメージしやすいことから、不動産広告や間取り図などでよく用いられます。
ここからは、それぞれの単位が表す広さや他の単位への変換方法を解説します。
1.1. 「坪」「平米」「畳」をそれぞれに換算すると?
「坪」は、主に土地の面積を表すのに使われる単位です。建物の面積を表す場合は「建坪(たてつぼ)」といい、建物を真上から見たときの建築面積を坪単位で表します。
1坪の基本的な換算値は以下のとおりです。
| 単位 | 換算値 |
|---|---|
| 1坪 | 約3.30578㎡ |
| 1坪 | 約2畳 |
| 1㎡ | 約0.3025坪 |
| 1㎡ | 約0.62畳 |
| 1畳 | 約1.62㎡ |
| 1畳 | 約0.5坪 |
「畳」は、畳1枚ぶんの広さを表す単位です。畳のサイズは発祥や地域によって異なるため一概にはいえませんが、不動産業界のルールでは1畳=約1.62㎡以上と定められています。
上記を踏まえた「坪数」「平米数(㎡)」「畳数」の早見表は以下のとおりです。土地や建物、部屋の広さをイメージしたいときや、不動産を比較・検討する際にご活用ください。
| 坪数 | 平米数(㎡) | 畳数(おおよその畳数・中京間) |
|---|---|---|
| 1坪 | 3.31㎡ | 約2畳 |
| 5坪 | 16.25㎡ | 9.98畳(約10畳) |
| 10坪 | 33.05㎡ | 19.96畳(約20畳) |
| 15坪 | 49.58㎡ | 29.94畳(約30畳) |
| 20坪 | 66.11㎡ | 39.92畳(約40畳) |
| 25坪 | 82.64㎡ | 49.90畳(約50畳) |
| 30坪 | 99.17㎡ | 59.88畳(約60畳) |
1.2. 坪・平米(㎡)・畳の換算式
任意の数値を「平米(㎡)」「坪」「畳」の各単位に変換したい場合は、以下の計算式でそれぞれの数値を算出できます。
坪 → 平米(㎡) :坪数 ÷ 0.3025
平米 → 坪 :平米数 × 0.3025
平米 → 畳 :平米数 ÷ 1.62
例えば、敷地面積40坪を平米(㎡)に変換する場合、上記の計算式に当てはめると40÷0.3025=約132.2平米(㎡)となります。
敷地面積40平米(㎡)を他の単位に変換したい場合も同様に、それぞれの式にあてはめると以下の数値になります。
40平米(㎡)×0.3025=約12.1坪、40平米(㎡)÷1.62=約24.7畳
2. 住む人数別の快適な住まいの広さ
住む人数に応じて、快適に感じる住まいの広さは異なります。このため家を建てる際は、家族構成を踏まえて土地や建物、部屋の広さを考える必要があります。
2.1. 政府が定める居住面積水準
国土交通省は、住宅政策の基本方針を示す「住生活基本計画」のなかで、快適に生活できる住まいの広さの基準として「居住面積水準」を設けています。居住面積水準は、「最低居住面積水準」「誘導居住面積水準/都市居住型」「誘導居住面積水準/一般型」の3つに分けられます。
「最低居住面積水準」とは、健康で文化的な住生活を営むために、最低限必要な家の広さを定めた基準です。それに対して、「誘導居住面積水準」とは、豊かな住生活の実現を前提に、多様なライフスタイルに対応できる水準を指します。
さらに「誘導居住面積水準」は、都市の中心または周辺に位置する共同住宅(マンション・アパートなど)を想定した「都市居住型」と、都市部以外や郊外などの一般地域に位置する戸建て住宅を想定した「一般型」に分けられます。
国土交通省は、家族構成や世帯人数に応じて、それぞれの具体的な水準を以下の数値で示しています。
| 世帯人数別面積(㎡) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| 最低居住面積水準 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 未就学児(3~5歳児)が1人いる | 35 | 45 | |||
| 誘導居住面積水準 | <都市居住型> | 40 | 55 | 75 | 95 |
| 未就学児(3~5歳児)が1人いる | 65 | 85 | |||
| <一般型> | 55 | 75 | 100 | 125 | |
| 未就学児(3~5歳児)が1人いる | 87.5 | 112.5 | |||
2.2. 1人暮らしの場合:25㎡~55㎡(約7.6坪~16.6坪)
1人暮らしで最低限必要とされる家の広さ(最低居住面積水準)は25㎡。他の単位に換算すると約7.6坪、約15.4畳です。主にワンルームの賃貸アパートなどがこの広さに該当します。
また、より豊かな住生活を実現するのに必要な広さ(誘導居住面積水準)は、都市居住型の場合40㎡(約12.1坪、約24.7畳)、一般型の場合55㎡(約16.6坪、約34畳)が推奨されています。これらは間取りでいうと主に1LDKか2LDKの家が該当します。
なお、住宅ローン控除を受けるには、床面積が40㎡以上必要です(※)。住宅購入を検討している方は、この条件も考慮して住まいの広さを検討しましょう。
※控除を受ける条件はこちらをご確認ください。
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
2.3. 2人暮らしの場合:30㎡~75㎡(約9.1坪~22.7坪)
カップル・夫婦や親子・兄弟姉妹など2人暮らしの場合、最低限必要とされる家の広さは30㎡(約9.1坪、約18.5畳)で、1K〜1LDKの共同住宅でよく見られる広さです。
また、さまざまなライフスタイルに対応できる広さとしては、都市居住型の場合55㎡(約16.6坪、約34畳)、一般型の場合75㎡(約22.7坪、約46.3畳)が推奨されています。間取りでいうと主に2LDK〜3DKの家が該当しますが、将来的に家族が増える可能性がある場合、もう少し広い家にしておくと安心です。
2.4. 3人暮らしの場合:40㎡~100㎡(約12.1坪~30.3坪)
世帯人数が3人以上の場合、子どもの年齢によって必要とされる家の広さの基準が異なります。
未就学児(3歳〜5歳)の子どもがいる3人家族の場合、最低居住面積水準は35㎡(約10.6坪、約21.6畳)。誘導居住面積水準は、都市居住型の場合が65㎡(約19.7坪、約40.1畳)、一般型の場合が87.5㎡(約26.5坪、約54畳)です。
子どもが就学年齢になると、最低居住面積水準は40㎡(約12.1坪、約24.7畳)。誘導居住面積水準は、都市居住型の場合が75㎡(約22.7坪、約46.3畳)、一般型の場合が100㎡(約30.3坪、約61.7畳)とより広いスペースが必要になります。
子どもの成長を考えると、家を建てる場合は87.5㎡(約26.5坪、約54畳)以上の広さが、間取りは子ども部屋と夫婦の寝室を確保できる2LDK以上がおすすめです。また、子どもが小さいうちは1LDKの家に住み、スペースが必要になったら2LDK、3LDKの家に移るのも選択肢の一つです。
2.5. 4人暮らしの場合:45㎡~125㎡(約13.6坪~37.8坪)
両親+子ども2人(1名は未就学児)の4人暮らし場合、最低居住面積水準は45㎡(約13.6坪、約27.8畳)。誘導居住面積水準は、都市居住型の場合が85㎡(約25.7坪、約52.5畳)、一般型の場合が112.5㎡(約34坪、約69.4畳)です。
子どもが2人とも就学年齢になると、最低居住面積水準は50㎡(約15.1坪、約30.9畳)。誘導居住面積水準は、都市居住型の場合が95㎡(約28.7坪、約58.6畳)、一般型の場合が125㎡(約37.8坪、約99.2畳)と、より広いスペースが求められます。
家を建てる場合、広さは子どもが成長してもゆとりを感じられる100㎡(約30坪)以上がおすすめです。間取りは、夫婦の寝室+子ども部屋2つを確保できる3LDK以上が望ましいでしょう。
2.6. 5人暮らし以上の場合は?居住面積水準の計算方法
最低居住面積水準・誘導居住面積水準は、以下の計算式で算出できます。世帯人数が5人以上の場合は下記の表をもとに、必要な住まいの広さを計算しましょう。
| 2人以上の世帯 | ||
|---|---|---|
| 最低居住面積水準 | 10㎡×世帯人数+10㎡ | |
| 誘導居住面積水準 | <都市居住型> | 20㎡×世帯人数+15㎡ |
| <一般型> | 25㎡×世帯人数+25㎡ | |
参照:徳島県庁「誘導居住面積水準、最低居住面積水準とは何ですか。」
なお、世帯人数は未就学児(3歳〜5歳)の場合0.5人としてカウントします。
3. 「坪単価」とは?

その他に不動産広告でよく見かける表現としては「坪単価」「坪15.8万〜17.8万円」などが挙げられます。坪単価とは1坪あたりの価格を表す指標です。土地の場合は1坪(約3.3㎡)あたりの価格を、建物の場合は1坪あたりの建築費用を表します。
坪単価は、原則として本体価格 ÷ 面積(坪)で求められます。例えば、30坪の土地が1,000万円で販売されている場合、坪単価は約33万3,000円です。延べ床面積50㎡の建売住宅が3,000万円で販売されている場合、坪単価は60万円となります。
ただし、坪単価に明確な定義はなく、厳密な計算方法も建築会社ごとに異なります。また、家の性能や設備、間取りなどによっても建物の価格は変わってくるため、単純に坪単価だけを比較して住宅を選ぶのはおすすめできません。住宅の購入および建築を検討している場合は、坪単価だけで比較するのではなく、総額や住宅の品質などから総合的な判断が重要です。
注文住宅の平均延べ床面積や坪単価に関しては以下の記事で詳しく紹介しています。興味のある方は併せてご覧ください。
4. 一坪は何平米かを知って快適に暮らそう

不動産広告などでよく見かける「坪」や「畳」の単位は、一定の計算式を用いることで「平米(㎡)」に変換が可能です。
1坪=約3.3平米(㎡)・約2畳と覚えておくと、不動産情報を見たときに広さの把握や比較がしやすくなるでしょう。
快適に感じる住まいの広さは人それぞれですが、その目安を知るには国土交通省が公表している居住面積水準が便利です。お住まいの地域や世帯人数、住宅の種類に応じて、最低限必要とされる家の広さや、ゆとりある暮らしに必要な家の広さが具体的な数値で示されているため、参考にすると良いでしょう。
「一建設」の注文住宅は、間取りや設備、デザインなどを自分好みにアレンジした設計が可能です。敷地面積や予算に制限がある場合でも、年間約9,000棟の着工実績と豊富なノウハウを活かして、お客さまの生活スタイルやご要望に合ったプランをご提案します。
コストとクオリティのバランスのとれた注文住宅をお求めの方はぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。
一建設の注文住宅を見る
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
ご自宅の売却・引越し(住み替え)も一建設にお任せ
一建設の『ラクいえ売却』
住み替えによる不安を無くすために生まれた、一建設の『ラクいえ売却』。
住まいが売れるタイミングと新しい住まいが見つかるタイミングを合わせる必要がなく、
愛着のある住まいが高く売れるまで交渉する手間もありません。
ダブルローンをはじめとする自宅売却のお悩みを解消します。
- #売却後も1年間賃料無料で住み続けられるからゆとりをもった住み替えが可能
- #引越し費用を最大50万円一建設が負担で手厚くサポート
- #新生活に嬉しいキャッシュバック制度あり
- #一建設の取り扱い物件以外も売却可能