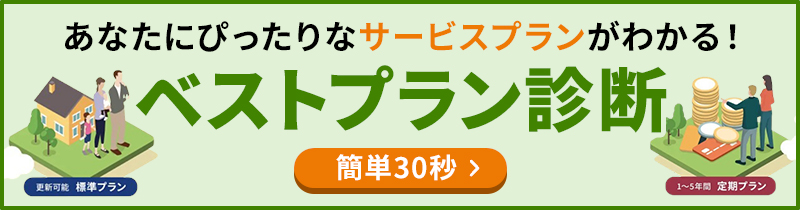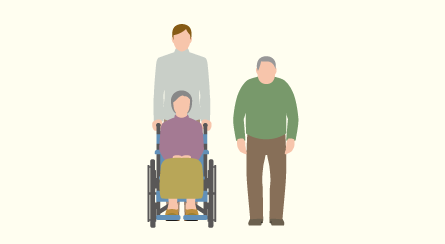生活保護を受けるには、 資産活用の原則といって、まずは保有資産を処分し、生活費に充てる必要があります。
しかし、「持ち家がないとさらに生活に困る」「できれば今の家に住み続けたい。」という方も多いでしょう。
そこでこの記事では、持ち家があっても生活保護を受けられるのか、受給条件や売却が必要なケースを解説します。
記事の後半では、持ち家を活用した資金調達法などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
INDEX
持ち家があっても生活保護は受けられる?
生活保護は、資産や能力、その他あらゆる手段を活用しても、なお生活に困窮する場合に初めて利用できる制度です。
そのため、土地や建物などの不動産は売却し、生活費に充てるのが原則です。
ただし、厚生労働省は例外として、生活保護制度の運用方針で以下を定めています。
被保護世帯の居住の用に供される家屋及びそれに付属する土地については、保有を容認し、保護を適用。
参照:2 不動産の保有の考え方-資産活用の在り方|厚生労働省
わかりやすく説明すると、「居住の用に供される家屋およびそれに付属する土地」=持ち家は、保有が許されるという意味です。
実際、令和5年度の厚生労働省の調査では、生活保護受給世帯のうち3%弱(162万6,263世帯のうち4万6,737世帯)が、持ち家を保有しているというデータがあります。
参照:9-1被保護世帯数、住居区分・床面積別上限額の適用状況・世帯類型・世帯人員・級地別-令和5年度被保護調査-個別調査(住居の状況)|厚生労働省
そもそも生活保護とは
生活保護とは、何らかの事情で生活できるだけの収入を得られない人を、経済的に援助する制度です。受給資格は、収入や資産状況など一定の条件を満たす必要があり、日本国憲法第25条で規定されている「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を助長することを目的として、国が生活費や住宅費などを援助します。
生活保護の内訳
生活保護では受給者の状況に応じて、必要な費用が用途ごとに分けて支給されます。
具体的な内訳は以下のとおりです。
| 扶助の種類 | 費用の概要 | 支給内容 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活に必要な費用 | 基準額は「食費などの個人的費用」と「光熱水費などの世帯共通費用」を合算し、基準額を算出 ※ 母子家庭など特定の世帯には加算あり |
| 住宅扶助 | アパートなどの家賃 | 一定の範囲内で実費を支給 |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品 | 一定の基準額を支給 |
| 医療扶助 | 医療機関に直接支払い(本人負担なし) | |
| 介護扶助 | 直接介護事業者に直接支払い(本人負担なし) | |
| 出産扶助 | 一定の範囲内で実費を支給 | |
| 生業扶助 | ||
| 葬祭費用 | ||
住宅扶助は、賃貸住宅に住んでいる人の家賃や、土地が借地の場合の地代(土地の賃借代金)などが支給対象です。
そのため戸建て住宅やマンション等、所有している土地と建物=持ち家に住んでいる場合、基本的に住宅扶助は支給されません。
生活保護の受給要件
日本国民であれば、年齢や性別、職業などに関係なく誰でも生活保護を申請できます。
ただし、生活保護を受給するには以下の要件を満たす必要があります。
収入がない
生活保護を受給するには、国が定める最低生活費を世帯収入が下回っている必要があります。
最低生活費とは、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用です。地域や世帯の人数などを考慮して、一定の基準に基づき算出されます。
この最低生活費を、世帯収入が下回っていることが生活保護の受給要件の一つです。世帯収入には、給料だけでなく、年金や養育費、親戚からの仕送りなど労働以外の収入も含まれます。
働きたくても働けない
収入がゼロでも働ける状態であれば、働く努力が求められます。そのため就労能力または就労環境がないなど、働きたくても働けない状態であることも受給要件の一つです。
具体的には、病気や怪我、障害などで働けない、介護が必要な家族がいる、年齢的に就労が困難などの状況が該当します。
>>親の介護費用はいくら?費用負担を減らす制度や払えないときの対策を紹介
ただし、病気や怪我などで一時的に働けない場合は、完治したら就業する意思と努力が求められます。症状が回復し、働ける状態になっても就労の意思や努力が見られない場合、生活保護は支給停止または打ち切りとなる可能性があります。
参照:生活保護法第26条(保護の停止及び廃止)|GOV法令検索
資産を持っていない
生活保護は、自分が持っている資産を生活のために利用して、それでもなお生活の維持が難しい場合に支給対象となります。(資産活用の原則)
そのため現金化できる資産がある場合は、それらを売却して生活費に充てることが先決です。生活保護申請にあたり、現金化が求められる資産の代表例は以下のとおりです。
- 不動産(別荘など)
- 自動車
- 貴金属
- 高級ブランド品
- 貯蓄性のある生命保険
持ち家も不動産の一つですが、生活上必要なものとして認められれば保有が容認されます。
他の公的制度を利用できない
生活保護は、経済的に困窮した人を支える「最後のセーフティネット」の役割を持つ社会福祉制度です。そのため年金制度や保険制度など、その他生活を支援する公的制度を利用してもなお生活が困難な場合に適用されます。
生活保護の申請・受給前に活用すべき主な公的制度は以下のとおりです。
| 制度 | 給付の種類 | 主な内容・対象者 |
|---|---|---|
| 年金制度 | 老齢年金 | 高齢者の生活を支援する年金制度 |
| 遺族年金 | 家計を支えていた家族が亡くなった遺族を支援する年金制度 | |
| 障害年金 | 病気や怪我で働けない人のための年金制度 | |
| 健康保険 | 傷病手当金 | 一時的な病気・怪我による所得補償 |
| 高額療養費制度 | 医療費の自己負担額を軽減する制度 | |
| 雇用保険 | 失業保険 | 失業者の生活と再就職を支援する給付制度 |
| その他公的給付制度 | 児童扶養手当 | 18歳未満の子を養育しているひとり親家庭を支援する給付制度 |
| 住宅確保給付金 | 家を失った、またはその恐れがある人を支援する給付制度 |
生活保護の申請前に、まずは自治体の福祉事務所や役所の窓口で相談しましょう。具体的な支援プランの作成や、利用可能な公的制度の案内が受けられます。
身内の支援が受けられない
生活保護の申請を受けると、ケースワーカーが両親・祖父母・子などの直系血族や兄弟姉妹などの親族に扶養の可否を確認します。これらの親族から十分な経済的支援が受けられる場合、生活保護の支給対象にはなりません。
ただし、経済的余裕がない、扶養の意思がないなどの理由で援助が受けられない場合は、生活保護の支給対象となります。
参照:扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について|厚生労働省
生活保護の申請の流れ
生活保護の申請ができるのは、本人もしくは直系血族や兄弟姉妹などの扶養義務者、同居している親族のみです。まずは福祉事務所の窓口で、生活保護の申請を検討している旨を伝えましょう。
申請時には、本人確認書類のほか、現在の収入や保有資産の証明書類などが必要です。
必要書類の提出後は、ケースワーカーによる家庭訪問や資産調査、親族への扶養照会などがおこなわれます。これらの結果をもとに、生活保護の受給の可否が判断され、通常は2週間以内に電話または郵送で通知が届きます。
担当者から支給額や扶助の内容に関する説明を受けたら、いよいよ支給開始です。原則として、月に1回生活保護費が指定の銀行口座に振り込まれます。
ただし、一度生活保護の受給が認められても、それがずっと続くわけではありません。受給中は、担当者による指導や面談など、自立に向けた支援がおこなわれるほか、定期的に収入や資産状況が確認されます。調査の結果、生活状況の改善が認められた場合には、支給額の減額や生活保護の終了が決定します。
持ち家があっても生活保護が受けられるケース

2.2生活保護の受給要件 で説明したように、生活保護は保有資産を生活のために活用し、それでもなお生活が難しい場合に支給対象となります。
そのため、原則として不動産は売却して生活費に充てる必要がありますが、持ち家の場合は以下の条件に該当すれば、例外的に保有が認められます。
売却すると住む家がなくなる場合
生活保護は、憲法第25条に基づき「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を助長することを目的としています。
そのため、持ち家が単なる資産ではなく、生活を続けるのに最低限必要なものと判断された場合は、売却せずに生活保護を受けられます。
具体的には、加齢や障害などにより賃貸住宅への転居が難しく、持ち家を失うことで生活がさらに苦しくなったり、生活の立て直しが難しくなったりする場合が該当します。
住宅ローンを完済している場合
持ち家に住んだまま生活保護を受給するには、原則として住宅ローンを完済している必要があります。仮に生活保護費が住宅ローンの返済に充てられた場合、国が個人の資産形成を助けることになってしまうためです。
ただし、完済まで5年以内、ローン残高額が300万円以下など、完済までの期間が比較的短い場合は、生活保護の受給が認められることもあります。
引っ越し費用が家の売却価格を上回る場合
転居するより、今の家に住み続けるほうが費用が安く済むと判断された場合も、持ち家に住んだまま生活保護の受給が認められます。
具体的には、引っ越し費用が家の売却価格を上回る、賃貸物件の家賃が固定資産税や維持費を上回るなどのケースが該当します。
生活保護のために持ち家を売却しなければならないケース
持ち家は、生活保護の受給中も例外的に保有が認められる資産です。しかし、持ち家だからといって無条件で住み続けられるわけではありません。
主に以下のケースに該当している場合は、持ち家でも生活保護の申請・受給にあたって売却が求められます。
資産価値が高い場合
厚生労働省は、生活保護受給時における持ち家の保有に関して、以下の運用方針を示しています。
ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等による資産の活用をした上で、保護の要否を判断。
参照:2 不動産の保有の考え方-資産活用の在り方|厚生労働省
そのまま住むことで得られる生活上の価値より、売却して得られる金額のほうが明らかに大きいと思われる場合は、売却してから生活保護が必要かどうか判断するという意味です。
具体的には、豪華な持ち家や、同居人数に対して住居の規模が見合わないなどのケースが該当します。
金額に換算すると、売却金額2,000万円程度が目安です。
住まいとして利用していない場合
別の住居に住んでいる場合は、持ち家を売却して生活費に充てるよう求められます。3.1 売却すると住む家がなくなる場合 と異なり、持ち家が生活を続けるのに最低限必要なものではなく、活用すべき資産とみなされるためです。
そもそも、持ち家とは別に住まいがある状況で、生活できない状態になるとは考えにくいため、生活保護の必要性は低いと判断される可能性が高いでしょう。
また、現在持ち家に住んでいる状態で実家を相続した場合には、生活保護を申請する前に相続した実家の売却を求められることが一般的です。ただし、築年数が経過している物件や立地が良くない場合は、すぐに売却できないことも考えられます。売却が難しい状況でも受給できる可能性はあるため、築年数や物件状況に不安がある場合は、早めに福祉事務所へ相談するとよいでしょう。
多額の住宅ローンが残っている場合
原則として、住宅ローンが残っている場合は持ち家の売却が求められます。受給者が生活保護費を住宅ローンの返済に充てた場合、国が個人の資産形成を助けることになってしまうためです。
ただし、3.2 住宅ローンを完済している場合 で説明したように、完済までの返済期間が5年以内、ローン残高が300万円以下など、近いうちに完済が見込める場合は受給を認められるケースもあります。
>>住宅ローンの返済が厳しい人が急増?ローンが払えない時の対処法
持ち家を活用した生活資金の調達方法
経済的に困窮していても、持ち家を売却すれば、生活費を確保できる可能性があります。また、売却だけでなく、持ち家を担保とすることで、生活資金の借り入れができるサービスもあります。
持ち家を活用した生活資金の調達方法は以下のとおりです。
>>不動産を現金化するならこの方法!メリット・デメリットをわかりやすく解説
任意売却
住宅ローン返済中の物件を売却するには、債権者(金融機関)に抵当権を外してもらう必要があります。
住宅の売却金額が住宅ローンの残債を上回る、いわゆるアンダーローンの状態であれば特に問題なく売却できますが、売却金額がローンの残債を下回るオーバーローンの場合は注意が必要です。売却代金で残債を一括返済できないため、債権者(金融機関)に許可を得て、任意売却の手続きを進める必要があります。
任意売却とは、債権者(金融機関)と売却価格や売却時期などの条件を調整し、市場で物件を売却する売却方法です。
通常、住宅ローンの滞納が続くと、持ち家は競売にかけられ、相場より安い価格で強制的に売却されます。しかし、競売になる前に任意売却をおこなえば、市場価格に近い価格で売却し、残債を減らすことができます。
>>住宅ローン返済中でも持ち家は売れる?オーバーローンでも売却できる3つの方法
>>任意売却のメリット・デメリットや流れを解説!ローン返済の代替案も紹介
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、持ち家(自宅)を担保とした資金融資です。
主に、50歳以上80歳未満の方を対象とするサービスで、自宅を担保にして生活資金を借りられます。
契約者が亡くなった後に自宅を売却することで資金回収を図るため、生存中は毎月利息分のみを支払います。
売却せず、持ち家を担保にして融資を受けるという形の資金調達法です。
>>リバースモーゲージと生活保護|仕組みや利用する順番について解説
>>リバースモーゲージの利用条件とは?年齢や使い道、担保物件の条件を解説
リースバック
「生活のために持ち家の売却を検討しているけど、できれば今の家に住み続けたい……。」と考えている方も多いでしょう。
そんな方には、不動産の売買契約と賃貸借契約を組み合わせたリースバックがおすすめです。持ち家の売却後、毎月家賃を支払うことで、賃貸物件として自宅に住み続けられます。
また、任意売却でも、買い主と賃貸借契約を結ぶことでリースバックの仕組みを利用可能です。リースバックに対応している不動産会社に仲介を依頼しましょう。
>>リースバックと任意売却の違いは?併用するメリットや注意点を解説
「リースバックプラス+」は、一建設が提供するリースバックサービスです。
お客様のライフスタイルやニーズに合わせて3つのタイプをご用意しております。売却後もずっと住み続けられる「標準プラン」や、賃料重視の「定期プラン賃料優遇タイプ」、将来買い戻しを検討している方のための「定期プラン買戻優遇タイプ」の中から、ご自身の希望に合ったプランをお選びください。
持ち家を活用し、ローンの解消や資金の確保を考えている方の選択肢の一つとなれば幸いです。
生活保護の受給中に持ち家を売却するときの注意点
基本的に、持ち家を売却すべきかどうかは生活保護の受給前に判断されます。
しかし、何らかの事情で、生活保護受給中に持ち家を売却する場合は注意が必要です。
売却金額によっては、受給の取り消しや、過去の支給分の返還を求められる場合があります。今まで生活保護を受給していた期間の生活費も、本来その資金で賄えるはずだったと判断されるためです。
まとめ
生活保護は、経済的に困窮した人を支える「最後のセーフティーネット」です。資産や能力、その他あらゆる手段を活用してもなお生活に困窮する場合に利用できます。
したがって、代表的な資産である不動産は売却し、生活費に充てるのが原則です。
しかし、持ち家に関しては、生活を続けるのに最低限必要なものとして認められれば、例外的に保有が認められます。
持ち家を保有したまま生活保護の受給が認められるケースは以下のとおりです。
- 売却すると住む家がなくなる場合
- 住宅ローンを完済している場合
- 引っ越し費用が家の売却価格を上回る場合
反対に、持ち家を住まいとして利用していない場合や、資産価値が高い場合、多額の住宅ローンが残っている場合などは、活用可能な資産とみなされ、売却が求められます。
しかし、持ち家の売却が必要なケースでも「できれば愛着のある我が家に住み続けたい……。」と思う方は多いでしょう。
そのような場合には、売却後も自宅に住み続けられるリースバックがおすすめです。買い主との契約により、賃貸物件として住み慣れたマイホームに住み続けられます。
「リースバックプラス+」では、ずっと安心して住み続けられる「標準プラン」と賃料重視の「定期プラン賃料優遇タイプ」、将来買い戻しに有利な「定期プラン買戻優遇タイプ」の3タイプをご用意しております。
原則、住宅ローンが残っていても利用できますので、興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。