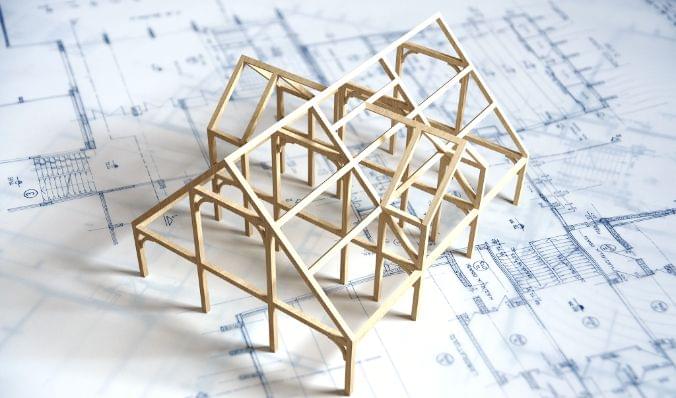2025.03.10 | 費用・制度
建ぺい率・容積率とは?家を建てる前に知っておきたい基礎知識

目次
はじめの費用・制度
家づくりを進めるうえでは、価格と品質のバランスが非常に重要です。
一建設では、年間約9,000棟超の供給実績を活かし、コストを抑えながらも高品質な注文住宅を実現しています。
建築に必要な工程をすべて含んだ安心のコミコミ価格に加え、着工金や中間金が不要な資金計画の立てやすさも魅力です。
自社一貫体制による中間マージンの排除など、低価格を支える仕組みについて、詳しくは価格ページをご覧ください。
広い土地と十分な資金さえあれば、大きな家が建てられると思っていませんか?実は、建てられる建物の大きさは、自治体によって地域ごとに上限が設けられているため注意が必要です。
この記事では、土地に対する建物の大きさを表す「建ぺい率」と「容積率」という2つの指標を解説します。
法律を遵守して家を建てるために、建ぺい率・容積率の計算方法や、各自治体で設定される上限の基準、上限をオーバーした際のリスクなどを知っておきましょう。
1. 建ぺい率・容積率とは?
簡単に説明すると、「建ぺい率」は土地に対する建築面積(通常、建物の1階部分の面積)割合を、「容積率」は土地に対する建物の延べ床面積(すべての階の面積の合計)の割合を表す指標です。どちらも安全で快適な家づくり・まちづくりの観点から、地域ごとにそれぞれの上限が定められています。
ここからは以下の項目に分けて、建ぺい率・容積率の定義や計算式などを解説します。
- 建ぺい率の定義・計算式
- 容積率の定義・計算式
- 建ぺい率・容積率の上限を知る方法
1.1. 建ぺい率の定義
建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の建築面積の割合です。漢字だと建蔽率と表記され、蔽という漢字には「おおう」という意味があることから、「土地を建物がおおっている面積の割合」と考えるとイメージしやすいかもしれません。
敷地面積とは建物を建てる土地の面積、建築面積とは建物を真上から見たときの面積を指します。例えば、2階建ての家で1階のほうが広い場合は、1階の面積が建築面積にあたります。
建ぺい率は、日当たり・通気性の確保、火災時の延焼防止・避難経路の確保、景観保護などの観点から、行政でその上限が定められています。建ぺい率の上限は、各自治体によって最低30%〜最高80%の間で定められており、これを超える建物は建築できません。
1.1.1. 建ぺい率の計算式
建ぺい率を求める計算式は以下のとおりです。
建ぺい率(%)=建物の建築面積(㎡)÷敷地面積(㎡)×100
例えば、200㎡の土地に、1階の面積が120㎡、2階の面積が80㎡の家を建てるとしましょう。より広い1階の面積が建築面積として計算するため、
120㎡(建築面積)÷200㎡(敷地面積)×100=60%
となり、この場合の建ぺい率は60%となります。
なお、土地の広さを超える建物が建つことはないため、建ぺい率は必ず100%以下となります。
1.2. 容積率の定義
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。
延べ床面積とは、各階の床面積の合計のことで、例えば、3階建ての建物の場合、1階、2階、3階の床面積の合計値が延べ床面積となります。
日当たり・通気性の確保や景観保護など建ぺい率と同様の理由に加え、人口密集を防ぐ目的から、容積率も各自治体によって上限が決められています。
建物の平面的な広さを制限する建ぺい率に対し、容積率は3次元空間の利用割合を制限するのが特徴です。
1.2.1. 容積率の計算式
容積率を求める計算式は以下のとおりです。
容積率(%)=建物の延べ床面積(㎡)÷敷地面積(㎡)×100
例えば、200㎡の土地に1階の面積が120㎡、2階の面積が80㎡の家を建てるとしましょう。
120㎡+80㎡(延べ床面積)÷200㎡(敷地面積)×100=100%
上記の計算式から、この場合の容積率は100%となります。
一般的に、建物が高さを増すほど延べ床面積は大きくなるため、容積率が100%以上になることは珍しくありません。実際に、高層のタワーマンションなどでは1,000%を超えることもあります。
1.3. 建ぺい率・容積率の上限を知る方法
建設予定地の建ぺい率・容積率は、自治体のホームページで確認できます。用途地域に関するページに掲載されているほか、自治体によっては都市計画図がインターネット上に公開されている場合もあります。
見方がわからない場合や不明点がある場合は、役所の都市計画課や建設予定地の情報を掲載している不動産会社に問い合わせると安心です。
2. 用途地域による建ぺい率・容積率の違い

建ぺい率や容積率の上限は、用途地域ごとに定められており、その範囲内で各自治体が具体的な数値を定めています。
2.1. 用途地域とは
用途地域とは、都市計画法に基づいて土地利用の方法を定めたものです。安全で快適なまちづくりのために、利用目的に応じて土地を分類し、その区分に応じて建築可能な建物の種類を定めています。
用途地域は、大きく分けて住居・商業・工業のカテゴリがあり、そこからさらに細かく13種類に分類されます。
| 用途地域 | 用途 | 建築可能な建物 | |
|---|---|---|---|
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域 | ・住宅 ・事務所兼住宅 ・小規模な店 ・小中学校 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域 | ・住宅 ・小中学校 ・150㎡までの店 |
|
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域 | ・住宅 ・病院 ・大学 ・500㎡までの店 |
|
| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域 | ・住宅 ・病院 ・大学 ・1,500㎡までの店や事務所、利便施設 |
|
| 第一種住居地域 | 住宅の環境を守るための地域 | ・住宅 ・3,000㎡までの店舗 ・事務所 ・ホテル |
|
| 第二種住居地域 | 主に住宅の環境を守るための地域 | ・住宅 ・店舗 ・事務所 ・ホテル ・カラオケボックス |
|
| 準住居地域 | 道路環境と住居環境を保護するための地域 | ・住宅 ・店舗 ・事業所 ・カラオケボックス ・ボウリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場など |
|
| 田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅の環境を守るための地 域 |
・住宅 ・150㎡以下の店 ・農産物の直売所、農家レストランなど |
|
| 商業系 | 近隣商業地域 | 地域住民が日用品の買い物などをするための地域 | ・住宅 ・店舗 ・事業所 ・ホテル ・遊戯施設・風俗施設 ・小規模の工場 |
| 商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地 域 |
・住宅 ・店舗 ・事業所 ・ホテル ・遊戯施設・風俗施設 ・小規模の工場 |
|
| 工業系 | 準工業地域 | 軽工業の工場やサービス施設などがある地域 | 危険性、環境悪化が大きい工場以外はほぼ建築可能 |
| 工業地域 | どのような工場でも建てられる地域 | ・住宅 ・店舗 ・工場 ※学校、病院、ホテルなどは建てられない |
|
| 工業専用地域 | 工場のための地域 | どのような工場も建てられるが、住 宅、店、学校、病院、ホテルなどは建てられない |
参照:国土交通省「建築物の用途制限(法第48条)・用途地域による建築物の用途制限(法別表2)-建築基準法(集団規定)」
2.2. 用途地域ごとの建ぺい率・容積率
建ぺい率・容積率の上限は、用途地域ごとに以下の範囲で定められています。
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |
|---|---|---|---|
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 30%〜60% | 50%〜200% 100%〜500% |
| 第二種低層住居専用地域 | |||
| 第一種中高層住居専用地域 | |||
| 第二種中高層住居専用地域 | |||
| 第一種住居地域 | 50%〜80% | ||
| 第二種住居地域 | |||
| 準住居地域 | |||
| 田園住居地域 | 30%〜60% | 50%〜200% | |
| 商業系 | 近隣商業地域 | 60%〜80% | 100%〜500% |
| 商業地域 | 80% | 200%〜1300% | |
| 工業系 | 準工業地域 | 50%〜80% | 100%〜500% |
| 工業地域 | 50%〜60% | 100%〜400% | |
| 工業専用地域 | 30%〜60% |
参照:国土交通省「容積率制限(法第52条)・建蔽率制限(法第53条)-建築基準法(集団規定)」
住居系のエリアでは住環境が重視されるため、建ぺい率は30%〜80%、容積率は50%〜200%と低めに設定されています。
人々が買い物や娯楽で利用する建物が立ち並ぶ商業系のエリアは、建ぺい率は60%〜80%、容積率は100%〜1,300%と、住居系・工業系に比べて高めの設定となっています。
工業系のエリアは、建ぺい率30%〜80%、容積率100%〜500%で設定されています。ただし、工業専用地域は工業の発展を目的としているため、この建ぺい率・容積率の範囲内でも住宅は建てられません。
また、前面道路が12m未満の場合、容積率には用途地域の区分に応じてさらに以下の上限が設けられるため注意が必要です。
| 用途地域 | 前面道路による容積率 | |
|---|---|---|
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 前面道路幅員×40% |
| 第二種低層住居専用地域 | ||
| 第一種中高層住居専用地域 | 前面道路幅員×40% (特定行政庁指定区域:×60%) |
|
| 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 第一種住居地域 | ||
| 第二種住居地域 | ||
| 準住居地域 | ||
| 田園住居地域 | 前面道路幅員×40% | |
| 商業系 | 近隣商業地域 | 前面道路幅員×60% (特定行政庁指定区域:×40%または×80%) |
| 商業地域 | ||
| 工業系 | 準工業地域 | 前面道路幅員×60% (特定行政庁指定区域:×40%または×80%) |
| 工業地域 | ||
| 工業専用地域 |
参照:国土交通省「容積率制限(法第52条)-建築基準法(集団規定)」
前面道路が12m未満の場合、容積率の上限は、用途地域による制限と前面道路による制限のうち小さいほうが適用されます。
2.3. 複数の用途地域にまたがる場合
土地が複数の用途地域にまたがっている場合は、敷地に対する用途地域の割合を考慮して上限を算出します。
例えば、100㎡の敷地が、以下の条件で異なる2つの地域にまたがっているとします。
| 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | |
|---|---|---|---|
| 100㎡のうち40㎡ | 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 100% |
| 100㎡のうち60㎡ | 第一種住居地域 | 60% | 200% |
※前面道路は12㎡以上とする
この場合の建ぺい率は、以下の式で計算できます。
第二種中高層住居専用地域に相当する部分:50%×(40/100)=20%
第一種住居地域に相当する部分の部分:60%×(60/100)=36%
第二種中高層住居専用地域に相当する部分と第一種住居地域に相当する部分、それぞれの敷地内の割合を考慮した合計値である56%が、この敷地の建ぺい率の上限です。
容積率も同様の方法で、以下のように計算し、
第二種中高層住居専用地域に相当する部分:100%×(40/100)=40%
第一種住居地域に相当する部分の部分:200%×(60/100)=120%
上記の合計値である160%が上限となります。
3. 建ぺい率・容積率の注意点・確認ポイント

建ぺい率や容積率を超えて建物を建築することは、都市計画法や建築基準法の違反行為となります。違反が発覚した場合、行政から改築や撤去を命じられる可能性があるため注意が必要です。
建ぺい率・容積率を正しく計算し、法律を遵守した住宅を建てるためにも以下の点に注意しましょう。
- 敷地面積の正確な把握
- 制限を緩和する要件の確認
- 将来に備えた設計か確認
- 建築確認申請との整合性
3.1. 敷地面積の正確な把握
建ぺい率・容積率を正しく計算するには、敷地面積の正確な把握が重要です。敷地面積が想定より小さいと、建物の面積や容積が上限を超えてしまう可能性があるためです。
敷地面積は、表面積ではなく真上から見た面積(水平投影面積)で計測されます。斜面がある場合や土地に高低差がある場合は、正確な計測が難しいことから、実際より小さく計算されることがあるため注意が必要です。
また、昔からある土地では、不動産登記簿に記載されている情報が古い場合もあるため注意しましょう。登記簿面積と実際の面積に差があることに気付かないまま住宅計画を進めると、のちのち思わぬトラブルにつながる可能性があります。
注文住宅の場合、依頼先の建築会社によって、敷地の形状や面積、敷地にかかる法規制や地盤の強度などを調査する「敷地調査」がおこなわれるのが一般的です。調査結果に疑問や不明点がある場合は、建築会社の担当者に確認しましょう。
3.2. 制限を緩和する要件の確認
地域や建物の性能によっては、建ぺい率の上限が緩和されることもあります。
例えば、自治体が指定する角地に位置し、一定の条件を満たした住宅は、建ぺい率の上限に10%加算されます。つまり、建ぺい率が60%と定められている地域では、この場合70%が上限となります。
また、火災予防のために厳しい建築制限がある防火地域に位置し、一定の耐火性能を持つ耐火建築物も、建ぺい率が10%加算されます。
これらの緩和割合は合算が可能なため、防火地域の角地にある耐火建築物の場合、建ぺい率が合計20%加算されます。
参照:国土交通省「建蔽率制限の特例(法第53条第3~6項)-建築基準法(集団規定)」
3.3. 将来に備えた設計か確認
建ぺい率や容積率が上限に達している建物は、それ以上建物を広げたり高さを増したりできません。このため最初から上限ぎりぎりの建ぺい率・容積率で家を建てると、将来の増改築が難しくなる可能性があります。
ライフスタイルの変化に応じて柔軟に住まいを変えられるよう、ある程度余裕を残した設計にしておくと安心です。
3.4. 建築確認申請との整合性
建ぺい率・容積率は、建設予定の建築物が建築基準法に適合しているか確認する「建築確認申請」に必要な項目です。基本的に建築確認申請後の設計変更は認められず、変更する場合は申請の再提出が必要となります。
このため申請後に無断で設計変更したり、申請時の設計と完成した建物に違いがあったりすると、違法建築になる恐れがあるため注意が必要です。
建物完成時におこなわれる完了検査で、建築確認申請時に記載した建ぺい率・容積率と、実際の建物の建ぺい率・容積率が一致していることを確認しましょう。
4. 建ぺい率・容積率違反のリスク
建物を建築する際、建ぺい率や容積率の上限を遵守することは、都市計画法や建築基準法などの法律で義務付けられています。
指定の建ぺい率・容積率を超えて建築した場合、以下のリスクがあります。
- 工事を請け負ってもらえない
- 住宅ローンが利用できない
- 売却が困難になる
4.1. 工事を請け負ってもらえない
建築会社には、建築基準法や都市計画法などの法律に基づいて建物を建築する社会的責任があります。また、法令違反が発覚した際には行政から改築や撤去を命じられる可能性が高いです。
このようなリスクを回避する観点から、建築会社が指定の建ぺい率・容積率を超えた建築物の工事を請け負うことはほとんどありません。
4.2. 住宅ローンが利用できない
違法建築物は、行政から改築・撤去を命令される可能性が高いなどの理由で買い手がつきにくいことから、通常の物件よりも担保価値が低くなります。
法的リスクに加えてこのような資金回収リスクもあるため、違法建築の場合は住宅ローンなど金融機関による融資も受けられないのが一般的です。
4.3. 売却が困難になる
違法建築物には、前述のとおり改築・撤去が必要となる可能性がある、住宅ローンが組めないなどのほかにも、リフォームに制限がかかる、建て替えの際は建物が小さくなるなど、買い手がつきづらくなる要素が複数存在します。
このように指定の建ぺい率・容積率に違反すると、建築物の市場価値が低くなり、売却が困難になるリスクがあります。
5. 建ぺい率・容積率を確認して理想の家を建てよう

建ぺい率・容積率は、ともに土地に対する建物の大きさを表す指標です。家を建てる際には、地域指定の建ぺい率・容積率を把握し、その範囲内で設計する必要があります。土地の条件によっては希望する建物が建てられない場合もあるため、土地選びの段階から慎重に検討しましょう。
分譲戸建て住宅のシェアNo.1(※)の飯田グループのパワービルダーである一建設は、建売・注文住宅はもちろん、無料の土地探し支援ツール「ランディ」や未公開物件の紹介など、土地探しの分野でもお客さまをサポート。
お持ちの土地に家を建てる場合も、お客さまのご希望に沿って最適な間取りをご提案します。
一建設では専任の担当者がご相談から施工、アフターメンテナンスまで一貫してお客さまをサポートします。家づくりに関することなら何でも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※分譲戸建住宅市場におけるシェア(2023年4月1日~2024年3月31日住宅産業研究所調べ)
一建設の注文住宅を見る
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
ご自宅の売却・引越し(住み替え)も一建設にお任せ
一建設の『ラクいえ売却』
住み替えによる不安を無くすために生まれた、一建設の『ラクいえ売却』。
住まいが売れるタイミングと新しい住まいが見つかるタイミングを合わせる必要がなく、
愛着のある住まいが高く売れるまで交渉する手間もありません。
ダブルローンをはじめとする自宅売却のお悩みを解消します。
- #売却後も1年間賃料無料で住み続けられるからゆとりをもった住み替えが可能
- #引越し費用を最大50万円一建設が負担で手厚くサポート
- #新生活に嬉しいキャッシュバック制度あり
- #一建設の取り扱い物件以外も売却可能