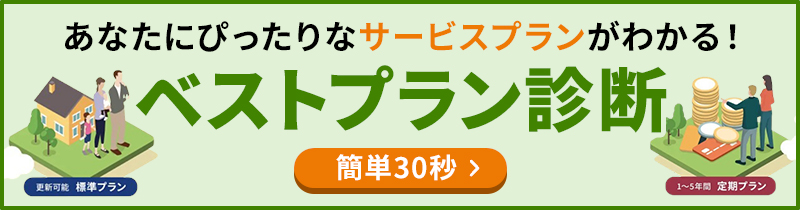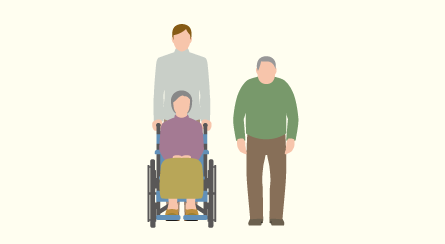年金だけでは老後を安心して過ごせない──そんな不安を抱える方が増えています。物価高騰や医療費の負担、住宅ローンの残債などが重なり、老後資金に「余裕がない」どころか「足りない」と感じる方も少なくありません。 この記事では、年金や老後資金が足りないと感じる理由から対策、今注目されている「リースバック」という選択肢まで、わかりやすく解説します。
老後資金が「ない」と感じる方が増加している理由
年金だけでは生活が難しいと感じる高齢者が増加しています。
2022年度におこなわれた生命保険文化センターの生活保障に関する調査によれば、老後生活に対して「不安を感じている」と回答した方は全体の82.2%に上り、そのうち17.5%は「とても不安」と深刻な懸念を抱えています。多くの方が老後資金に対する不安を抱いており、その割合の高さは社会全体の課題であることを示しています。
その背景には、収入の減少に加え、支出の増加という複合的な課題が潜んでいます。さらに、現役時代に十分な貯蓄や投資をできなかった方や、老後の生活を具体的に想定していなかった方も多く、結果として「資金がない」と感じるケースが増加しています。
年金額の減少
近年、年金額は実質的に目減りしています。
たとえば、令和5年度の厚生年金(夫婦2人分)の平均支給額は月約22万円程度。一方、物価の上昇や実質賃金の低下により、年金の実質的な購買力は低下傾向にあります。また、少子高齢化が進行する日本では、今後も年金額の抑制が続く可能性が高いといわれています。
さらに、厚生年金と比べて支給額が低い国民年金(老齢基礎年金)では、一人あたり満額で月額約6万6,000円程度とされており、それだけで生活を賄うのは非常に困難です。
自営業者やフリーランスとして働いていた方は国民年金のみの受給になるケースが多く、老後の生活資金に不安を感じる大きな要因となっています。
物価高騰
総務省の消費者物価指数によると、2025年6月時点では前年同月比3.3%の上昇を記録。特に食料品や光熱費の値上がりが家計を圧迫しています。収入が固定される年金生活では、こうした物価上昇は生活レベルの低下を直接引き起こします。
また、物価が上がる一方で年金額の増加は緩やかであり、生活費に対して支給額が追いつかないという現実もあります。特に電気・ガス料金や食料品など日常的に必要な支出が上昇することで、家計収支のバランスが崩れ、生活の質を保つために貯蓄を切り崩さざるを得ない高齢者も少なくありません。
住宅ローンの残債
近年は「50代でマイホーム購入」というケースも多く、退職時点で住宅ローンが残っている方もめずらしくありません。定年後も支払いが続くことが、老後の資金計画を困難にしています。
近年では、住宅ローンの返済期間が長期化する方も増えており、60歳以降もローンが残るケースは決して少なくありません。高齢になってからのローン返済は、収入の限られるなかで家計への大きな負担となり、生活の質を維持するうえでも見直しが必要です。
教育費負担の継続
子どもの晩婚化・進学率の上昇に伴い、教育費が長期化しています。
幼稚園から大学まですべて私立に通った場合にかかる費用は、約2,200万円。さらに、結婚資金や孫への支援をおこなう家庭もあり、老後に突入しても教育関連の出費が続くケースもあります。
場合によっては、子どもの奨学金返済を親が一部肩代わりすることもあり、家計への影響が長期化することも。これにより、老後の貯蓄を取り崩さざるを得ない状況に陥る方も少なくなく、資金不足を加速させる要因の一つとなっています。
医療費・介護費の増額
高齢になると避けられないのが医療費と介護費です。高齢者医療の自己負担割合は原則1割(一定以上所得者は2~3割)ですが、入院や手術があれば大きな出費になります。介護においても、在宅介護で月平均5万〜10万円、施設入所では月20万円以上かかることもあります。
これらに加えて、通院や薬代、介護用品の購入など日常的な支出も無視できません。要介護認定を受けると介護保険の適用はあるものの、全額をカバーできるわけではなく、利用回数やサービス内容によっては追加の自己負担が発生します。これらの積み重ねが、長期にわたり高齢者の家計を圧迫する原因となっています。
老後に必要とされる資金とは?

「老後資金はいくら必要?」という疑問は多くの方が抱える課題です。実際の生活費をベースに、世帯ごとの必要額を具体的に見ていきましょう。
一人暮らしの老後にかかる資金
総務省の家計調査(高齢単身世帯)によると、65歳以上の一人暮らし世帯の月平均支出は約15.5万円。
年金収入が月11万円程度と仮定すると、毎月4.5万円の赤字が出ます。これを20年続けた場合、生活費の不足分だけで約1,080万円にのぼります。
さらに、医療費や介護費、住宅修繕費、交際費、冠婚葬祭など突発的な出費を加味すれば、必要な備えは1,500万円以上になると見込まれます。
夫婦世帯の老後にかかる資金
高齢夫婦無職世帯の月平均支出は約25.7万円。一方、年金収入は月22万円前後で、約3万〜4万円の不足となります。老後が30年間続いた場合、総支出額は約9,250万円にも達することになり、年金だけでは到底まかないきれません。
さらに、住宅修繕費や医療・介護費用、冠婚葬祭や突発的な出費を加味すると、必要な貯蓄額は2,000万〜3,000万円以上は必要になるでしょう。
老後資金が足りない場合の対策方法
資金が足りないと感じたとき、今からでもできる対策があります。重要なのは選択肢を知ることと行動することです。以下では、働き続ける方法から公的支援の活用、持ち家の活用まで具体的にご紹介します。
働き続ける
令和5年度の総務省による調査では、労働力人口6,925万人のうち、65歳以上の就業者数が900万人を超え、過去最多を記録しています。
定年退職後は年金だけで生活することに不安を感じる人に向けたシニア向けの再雇用制度や短時間勤務の拡充も進み、週2~3日の勤務でも月5万〜10万円の収入を得ることが可能です。健康維持にもつながるため、働き続けることは有効な選択肢といえます。
家計支出の見直し
固定費の見直しが、老後の家計改善に直結します。例えば、保険の見直しや格安スマートフォンへの変更、サブスクの解約など。月々1万円の支出削減で年間12万円、20年で240万円の節約効果が得られます。
また、光熱費を抑えるために省エネ家電に買い替えたり、使用時間を意識するだけでも支出を削減できます。クレジットカードのポイント活用や、地域の優待制度などを賢く使うことでも、支出を抑える工夫が可能です。
公的支援制度の利用
生活保護や高額療養費制度、介護保険サービスなど、公的支援制度の活用も重要です。
たとえば、高額療養費制度を利用すれば、医療費の自己負担額に上限が設けられ、過度な出費を抑えることが可能です。特に手術や入院などの突発的な医療費に対して大きな効果を発揮します。
また、介護保険では訪問介護やデイサービス、施設入所など多様なサービスが提供されており、要介護認定を受けることで利用が可能となります。自治体によっては家賃補助や生活支援サービス、シルバーパスの交付、地域包括支援センターによる個別相談の実施など、独自のサポートも用意されています。
こうした制度を知り、適切に利用することで、老後の生活負担を軽減できます。
持ち家を活用
持ち家がある方は、それ自体が大きな資産であり、老後の生活を支える重要な手段となります。
例えば、自宅を売却して賃貸住宅に住み替えることでまとまった資金を得たり、リバースモーゲージを利用して住みながら融資を受ける方法もあります。こうした方法はいずれも生活資金の確保に役立ちますが、引っ越しの負担や将来の相続を考えると慎重な判断が必要です。
なかでもリースバックは、現在の住まいに住み続けながら現金化が可能なため、老後の生活スタイルを変えずに資金を得たい方にとってとても有効な選択肢として注目を集めています。
今、注目のリースバックとは?
自宅を売却しても住み続けられるリースバックは、老後資金に困ったときの新しい選択肢として話題です。
リースバックとは、自宅を不動産会社などに売却し、そのまま賃貸借契約を結ぶことで住み続けられる取引です。まとまった資金を得ながら、住み慣れた家で暮らし続けられる点が最大のメリットです。家を手放すストレスを最小限に抑えつつ、資金を確保できます。
主なメリットは以下のとおりです。
- 老後資金を一括で確保できる
- 引っ越し不要で生活環境を維持できる
- 相続対策や債務整理にも有効
リースバックを活用することで、老後の生活費や医療費といった急な出費にも柔軟に対応できる現金を確保できる点が、多くの高齢者にとって魅力となっています。
まとまった資金を一括で得られるため、年金や貯蓄だけでは不安な場面でも心の余裕を持って対応できるという声も増えています。
一建設の「リースバックプラス+」の特徴
リースバックを検討する際は、信頼できる企業を選ぶことが何より大切です。
一建設の提供する「リースバックプラス+」では、以下のようなサービスを提供しており、ご利用いただくすべてのお客様に対し、専門のコンサルタントが資金計画や契約内容のご相談に丁寧に対応します。
- 売却と賃貸借契約がワンストップで完了
- 相談無料
- 売却後も契約内容によっては再購入可能
- 老後資金・介護費用・相続対策など、幅広い用途に対応
また、不動産取引が初めての方でも安心してご利用いただけるよう、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。契約後のサポート体制も万全で、これまで多くのご高齢のお客様から高いご満足の声をいただいております。
まとめ
老後資金がないと感じる方でも、住まいという資産をうまく活用することで、安心した生活を手に入れることは可能です。年金や貯蓄だけでは将来が不安という方でも、自宅を活用すれば新たな選択肢が見えてきます。
そのなかで注目されているのがリースバックという仕組みです。住み慣れた家にそのまま住みながら資金を確保できるため、生活環境を変えることなく、老後のゆとりを生み出す現実的な方法として支持されています。
特に一建設の「リースバックプラス+」は、手続きのわかりやすさと信頼性に定評があり、将来に備えたい多くの方に選ばれています。老後の暮らしに不安を抱える今だからこそ、住まいを守りながら安心を手に入れる手段として、ぜひご検討ください。