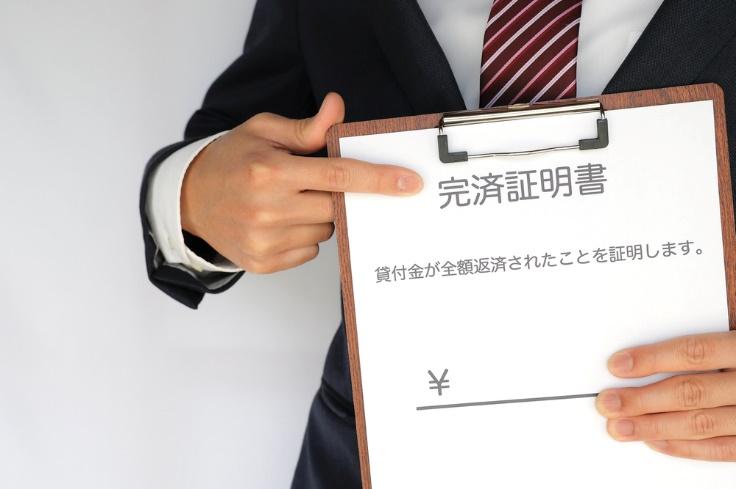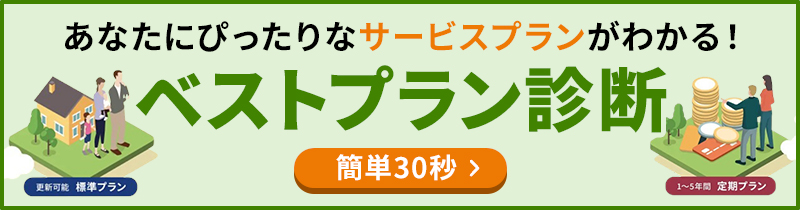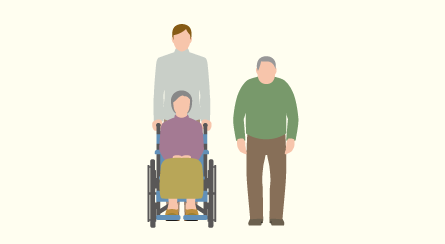住宅ローンは「返済したら終わり」ではありません。完済後は、抵当権抹消や火災保険関係の手続きなどが必要となります。
この記事では、住宅ローン完済までの平均的な期間や、完済後に必要な手続き、抵当権を抹消しない場合のデメリット、抵当権抹消手続きなどについて分かりやすく解説します。住宅ローン完済後の使い道、住宅ローン完済に関するよくある質問も掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
INDEX
住宅ローン完済に必要な平均的な期間
2020年に住宅金融支援機構が発表した「2020年度 住宅ローン貸出動向調査」によると、2019年度に新規で貸し出された住宅ローンの平均返済期間は27.0年(単純平均)でした。2016年度は25.6年、2017年度は26.4年、2018年度は26.7年だったことを踏まえると、ここ数年で平均返済期間が長期化していると考えられます。

一方、2019年度中に完済された債権について、完済までの平均期間は16. 0年(単純平均)でした。2016年度は15.0年、2017年度は15.2年、2018年度は15.7年だったため、こちらも伸長の傾向にあります。
参考:
2020年度 住宅ローン貸出動向調査|住宅金融支援機構
[関連リンク]
住宅ローンの借りすぎで後悔!後悔する人の特徴と対処法について説明
上記のように、完済までの平均期間は20年足らずです。通常、住宅ローンの借入期間は最長35年間である一方で、実際に完済されるまでの平均期間は20年未満となっています。これは、多くの方々が返済を早めて「全額繰り上げ返済」をおこなっているためです。
全額繰り上げ返済をする背景には、以下のような理由があります。
- 低金利の別の金融機関に借り換えるため
- 将来の余裕資金を確保するため
- 子どもたちの独立などで転居が生じたため
なお全額繰り上げ返済とは別に、毎月の返済額に加えて、まとまった金額を返済する「繰り上げ返済」もあります。元金の返済を前倒しすることで、その分の支払利息がなくなり、ローン残高を予定より早く減らせます。返済期間を短縮する「期間短縮型」と、毎月の返済額を減らす「返済額軽減型」に分類され、主に前者が利用されています。
住宅ローン完済時に必要な手続き
完済時には、3つの手続きが必要となります。以下で詳しく解説します。
- 金融機関での繰り上げ返済の手続き
- 抵当権抹消の手続き
- 火災保険の質権抹消の手続き
金融機関での繰り上げ返済の手続き

住宅ローンを一括で繰り上げ返済する場合、金融機関での手続きが必要です。銀行ごとに必要な手続きが異なるため、詳細は銀行の担当者や窓口にご確認ください。
一般的には、一括返済をおこなう予定の1ヵ月以上前に連絡を取ることで、手続きをスムーズに進められます。ただし、住宅ローンの一括返済時には、元本や利息だけでなく、手数料も発生することに注意が必要です。この手数料の金額は金融機関によって異なるため、一括返済を申し込む際には必ず料金を確認しておきましょう。
抵当権抹消の手続き
住宅ローンの返済が完了したあとには、抵当権抹消の手続きが必要です。
抵当権とは、住宅ローンなどで融資が発生する際、購入する土地や建物に対して金融機関が設定する権利を指します。一般的に、不動産登記簿に抵当権設定を登記することが条件です。抵当権を行使することで、ローンの借り手(債務者)が返済不能となった際、貸し手(債権者)が借り手の土地や建物から返済を受けられる仕組みになっています。
住宅ローンを完済すると、借り手は不動産の登記から抵当権を削除できます。金融機関は抵当権抹消手続き案内と必要書類を提供しますが、手続き自体は債務者がおこないます。抵当権抹消は義務ではありませんが、手続きを怠ると、将来的に買い手が見つからなかったり、土地や建物を担保に新たな融資が受けられなかったりするなどの不都合が生じる可能性があります。
また、金融機関から提供される抵当権抹消に関する書類には有効期限が設定されている場合が多いため、早めの手続きをおすすめします。
火災保険の質権抹消の手続き
住宅ローンを活用する際、火災保険に関連した質権設定がおこなわれることがあります。これは、もし火災が発生して住宅が被害を受けた場合、火災保険による保険金が金融機関に支払われる仕組みです。仮に建物が火災により全焼した場合、抵当権は実行できなくなりますが、質権が設定されていれば、金融機関は貸付金を回収できます。
質権が有効な場合、住宅ローンの返済完了後に金融機関から「保険証書」とともに「質権消滅確認請求書」が送付されます。この通知を受けて、債務者が保険会社と連絡を取り、質権の解除手続きを進めることが必要です。
抵当権を抹消しない場合のデメリット

先ほど「抵当権抹消は義務ではない」とお伝えしましたが、抹消しない場合、4つのデメリットがあります。
- 不動産の買い手がつきにくくなる
- 所有者が亡くなった場合、抹消手続きに時間がかかる
- 新しい融資を受けるときに不利になる
- 抹消書類の再発行に手数料や手間がかかる
不動産の買い手がつきにくくなる
不動産に抵当権が残っている場合、登記簿謄本の乙区に表示されます。購入希望者が現れても、抵当権が謄本上で確認できることから、「本当に住宅ローンは完済されているのか」と不安が生じ、売却が難しくなります。
実際には、抵当権が残っていても売却自体はできるため、売れないとは断言できませんが、買い手がつきにくくなる可能性は高いでしょう。第三者に対する抵当権が存在しないことを明示するには、抵当権の抹消が必要です。
所有者が亡くなった場合、抹消手続きに時間がかかる
抵当権を抹消しないまま所有者が亡くなると、新たな所有者となる相続人が抵当権を抹消しなければなりません。
しかし、複数の相続人がいる場合、物件の相続人が確定するまで手続きは遅れます。遺言書が存在しない場合は、遺産分割の協議がおこなわれ、抹消手続きの前に名義を相続人に変更する相続登記が必要となり、抵当権の抹消までさらに時間がかかる可能性があります。
新しい融資を受けるときに不利になる
不動産に抵当権が残っていると、住宅ローンを返済し終わっていないことになるため、新たな融資を受けることは非常に難しいです。
抵当権の優先順位は、登記された順番によって決まります。先に登記された抵当権が残っている場合、金融機関は融資に慎重になります。将来的に新たな借り入れの予定がなくても、住宅ローンを完済しているのであれば、早めに抵当権を抹消しておきましょう。
リフォーム用などで新規の融資を受ける際、自宅を担保にする場合も、抵当権が残っていると、抵当権付き不動産として判断されてしまい、ローンの審査で不利になる恐れがあります。
抹消書類の再発行に手数料や手間がかかる
抵当権の抹消手続きには、住宅ローンの完済後、金融機関から送付される「抹消書類」が必要です。手続きを先延ばしにすると、書類を紛失するリスクが高まります。もし抹消書類を紛失してしまうと、再発行には手数料や手続きの手間が生じるため、迅速に手続きをおこなうことが大切です。
ただし、手続きに慣れておらず、書類を忘れたり、手続きに不備が生じたりすると、居住地を所管する法務局に何度も足を運ばなければなりません。自分で手続きをおこなう際には、こうしたデメリットも考慮しましょう。
抵当権の抹消手続きをおこなう方法
抵当権抹消は、司法書士に依頼して手続きする方法と、自分で手続きする方法があります。ここでは、それぞれの手順や費用、必要なものを解説します。
司法書士に抵当権抹消手続きを依頼する場合
依頼の流れ
司法書士に手続きを依頼する場合の手順は、以下の通りです。
- 住宅ローンの完済後、金融機関から抹消書類を受け取る
- 司法書士に抵当権の抹消手続きを依頼する
- 司法書士が作成した抵当権抹消登記委任状に署名・押印する
- 抵当権抹消登記委任状と抹消書類を司法書士に提出する
- 委任状と抹消書類をもとに、司法書士は手続きをおこなう
- 抹消登記完了後、抹消を確認できる書類が送付される
必要なもの
抵当権抹消手続きを司法書士に依頼する際、登録免許税と司法書士の報酬が必要です。
費用
登録免許税は、<不動産の数×1,000円>で計算します。例えば、土地1筆と建物1棟の場合は2,000円かかります。抵当権抹消手続きの場合、司法書士の報酬相場は、10,000円から15,000円とされています。

自分で抵当権抹消手続きをおこなう場合
手続きの流れ
次に、自分で手続きする場合の流れを確認しましょう。
- 住宅ローンの完済後、金融機関から抹消書類を受け取る
- 自身の居住地を所管する法務局を調べる
- 法務省サイトから「抵当権抹消登記申請書」を取得する
- 居住地を所管する法務局に、取得した申請書と必要書類を提出する(マイナンバーカードがあればオンライン申請も可能)
- 抹消登記手続きの完了を確認できる書類を受け取る(法務局での受け取りか郵送から選択可能)
必要なもの
抵当権の抹消手続きにあたり、以下のものが必要となります。ご自身で準備しなければいけないものは忘れずに準備しましょう。
金融機関から送付されるもの
- 登記識別情報(登記済証)
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書や弁済証書などに解除の旨が記載されたもの)
- 金融機関等の会社法人等番号
- 代理権限証明情報(委任状)
- 抵当権抹消の委任状(金融機関などの印鑑があるもの)
自分で準備するもの
- 抵当権抹消登記申請書(法務局のホームページから入手可能)
- 認印
- 登録免許税(収入印紙)
- 免許証などの身分証明書
抵当権の抹消登記申請手続きについては、法務局サイトで分かりやすく説明されています。
参考:
住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)|法務局
費用
自分で手続きする場合にかかる費用は登録免許税のみです。登録免許税は、不動産の個数に基づき、〈不動産の数×1,000円〉で計算します。土地1筆と建物1棟の場合は、合計で2,000円となります。
住宅ローン完済後も生じる費用
ローンを完済した後も生じる、3つの費用について解説します。
固定資産税
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産にかかる税金です。具体的には、総務大臣が定めた基準に従い、市区町村長が固定資産評価額(課税標準額)を決定し、税率1.4%をかけた金額を固定資産税として納める必要があります。固定資産評価額や税額は、納税通知書で確認できます。
また、市街化区域に不動産を所有している場合、固定資産税に加えて都市計画税も納税しなければなりません。税率は0.3%です。
参考:
火災保険料
火災保険は、火災や自然災害、盗難などで生じた建物や家財への損害を補償する保険です。建物の購入時、ほとんどの方が契約していると思います。住宅ローン完済後も火災保険に加入し続ける場合、毎月保険料がかかることを覚えておきましょう。
修繕費
経年劣化や破損、不具合が発生すれば、建物を修繕しなければなりません。大きな修繕なら一度で100万円を超えるケースも少なくないため、修繕費は計画的に準備する必要があります。
住宅ローン完済後のお金の使い道

住宅ローンを完済すると、これまでローン返済に充てていた資金が余剰となります。しかし、この余剰資金を適切に管理しないと、使い過ぎてしまうかもしれません。そんな事態を避けるためには、これまでローン返済に充てていた資金をこれからどう使うかを慎重に検討し、計画を立てることが大切です。
定年退職後の再雇用期間中、定年前ほどの収入は得られないかもしれませんが、一定の収入は維持されることが一般的です。この収入を活用して、これまでローン返済に充てていた資金の一部を将来のために積み立ててみるのはいかがでしょうか。例えば、毎月自動的に引き落とされる積み立て商品に投資することで、お金が自然と貯まっていき、過度の支出を防ぐことにもつながります。
住宅ローン完済についてよくある質問
ローン完済に関するよくある質問をいくつかご紹介します。
よくある質問① 一括返済した場合、住宅ローン控除はどうなる?
一度に全額返済すると、住宅ローン控除の対象から外れます。また、一部繰り上げ返済し、返済期間が短縮され、残りの期間が10年未満となる場合も、控除が適用されなくなるため、注意が必要です。
参考:
よくある質問② 完済したら2軒目でも住宅ローンを利用できる?
住宅ローンを完済している1軒目を売却して、2軒目に住み替えで引っ越す場合、2軒目も住宅ローンの利用は可能です。ただし、住宅ローンは原則、居住用の物件に利用されることが前提となります。投資用の物件などを2軒目として購入する場合には利用できません。
よくある質問③ 2軒目も住宅ローンの控除が適用になる?
住宅ローン控除は、住み替え時に要件を満たす場合にのみ適用されます。親族の居住用やセカンドハウス用に借りた住宅ローンについては、この控除の対象外となります。
まとめ
住宅ローンが完済される期間は平均で20年未満です。多くの方々が返済を早めて、全額を繰り上げ返済していると考えられます。
ローン完済後には、抵当権抹消や火災保険の手続きが必要です。抵当権を抹消しないと、不動産の売却が難しくなったり、相続の際に手間が増えたりする可能性があります。なお、抵当権抹消手続きは、自分でおこなう方法と司法書士に依頼する方法があります。どちらにしても、手続きには時間がかかるため、事前に知識を身につけて、手順などを把握しておくと安心です。
またローン完済後には、資金を適切に管理するために、積み立て型の金融商品を検討するのも良いでしょう。
長い返済期間の間には、さまざまな理由で住宅ローンの支払いが難しくなることもあります。住宅ローンの早期完済を目指す方は、リースバックという方法も検討してみてはいかがでしょうか。リースバックとは、持ち家を「住みながら売却」できる資産活用法です。一建設の「リースバックプラス+」は、独自のメリットを盛り込んだ2プラン3タイプをご用意しています。気になった方はぜひご検討ください。