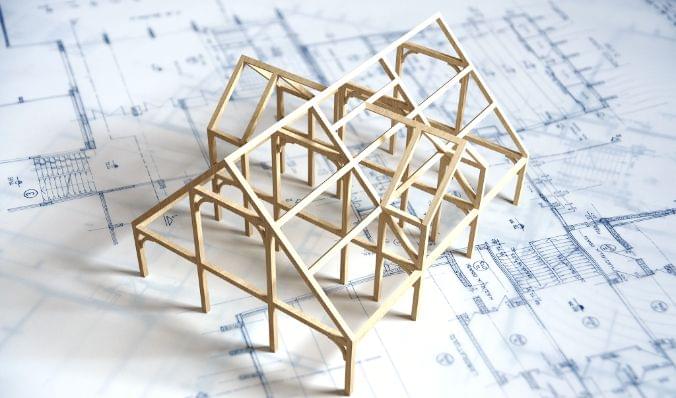2024.09.11 | 二世帯住宅
二世帯住宅はやめた方がいい?デメリットだらけと言われる理由やメリット、気をつけるポイントを解説!

目次
はじめの二世帯住宅プラン
一建設では、親世帯と子世帯がそれぞれ快適に暮らせる二世帯住宅をご提案しています。
完全分離型から一部共用型まで、生活スタイルに合わせた自由な設計が可能です。
収納やリビングの空間設計、開放的なキッチンなど、暮らしやすさに配慮した工夫も充実。
高品質かつコストパフォーマンスに優れた家づくりをお考えの方は、ぜひ一建設の二世帯住宅プランをご覧ください。
二世帯住宅を検討しているけれど、インターネットや周囲の人からは「やめた方がいい」と言われ、決断できずに困っている……。そんな方はいらっしゃいませんか?
しかし、デメリットを回避する工夫をすれば、二世帯住宅のメリットを感じながら快適に生活できます。
そこでこの記事では、二世帯住宅のメリット・デメリット、二世帯住宅に適した間取り、二世帯住宅で暮らすうえでの注意点などを、わかりやすく解説します。
1. 二世帯住宅はやめた方がいいといわれる理由【デメリット】
まず、二世帯住宅のデメリットは大きく分けて6つあります。
- プライバシーの確保が難しい
- 費用や家事の負担割合で揉めやすい
- 生活リズムが合わない
- 共用部分の使い方で揉めてしまう
- 二世帯住宅は売却しにくい
- 相続でトラブルになりやすい
1.1. プライバシーの確保が難しい
二世帯住宅のデメリットと聞くと、多くの方がプライバシーの確保を思い浮かべるのではないでしょうか。
本来、自宅はプライベートな空間です。しかし、二世帯がともに暮らすとなると、生活音や服装など気を遣う場面が多くなり、プライバシーの確保が難しくなります。特に、実の親子ではない配偶者はストレスが溜まりやすい傾向にあるため、二世帯住宅を検討する際は、各世帯のプライバシーを確保できる工夫が必要になります。
1.2. 費用や家事の負担割合で揉めやすい
二世帯住宅を設計する段階では、建築費や光熱費の割合など、支払いについて具体的に決めていないケースが多いため、のちのちトラブルになりやすいとされています。特に建築費は、「二世帯で折半するから大丈夫」と考えてしまいますが、住宅ローンに関しては返済までに長い年数がかかるため、リスクを踏まえて検討しましょう。
また、家事の負担割合もトラブルの元です。キッチンや浴室など生活に必要な設備を完全に共用する場合、料理や掃除をどちらがするかで揉めるといったケースが考えられます。
こういった負担割合で揉めてしまうと、二世帯間の関係が悪化してしまいかねないため、しっかり話し合いをすることが大切です。
1.3. 生活リズムが合わない
二世帯住宅では、一つの建物に2つの家族が住むことになるため、生活リズムの違いが生まれてしまいがちです。例えば、親世帯が早起きをするため、子世帯の就寝中に掃除機や洗濯機をかけて、大きな音が気になってしまうといったシーンが想像できます。
また、親世帯からすると、子どもの声や足音がうるさい、寝ているときに子世帯がテレビをつけていて眠れないといったストレスがあるかもしれません。
1.4. 共用部分の使い方で揉めてしまう
キッチンやリビングなどのスペースを共用にしている場合、譲り合う必要があり、どちらかの世帯が使い方に無頓着だったりすると、トラブルに発展することがあります。
例えば、洗濯機一つにしても、どの時間にどれくらいの洗濯物を洗いたいかで揉めてしまうといいます。自宅なのに自分のペースで使えないとなると、ストレスを感じてしまうこともあるため、注意が必要です。
1.5. 二世帯住宅は売却しにくい
当然のことですが、二世帯住宅を買う人は二世帯住宅に住む人に限られます。そのため、二世帯住宅は、一般的な一戸建てと比較して需要が少なく、売却しにくいといわれています。特に、共用部分の多い二世帯住宅は、売却が難しい可能性が高いです。売却しても相場より安い金額になることを想定しておきましょう。
1.6. 相続でトラブルになりやすい
二世帯住宅を共有名義で購入した場合、親が他界した際、親の持ち分に対して兄弟姉妹などに相続が発生するため、トラブルになりやすいです。
例えば、親世帯と子世帯で5割ずつの持ち分だとすると、親の他界時には、親の持ち分を兄弟姉妹で分ける必要が出てきます。引き続き住むためには持ち分に相当する資産を兄弟姉妹に提供する必要がありますが、子世帯が用意できない場合、家の売却を要求されることもあるため、相続についても事前の相談が重要です。
1.7. 一建設の二世帯住宅は快適な暮らしを実現
一建設では、二世帯住宅もご提供しています。一建設の二世帯住宅は、ご家族での共同生活を豊かで安心できるものにするため、プライバシーの確保や共用部分の快適さを実現します。
詳しく知りたい方は、ぜひこちらをご覧ください。
2. 二世帯住宅のメリット

二世帯住宅にはメリットもたくさんあります。ここでは6つのメリットをご紹介します。
- 親からの援助が受けられる
- 子育てや介護、家事などが協力しやすい
- にぎやかで楽しい
- 家に常に誰かがいて安心できる
- 補助金や税制上のメリットがある
- 相続税を抑えられる可能性がある
2.1. 親からの援助が受けられる
親の援助が受けられることは、二世帯住宅の最大のメリットです。具体的には、二世帯住宅を建てる場合、親が所有する土地や実家を活用するケースが多いため、費用を抑えられます。
また、将来の介護も考慮して親が費用を多く支払うケースも少なくないようです。二世帯住宅を建てる際は、親世帯の援助をどの程度受けられるか、事前に確認しておきましょう。
2.2. 子育てや介護、家事などが協力しやすい
二世帯住宅は、親世帯が同居しているため、離れて暮らすよりもサポートを受けやすい傾向にあります。例えば、子どもの看病や送り迎えで協力してもらいやすかったり、子世帯が親世帯の健康状態を把握しやすかったりするでしょう。子育てや家事が協力しやすい点は、特に共働きの子世帯にとって大きなメリットといえます。
2.3. にぎやかで楽しい
二世帯で暮らすと、一世帯で暮らす場合と比較して家がにぎやかになります。これにより二世帯間のコミュニケーションが取りやすくなったり、親が共働きでも子どもに寂しい思いをさせないようにできたりといった利点が生まれます。
2.4. 家に常に誰かがいて安心できる
小さな子どもがいる場合、親世帯が同じ家にいると子どもを任せて安心して出かけられます。また、家が無人になるタイミングが減れば、空き巣に狙われる危険性が下がり、防犯につながることでしょう。
2.5. 補助金や税制上のメリットがある
2024年8月現在、二世帯住宅には、地域型住宅グリーン化事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業、地域の住宅補助などの補助金を受けられる可能性があります。
また、不動産所得税、固定資産税、都市計画税などで税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。
こういった優遇措置は制度によって条件が異なるため、二世帯住宅を検討する際は国や自治体のサイトをしっかり確認しましょう。
2.6. 相続税を抑えられる可能性がある
二世帯住宅は、相続時の税金を抑えられる可能性があります。
具体的には、小規模宅地等の特例制度が適用されれば、土地の評価額が最大80%減額されるため、相続税の課税対象額が引き下げられ、相続税額を抑えられます。適用には細かい条件があるため、詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
>>国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
3. 二世帯住宅が向いていない人の特徴

ここまで二世帯住宅のメリット・デメリットをお伝えしてきましたが、次のような方は二世帯住宅は向いていないでしょう。以下で詳しくご紹介します。
- ルールを守るのが苦手な方
- コミュニケーションが苦手な方
- 生活音や人に敏感な方
- 親世帯との関係性に不安がある方
3.1. ルールを守るのが苦手な方
二世帯住宅では、年代や価値観、生活リズムの異なる二世帯がともに暮らすため、誰かがルールを破ってしまうとストレスを感じる人が出てきてしまいます。
例えば、家事を折半するルールをどちらかが破るともう片方の世帯に家事の負担が集中してしまい、家族内の関係性が悪化する恐れもあります。同居する際には、二世帯でルールを守れるのか、必ず話し合いましょう。
3.2. コミュニケーションが苦手な方
二世帯住宅でよくある悩みの一つが、子育てや家事で親世帯の目が気になるというものです。実際、二世帯住宅はプライベートな空間が限定されるため、親世帯とのコミュニケーションなどでストレスを感じてしまう可能性があります。
3.3. 生活音や人に敏感な方
二世帯住宅で共用部分が多い場合、生活音や人の気配を感じやすくなります。普段から生活音や人に敏感だと感じている方は、二世帯住宅の間取りを工夫するなどの対策が必要です。
3.4. 親世帯との関係性に不安がある方
いくら二世帯住宅にはメリットがあるといっても、親世帯と距離を置きたい方や、パートナーが親世帯の肩を持つことに不満がある方の場合、同居すると毎日の生活でストレスや疎外感を感じることが多くなってしまいます。
二世帯住宅を検討しているのであれば、両親やパートナーとの関係性も忘れずに考えるようにしましょう。
4. 二世帯住宅の間取り3種類 やめた方がいい間取りはある?

二世帯住宅を建てるうえで、間取りはとても重要なポイントです。代表的な間取りは3種類あります。
- 完全分離型
- 部分共有型
- 完全共有型
ここからは、各間取りの詳細や、どのような方に向いているか、やめた方がいい間取りはあるのかを説明します。
4.1. 完全分離型
完全分離型は、玄関や水廻りなどの各スペースが世帯ごとに分離している間取りです。賃貸マンションで隣同士の部屋に住んでいる様子をイメージすると良いでしょう。
完全分離型は設備が2倍必要なため、建設費が高額になる場合がほとんどですが、プライバシーの確保や食費・光熱費を世帯ごとに管理できる点がメリットです。親世帯のことは心配だけれど、生活する場所は分けたい方に向いています。
4.2. 部分共有型
部分共有型は、完全分離型と異なり一部のスペースを二世帯で共有する間取りで、完全分離型よりも費用を抑えられるのが魅力です。また、部分共有型では1階を親世帯2階を子世帯が使用するケースが多いため、比較的プライバシーを確保しやすいといえます。一般的に玄関やリビングを共有する場合が多いため、そういった部分の共有が苦でない方に向いています。
ただし、どこまでを共有部とするかで、暮らし始めてからトラブルが発生しやすいデメリットがあるため、設計時に両世帯できちんと相談しておきましょう。
4.3. 完全共有型
完全共有型は、個人の部屋以外のスペースを二世帯で共有する間取りです。共有スペースが多いため、完全分離型や部分共有型より費用を抑えられます。
しかし、完全共有型はプライバシーの確保が難しく、人によってはストレスを感じやすい間取りといえます。そのため、親世帯との密なコミュニケーションを好む方に向いています。
4.4. 一建設の二世帯住宅なら自由な設計が可能
一建設の二世帯住宅なら、多様な生活スタイルに応じて完全分離型から部分共用型まで自由な設計が可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
5. 二世帯住宅でトラブルにならないために気をつけるべきポイント
最後に、二世帯住宅を検討する際、トラブルにならないために気をつけるべきポイントを3つご紹介します。
- 生活スタイルに合わせた間取りにする
- 家のルールをしっかり決めておく
- 遮音性・防音性を高める
5.1. 生活スタイルに合わせた間取りにする
二世帯住宅にはたくさんの人が一緒に住むため、にぎやかで楽しいというメリットがあります。その反面、生活リズムの違いからトラブルが生まれやすいのも事実です。
例えば、子世帯が夜勤のある仕事をしている場合、玄関やリビングを共有していると親世帯は生活音が気になって眠れないかもしれません。その場合、完全分離型を選択することでトラブルを回避できます。このように、自分たちの生活リズムに合わせた間取りを検討しましょう。
5.2. 家のルールをしっかり決めておく
二世帯住宅では、建築費や住みはじめてからの水道光熱費の支払い、家事、子育てなど、さまざまな事柄を二世帯間が共有・分割することになります。事前にルールをしっかり決めておかないと、負担する人が曖昧になり、誰かがストレスを感じてしまうかもしれません。
また、実際に生活を始めたあとも、体調や経済的状況の変化に合わせ、柔軟にルールを更新していくことが大切です。
5.3. 遮音性・防音性を高める
二世帯住宅で音は大きなトラブルの元です。小さな子どもが大きな声を出したり、足音が下の階に響いたりするシーンをイメージしてみてください。こういったストレスを軽減させるために、遮音性や防音性の高い建材を取り入れると良いでしょう。
6. 二世帯住宅はやめた方がいいといわれる理由と気をつけるべきポイントを知ろう
二世帯住宅は、プライバシー確保の難しさや売却しにくさなどから、やめた方がいいとされています。その一方で、家に常に誰かがいる安心感や、補助金や税制上の優遇措置などメリットもあります。ただし、ルールを守るのが苦手な方や、親世帯との関係性に不安のある方は、二世帯住宅はおすすめできません。
二世帯住宅には、完全分離型、部分共有型、完全共有型という3種類の間取りがあります。各家庭の生活スタイルに合わせた間取りを選びましょう。また、同居を始めてからトラブルにならないよう、家のルールを事前に決めておいたり、遮音性や防音性の高い建材を使用したりすることが大切です。
一建設は二世帯住宅の実績も豊富です。生活スタイルに合わせてさまざまなご提案が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
一建設の注文住宅を見る
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
ご自宅の売却・引越し(住み替え)も一建設にお任せ
一建設の『ラクいえ売却』
住み替えによる不安を無くすために生まれた、一建設の『ラクいえ売却』。
住まいが売れるタイミングと新しい住まいが見つかるタイミングを合わせる必要がなく、
愛着のある住まいが高く売れるまで交渉する手間もありません。
ダブルローンをはじめとする自宅売却のお悩みを解消します。
- #売却後も1年間賃料無料で住み続けられるからゆとりをもった住み替えが可能
- #引越し費用を最大50万円一建設が負担で手厚くサポート
- #新生活に嬉しいキャッシュバック制度あり
- #一建設の取り扱い物件以外も売却可能
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
注文住宅のオプション53選!新築でやっておけばよかったと後悔しないための選び方や費用相場を紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅の費用相場は?価格帯・広さ別の相場と費用を抑えるコツを解説
「注文住宅を建てたいけど、一体どれくらいお金が必要なんだろう……。」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。そ...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

「平屋はやめたほうがいい?」平屋のメリット・デメリットを9つずつ解説
2024.09.24 | 平屋
おすすめ記事
-

2024.03.15 | 費用・制度
【違いを比較】注文住宅と建売(分譲)住宅はどっちがいい?価格差は?
マイホームの取得を検討するなか、注文住宅にすべきか建売住宅(分譲住宅)にすべきかで迷う方は多いかと思います。設計の自由...
-

2025.02.13 | 平屋
平屋とは?平屋のメリット・デメリットと建築実例をご紹介
戸建て住宅の一般的な階層構造としては、平屋と2階建て、3階建てがあります。これから家を建てる方のなかには、何階建てにす...
-

平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
2025.06.13 | 平屋
-

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
2025.12.12 | 注文住宅
-

注文住宅とは?メリット・デメリットや後悔しないためのポイントをわかりやすく解説
2024.03.15 | 注文住宅
新着記事
-

2026.01.19 | マイホーム
2階リビングの魅力とは?メリット・デメリットと後悔しないためのポイントを解説
立地条件によっては、1階にリビングを設けると、十分なスペースや日当たりを確保できないケースもあるでしょう。 その...
-

2025.12.12 | マイホーム
ウォークインクローゼット設置のおすすめの間取りとは?注意すべきポイントや建築実例を紹介
衣類や荷物が増えるほど、「スッキリ片づく収納がほしい」と感じる方は多いでしょう。そんな願いを叶えるのがウォークインクロ...
-

シューズインクローゼットとは?シューズクロークとの違いや種類、メリット・デメリットを解説
2025.12.12 | マイホーム
-

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
2025.12.12 | 注文住宅
-

家を建てるには何をすればいいのか。流れや費用などの基礎知識と4つの注意点!
2025.12.01 | マイホーム