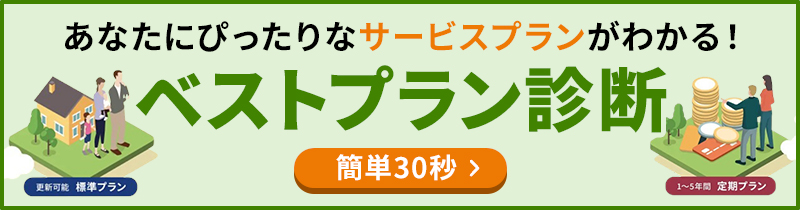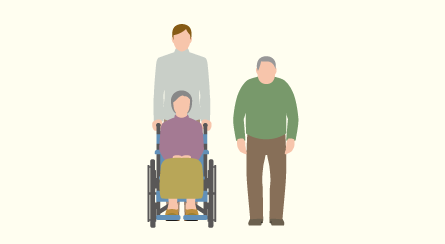毎月支払う住宅ローン。その返済負担が家計を圧迫し、なかには任意売却を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、任意売却するには一定の条件を満たす必要があり、誰でも・いつでもできるわけではないため注意が必要です。
そこでこの記事では、任意売却ができない原因や代表的な事例10選をご紹介します。任意売却のメリット・デメリットなどの基礎知識から、任意売却できない・売れない事態を防ぐための対処法まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
INDEX
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難な場合、債権者(金融機関)の同意のもと、一定の条件で不動産を売却することです。
通常、住宅ローン返済中の物件には、抵当権が設定されています。抵当権とは、土地や建物などの不動産を担保とする権利です。万が一債務者がローンを返済できなくなった場合、債権者は担保である対象の不動産を売却することで資金を回収できます。
住宅ローン返済中の物件を売却するには、債権者である金融機関の承諾を得て、抵当権を解除してもらう必要があります。
住宅の売却金額が住宅ローンの残債を上回るアンダーローンの場合であれば、売却代金で残債を一括返済できるため、特に問題なく売却が可能です。
しかし、売却金額がローンの残債を下回るオーバーローンの場合は、売却代金で住宅ローンの残債を完済できません。そのため、金融機関の許可のもと、売却価格や売却時期などの条件を調整しながら、売却活動を進める必要があります。
任意売却を検討するのはどんなとき?
任意売却を選択すれば、オーバーローンの状態でも自宅を手放し、売却代金を住宅ローンの返済にあてることが可能になります。
一般的に、任意売却が検討されるケースは以下のとおりです。
住宅ローンの返済が困難な場合
一般的に、任意売却は住宅ローンの返済が困難になった場合の救済措置として知られています。
失業や病気、怪我などで収入が減少し、住宅ローンの滞納が続くと、自宅は最終的に競売にかけられてしまいます。
競売とは、裁判所を通じて不動産を強制的に売却する手続きです。市場相場より低い価格で落札されるのが一般的なため、債務者により多くの借金が残る恐れがあります。
それに対して任意売却は、金融機関の同意を得たうえで、物件を市場で売却する方法です。競売より高額で物件を売却できる可能性が高いため、債務の圧縮が期待できます。
離婚する場合
離婚時にも、任意売却はよく検討されます。
離婚後どちらも今の家に住まない場合は、自宅を売却するのが現実的なためです。
オーバーローンの場合は、金融機関の承諾を得て、任意売却の手続きが必要となります。
ただし、共有名義の場合や、夫婦のいずれかが連帯保証人や連帯債務者となっている場合、任意売却をおこなうには双方の合意が必要です。
また、住宅ローンの返済義務は離婚後も継続します。例えば、元妻が連帯債務者である場合、主たる債務者である元夫の返済が滞れば、元妻に請求がいくことになります。そのため離婚時は、任意売却後の残債に関しても、今後の返済計画を話し合う必要があります。
債務整理をしている場合
債務整理とは、弁護士などの専門家を通じて、借金の減額や免除、返済計画の見直しなどを図る手続きのことです。
任意売却は、こうした債務整理の手段の一つとしておこなわれる場合もあります。
例えば、自己破産の手続きでは、裁判所の許可を得ることで、借金の返済が免除されます。その際、債務者に代わって財産を管理する破産管財人の判断によって、任意売却が選択されることがあります。
任意売却のメリット
任意売却を選択する主なメリットは以下のとおりです。
競売を回避できる
住宅ローンの滞納が6ヵ月~10ヵ月ほど続くと、裁判所から競売開始決定通知が届きます。
競売では「内覧ができない」「検討する時間が短い」などの理由から、不動産の落札金額が市場価格より安くなる傾向にあります。また、情報が公示されるため、近隣住民に知られやすいなどプライバシーの問題も深刻です。
その点、任意売却は市場で不動産を売買するため、競売より高額で売却できる可能性が高いです。また、住宅ローンの滞納が原因であるなど、売却の理由を近所に知られる心配もありません。
このように任意売却を選択すれば、債務者にとってデメリットの多い競売を回避できます。同様に、債権者(金融機関)にとっても、競売よりも高額で売却できる可能性が高いことから、より多くの残債を回収できるというメリットがあります。
生活を立て直しやすい
競売では、裁判所主導で売却が進むため、不動産が落札され、所有権が移転した時点で、強制的に退去を求められます。
その点任意売却では、債権者(金融機関)や買い主との交渉しだいで、引っ越し時期などスケジュールの調整が可能です。
また、債権者(金融機関)の配慮によって、売却代金から引っ越し費用を捻出してもらえる場合もあります。
売却後も同じ家に住み続けられる可能性がある
基本的に、任意売却では仲介を依頼する不動産会社を自由に選ぶことが可能です。
その相談先として、リースバックが得意な不動産会社を選択すれば、今の家に住み続けられる可能性があります。
リースバックとは、売買契約と賃貸借契約を組み合わせたサービスです。自宅を売却した後、新たな所有者と賃貸借契約を結ぶことで、賃貸物件として自宅に住み続けられます。
「リースバックプラス+」は、一建設が提供するリースバックサービスです。
自宅売却後もずっと安心して住み続けられる「標準プラン」や賃料重視の「定期プラン」など、お客様のライフスタイルやニーズに合わせた2プラン3タイプをご用意しております。
住宅ローンが残っている物件でも原則利用できますので、興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
任意売却のデメリット
一方、任意売却には以下のようなデメリットも存在します。
売却に手間がかかる
任意売却を進めるには、債権者(金融機関)をはじめ、共同名義人や連帯保証人など、不動産の所有権や債務に関わる全員の同意が必要です。
同意を得たあとも、債権者(金融機関)への連絡・交渉や、購入希望者への内覧対応など、さまざまな準備や調整が必要となります。
このように任意売却を成功させるには、さまざまな手続きを自分でおこなわなければならず、多くの時間と労力を要します。
必ず売却できるとは限らない
任意売却は、市場で買い主を探して売却する方法です。そのため、そもそも購入希望者が現れなければ最終的に競売に移行します。
また、売却価格や引っ越し時期などの希望条件を提示しても、買い主が応じない場合もあります。
このように任意売却を選択したからといって、必ずしも希望どおりに売却できるとは限らないため注意が必要です。
任意売却できない原因は?10のケースを解説

任意売却は、競売に比べて債務者・債権者の双方にとってメリットのある選択肢です。
しかし、以下のようなケースでは任意売却ができない可能性があるため注意が必要です。
- 住宅ローンを滞納していない場合
- 競売まで時間がない場合
- 売却価格がローン残高を大幅に下回る場合
- 債権者(金融機関)との関係が悪化している場合
- 債務者や保証人、相続人の同意が得られない場合
- 所有者の本人確認ができない場合
- 国や自治体に家を差し押さえられている場合
- 不動産をめぐる法的紛争がある場合
- 物件に問題がある場合
- 売却活動が十分でない場合
住宅ローンを滞納していない場合
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に検討される手段です。
そのため、住宅ローンを滞納していることが利用の前提条件となります。
一般的には3ヵ月〜6ヵ月ほど住宅ローンの滞納が続くと、競売を避けるために金融機関が任意売却に応じるケースが多くなります。
競売まで時間がない場合
任意売却が成立するまでは、通常3ヵ月〜6ヵ月かかります。
競売の中止を申請できるのは開札日の2日前までです。それまでに任意売却が成立しないと、強制的に競売に移行します。
開札日は、競売開始決定通知が届いた4ヵ月〜5ヵ月後に設定されるのが一般的なため、それよりも早く動き始めることが重要です。詳しくは、「7.1 早めに相談・準備を進める」で後述します。
売却価格がローン残高を大幅に下回る場合
任意売却するには、債権者(金融機関)の承諾が必要です。
しかし、不動産の市場価値がローン残高を大幅に下回るなど、資金回収が困難と判断された場合、債権者(金融機関)の同意を得られないことがあります。
債権者(金融機関)との関係が悪化している場合
任意売却の手続きには、債権者(金融機関)との連絡・交渉が不可欠です。
そのため債権者(金融機関)と住宅ローンの返済をめぐり、暴言や喧嘩などのトラブルがあった場合、「協力関係を築くのは困難」と判断され、任意売却の同意を得られない可能性があります。
債務者や保証人、相続人の同意が得られない場合
任意売却には、債務者本人や共有名義人、保証人や連帯保証人、連帯債務者など、不動産や債務に関係する全員の許可が必要です。一人でも同意が得られなければ、任意売却の手続きを進めることはできません。
また、対象の不動産が相続財産にあたる場合は、故人名義のままでは不動産を売却できません。遺産分割協議で、相続人全員の同意を得たうえで、相続登記や売却の手続きをおこなう必要があります。
所有者の本人確認ができない場合
任意売却や売買契約の手続きは、不動産の所有者がおこないます。そのため所有者が借金を逃れるために所在不明になっている、病気で契約に立ち合えないなどの場合、基本的に任意売却はできません。
また、認知症で判断能力を喪失しているなど、本人の意思確認ができない場合も同様です。
ただし、病気の場合は司法書士が所有者のもとに赴いて本人確認をする、認知症の場合は後見人を立てるなどの方法で、対応可能な場合もあります。このようなケースでは一度、債権者(金融機関)や弁護士・司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
国や自治体に家を差し押さえられている場合
多額の税金や保険料を滞納し、国や自治体に住宅を差し押さえられている場合、任意売却はできません。まずは税金や保険料を支払い、差し押さえを解除する必要があります。
例外として、売却代金を税金の納付にあてることを条件に、役所が任意売却を認めるケースもあります。しかし、その結果住宅ローンの回収分が大きく減ると、今度は「債権回収が見込めない」「配分案に同意できない」などの理由で、債権者(金融機関)に任意売却を拒否される可能性があります。
不動産をめぐる法的紛争がある場合
対象の不動産に関して、法的紛争や訴訟が進行中の場合も任意売却は困難です。
例えば、所有権で争っている場合、誰の同意を得るべきか明確でないため、売却手続きを進めることができません。
物件に問題がある場合
複数箇所から雨漏りしている、違法な増改築をおこなっているなど、建築物に重大な欠陥がある場合も、任意売却が困難になります。
購入希望者が現れる可能性が低いため、債権者(金融機関)の同意を得られない、仮に同意を得られたとしても買い主が見つからず、最終的に競売になるなどのリスクがあります。
売却活動が十分でない場合
任意売却を成功させるには、購入希望者を見つけるための売却活動が欠かせません。
債権者(金融機関)との交渉次第ですが、通常、任意売却が認められる期間は3ヵ月〜6ヵ月程度です。この期間内に買い主が見つからなかった場合、強制的に競売に移行します。
また、広告を出さない、内覧対応しない、債権者(金融機関)への活動報告を怠るなど、適切な売却活動がおこなわれない場合は「売却の意志がない」と判断され、任意売却の期間内でも競売に移行する可能性があります。
任意売却できないとどうなる?
債権者(金融機関)をはじめとする不動産の権利関係者から任意売却の同意を得られなかった、または売却活動をしても買い主が見つからなかったなどの場合は、強制的に競売になります。
そして、自宅の売却後も多額の債務が残った場合、自己破産などさらに厳しい選択肢を迫られる可能性があります。
競売にかけられる
住宅ローンの滞納が6ヵ月程度続くと、期限の利益(分割払いの権利)を喪失し、残債の一括返済を求められます。
しかし、多くの場合、住宅ローンを滞納している状況下で残債の一括返済に応じるのは困難です。
一括返済ができない場合、債権者(金融機関)は、裁判所に競売の申し立てをおこない、担保不動産を強制的に売却することで、債権回収を図ります。
それでも残債が払えない場合は自己破産のリスクも
競売での落札金額は市場価格の7割程度といわれています。そのため競売で得られる売却代金だけでは、住宅ローンの残債を一括返済できないケースがほとんどです。
競売後も多額の債務が残り、返済が困難な場合は、自己破産などの債務整理が必要となります。
自己破産とは、裁判所の許可を得て借金の返済を免除してもらう手続きです。免責が認められれば借金は帳消しとなりますが、保有財産は原則として換金・処分され、債権者への返済にあてられます。
任意売却できない・売れないを防ぐための対処法
上記のとおり、何らかの事情で任意売却が叶わない場合は、競売や自己破産などの厳しい対応を迫られることになります。
任意売却できない・売れないなどの事態を防ぐには、事前に以下のポイントを押さえておくことが重要です。
- 早めに相談・準備を進める
- 売却活動に力を入れる
- サポートが手厚い不動産会社を選ぶ
早めに相談・準備を進める
任意売却は必要な手続きが多く、債権者(金融機関)との交渉から取引成立まで約1年かかることも珍しくありません。
各工程にかかる期間の目安は以下のとおりです。
| 債権者から任意売却の同意を得る(期限の利益の喪失) | 住宅ローン滞納後3ヵ月〜6ヵ月 |
| 債権者と任意売却に関する条件の交渉 | 約1ヵ月 |
| 売却活動開始〜完了 | 約3ヵ月〜6ヵ月 |
また、競売の中止を申請できるのは開札日の2日前まで、開札日は競売開始決定通知が届いた4ヵ月〜5ヵ月後に設定されるのが一般的です。
上記を鑑みると、任意売却を検討している場合は、住宅ローンの返済が難しくなった段階で動き始めるのがおすすめです。共同名義人や連帯保証人などの権利関係者と話し合い、任意売却の実績がある不動産会社や弁護士などに相談しましょう。
売却活動に力を入れる
どれだけ熱心に売却活動に取り組めるかは、任意売却の成否を左右する重要なポイントです。
掃除や整理整頓、簡単な修繕などをおこなうだけでも物件の第一印象がよくなり、購入希望者の関心を集めやすくなります。
さらに内覧対応では、購入希望者に「ここに住みたい」と思ってもらえるよう、誠実で丁寧な受け答えを心がけましょう。あらかじめ物件のアピールポイントを整理しておく、購入希望者からの質問に備えるなどの事前準備も重要です。
このように売却活動に注力することで、購入希望者が増え、買い手が見つかりやすくなります。
サポートが手厚い不動産会社を選ぶ
売却活動では、販売戦略や広告の打ち出し方によっても反響が大きく変わります。
そのため、仲介を依頼する不動産会社の営業力や集客力も重要なポイントです。
また、任意売却に慣れている不動産選びであれば、債権者(金融機関)とのやり取りや、必要書類の準備、スケジュール調整などもサポートしてくれる場合があります。
売却後、今の家に住み続けられるリースバックという選択肢も
任意売却先として、リースバックサービスを提供している不動産会社を利用すれば、売却後も今の家に住み続けられます。
「リースバックプラス+」は、一建設が提供するリースバックサービスです。お客様のライフスタイルに合わせてずっと安心して住める「標準プラン」と期間を定めてお得に住める「定期プラン」の2プランを用意。引っ越し費用がかからないだけでなく、仲介手数料や敷金、礼金などの諸経費も不要なため、暮らしに関わる経済的な負担を軽減できます。
実際に利用者の約40%以上の方が、住宅ローンの返済のためにこのサービスを活用されていますので、興味がある方はぜひ選択肢の一つとしてご検討ください。
まとめ
任意売却は、競売よりも高額での売却が期待できることから、基本的には債務者と債権者(金融機関)双方にメリットのある選択肢です。
ただし、任意売却するには主に以下の条件を満たす必要があります。
- 債権者(金融機関)の同意
- 不動産の権利関係者(名義人や連帯保証人、相続人)などの同意
- 所有者の本人確認
その他、対象の不動産を国や自治体に差し押さえられている、法的紛争や訴訟が進行中であるなどのケースは、任意売却できないため注意が必要です。
任意売却を検討している際は、住宅ローンの返済が困難になった時点で、任意売却に詳しい不動産会社や弁護士などに相談しましょう。
また、「リースバックプラス+」を利用すれば、自宅の売却後も賃貸物件として、今の家に住み続けられます。住宅ローンが残っている場合でも原則利用可能で、実際に利用者のうち約40%の方が、住宅ローンの完済目的となっています。
「住み慣れた今の家を離れたくない」「住宅ローンの滞納で悩んでいる」方はぜひお気軽にご相談ください。