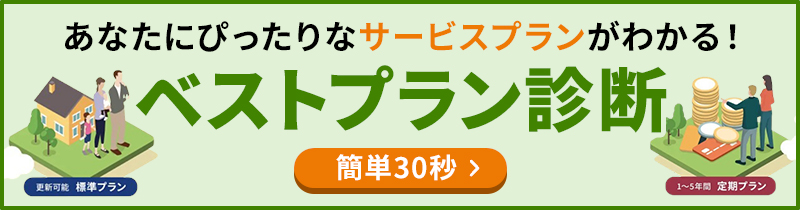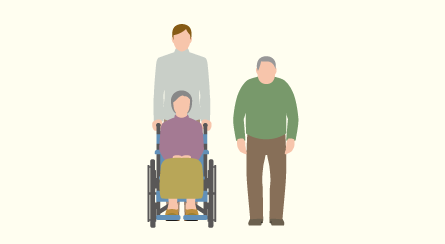親が所有するマンションを相続し、扱いに困っている方は意外と多くいらっしゃいます。管理や税金の問題があり、「売却して手放してしまいたい」と考えることもあるでしょう。
この記事では、親から相続したマンションを売却する方法について、一般的な手続きの流れや必要書類、名義変更(相続登記)の方法などを詳しく解説します。
INDEX
親のマンションを売却する方法
一般的に、親が所有するマンションを子どもが売却する方法としては「マンションを相続する(マンションの名義を変更する)」方法が知られています。
しかし実際は、「親の代理人になる」「成年後見人制度を利用する」という方法でも親のマンションを売却できます。
そこで、まずは親のマンションを売却する上記3つの方法について、それぞれご紹介します。
相続して名義を変更する
親が亡くなってマンションの所有権を相続した場合などは、マンションの売却前に、まず、マンションの名義を亡くなった親からご自身(子ども)へと変更する手続きが必要です。この名義変更の手続きを「相続登記」と呼びます。
相続登記は管轄の法務局でおこないます。相続登記をしてマンションの所有権がご自身に移った後、不動産会社を通じて売却活動を進めます。
この記事では、この「相続したマンションを売却する方法」について、手続きの流れや必要な書類などを後ほど詳しく解説します。
親の代理人になる
親が存命でありながら体調不良のような何らかの事情でマンション売却の手続きが難しい場合は、代理人として子どもが親のマンションを売却することができます。
あくまで親が所有権を持つマンションを代わりに売却する方法なので名義の変更はともなわず、相続登記の手続きも不要ですが、親(マンションの所有者)の代理人であることを示す「委任状」の作成が必要になります。
成年後見人制度を利用する
同じく親が存命でありながら、病気や認知症など何らかの理由で意思表示が難しい場合は、成年後見人制度を利用して子どもが親のマンションを売却することができます。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害、認知障害などによって、重要な判断を一人で下すことが不安な方を保護する制度です。家庭裁判所を通じて信頼できる成年後見人を定め、契約の締結や財産の管理など、さまざまな面での保護・支援を依頼します。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。
引用元:成年後見制度とは|厚生労働省
マンション売却においては成年後見人に選ばれた場合、成年被後見人(親本人)の意思や裁判所の許可を踏まえながら、親のマンションを売却します。売却を認められるには、それが親の利益になると判断されなければなりません。
成年後見人制度を利用する場合も相続登記は不要です。
相続した親のマンションを売却する時の一般的な流れ
ここからは、名義を変更した親のマンションを売却する方法について詳しく解説します。まずは、一般的な売却の流れを紹介します。
上記が相続した親のマンションを売却する時の一般的な流れです。相続登記の手続きがある以外は普通のマンション売却と大きな違いがないため、通常のマンション売却の方法も併せて参考にしてください。
[関連リンク]
マンション売却の流れ7ステップ!時間・費用・入金のタイミングも併せて解説
以下では各過程でおこなう手続きやポイントなどを解説します。
相続登記をする
親のマンションを相続して売却する場合、最初にマンションの名義を変更する相続登記の手続きをします。相続登記をしなければマンションの売却ができないため、迅速に完了させましょう。
相続登記の流れは以下のとおりです。
- 必要な書類を用意する
- 登記申請書を作成する
- 登記申請書を法務局へ提出する
- 登記完了証・登記識別情報通知書を受け取る
相続登記をするには、登記申請書をはじめとした必要な書類を、法務局に提出しなければなりません。法務局のホームページで申請書の様式をダウンロードできるので、それをA4の上質紙などに片面印刷し、各項目を記入しましょう。
用意した書類は相続するマンションの所在地を管轄する法務局の窓口へ直接持参するか、もしくは郵送で提出することも可能です。
最後に、登記所から交付される登記完了証と登記識別情報通知書を受け取って、相続登記の手続きは終了となります。こちらも窓口または郵送で受け取りができます。
なお2024年4月1日以降、不動産を相続した場合は、それを知った日から3年以内に相続登記をすることが不動産登記法によって義務化されています。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由がないにも関わらず相続登記の申請をしていなかった場合、10万円以下の過料が科されます。売却する場合もそうではない場合も、マンションを相続したら3年以内に相続登記の手続きを完了させましょう。
必要書類を準備をする
相続登記の手続きと並行して、マンションの売却に必要な書類の準備も進めましょう。入手に時間を要する書類もあるため、早めに動きはじめることをおすすめします。
マンションを売却する際に必要な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 入手方法 |
|---|---|
| 身分証明書 | 証明書の種類による。 |
| 住民票または戸籍附表 | 市区町村の窓口やコンビニエンスストア、郵送などで写しを取得可能。 |
| 印鑑証明書 | 市区町村の窓口やコンビニエンスストアで取得可能。 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 不動産の登記事項法務局に申請することで取得可能。 |
| 物件購入時の売買契約書 | 物件購入時に不動産会社から交付されている。紛失した場合、不動産会社に問い合わせることで再発行が可能。 |
| 物件購入時の重要事項説明書 | 物件購入時に不動産会社から交付されている。紛失した場合、不動産会社に問い合わせることでコピーを入手できる可能性がある。 |
| 登記済権利証または登記識別情報 | 物件購入時に法務局から発行されている。紛失した場合、再発行はできず別の手段で手続きを進める必要がある。 |
| 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | 固定資産税納税通知書は市区町村から毎年送付される。紛失した場合、再発行はできず、代わりに固定資産税納税通知書を市区町村の窓口または郵送で取得する。 |
| 物件購入時の間取り図および設備の仕様書 | マンションのパンフレットなどに記載あり。所持していない場合は不動産会社を介してマンションの管理会社に問い合わせることで取得可能。 |
| リフォーム履歴の確認資料 | 不動産会社を介してマンションの管理会社から取得可能。 |
| 建築確認済証および検査済証 | マンション購入時に入手。紛失した場合、再発行はできず、自治体で台帳記載事項証明書を代わりに取得する必要がある。 |
| マンションの管理規約または使用細則 | マンション購入時に入手。紛失した場合は不動産会社を介してマンションの管理会社に問い合わせることで取得可能。 |
| 耐震診断報告書およびアスベスト使用調査報告書 | 当該診断・調査が実施された場合、管理組合から入手。 |
| ローン残高証明書・返済償還表・抵当権抹消書類 | ローン残高証明書および返済償還表は銀行から送付される。抵当権抹消書類は登記簿謄本にて確認可能。 |
| 銀行通帳の控え | 振り込み先に指定する銀行口座の通帳またはキャッシュカードの銀行名、口座番号、氏名をコピーする。 |
マンション査定を不動産会社に依頼する
不動産会社に査定を依頼し、マンションがいくらで売れるか、目安を算出します。査定は適正な売り出し価格を設定したり、具体的な資金計画を立てたりするために重要です。
査定方法には以下の3種類があります。
匿名査定:Webサイト上でAIに目安の売却価格を算出してもらう方法
机上査定:Webサイト上で不動産会社に目安の売却価格を算出してもらう方法
訪問査定:不動産会社の担当者に物件を確認してもらい、目安の売却価格を算出してもらう方法
最も簡単かつ短時間で済むのが匿名査定、最も査定結果の精度が高いのが訪問査定です。おすすめは訪問査定ですが、時間の面で厳しい場合は匿名査定や机上査定を利用しましょう。
不動産会社と媒介契約を締結する
売却の仲介を依頼するため、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には以下の3種類があります。
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社と契約してマンションを売却する方法です。契約期間に決まりがなく、レインズへの登録義務もありません。売り主自身が直接買い主と売買契約を結ぶことも認められていて、最も自由度が高い契約方法です。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は、どちらも不動産会社を1社に絞り込んで契約を結びます。不動産会社から売り主への状況報告がおこなわれることと、レインズへの登録義務があること、契約期間が3ヵ月以内と定められていることも共通しています。
ただし報告の頻度や、レインズに登録するまでの期限には違いがあります。また、専任媒介契約は一般媒介契約と同様に売り主自身が直接買い主と売買契約を結べるのに対して、専属専任媒介契約は自分で取引ができません。
それぞれメリット・デメリットが異なるので、ご自身に合った契約方法を選びましょう。
マンション売却の流れ7ステップ!時間・費用・入金のタイミングも併せて解説
売却活動を開始する
不動産会社と媒介契約を締結したら売却活動を始めます。売却活動の内容は不動産サイトや住宅情報誌への掲載、新聞の折り込みチラシやポスティングなど多岐にわたります。しかしながら、基本的に売却活動は不動産会社がおこなってくれるため、任せておいて問題ありません。
売り主がおこなうことは、内覧の準備と当日の対応です。室内を清掃し、傷・欠陥などがあれば修繕を済ませておきます。修繕が難しい場合はトラブルを予防する観点から、購入希望者に対して事前に伝えておくことが望ましいです。
また内覧の際、購入希望者からの質問に的確に答えられるよう備えておくことも大切です。同時に、物件の魅力をアピールするための情報を整理しておきましょう。
このように、内覧時に向けてしっかりと準備をしておくことで、購入希望者からの印象がアップし、物件を購入してもらえる可能性が高くなります。
買い主と売買契約を締結する
内覧を終えてマンションの購入者が決まったら、契約書の読み合わせや重要事項の説明をし、買い主と売買契約を締結します。
また契約を結ぶタイミングで、売り主は買い主から手付金を受け取り、不動産会社に仲介手数料の半金を支払うのが一般的です。手付金は売却金額の5〜10%、仲介手数料は売却金額の3~5%程度が相場とされています。
売却代金を受け取る
後日、買い主による住宅ローンの融資が実行されるタイミングで、手付金を差し引いた売却代金が支払われます。残金支払いと引渡し時は、買い主と売り主、不動産会社の担当者が買い主が融資を受ける金融機関に集合するのが一般的です。
同時に売り主は、所有権移転登記や抵当権設定登記の手続きを、このタイミングで並行しておこなう方が多いです。
また、買い主から売却代金が支払われたら、売り主は不動産会社への仲介手数料の残り半金を支払います。
マンションを引き渡す
売却代金が支払われ、すべての手続きを終えたら、マンションの鍵や書類などを買い主に引渡します。
なお住宅ローンを完済していない場合、残りの精算を終えて抵当権を抹消する抵当権抹消登記が必要になりますが、抵当権抹消登記が済んでいないとマンションを売却できないため注意が必要です。
相続登記の前に完了させておくこと
前述のとおり、親のマンションを売却するためには、はじめに相続登記の手続きが必要です。ここでは相続登記の手続きをする前に確認しておくことや、話し合っておくことを解説します。
遺言書の確認
故人が生前に遺言書を作成していたかを調べ、作成していた場合は相続人に指定されている人を確認します。
遺言書の有無を調べるときは、まず自宅を探してみましょう。故人が自筆したものが保管されている場合があります。自宅にない場合、法務局に保管されている可能性が考えられるので確認してみてください。
この他に、故人が公正証書遺言を作成しているケースもあります。公正証書遺言とは、遺言者が2人以上の証人の立会いのもと口頭で遺言内容を伝え、それを公証人が文章としてまとめたものです。
公正証書遺言の有無は公証役場で検索できるので、法務局に預けられていなかった場合は確認してみましょう。
法定相続人の確認
遺言書が見つからなかった場合や、遺言書に相続財産の承継方法が記載されていなかった場合、すべての相続人で話し合いをおこない、分配を決めることになります。
分配を決める前段階の準備として、戸籍謄本を取得し、血縁関係を明らかにして法定相続人を確認しておくことが必要です。
相続財産の確認
マンションを含めた相続財産の調査もしておきましょう。相続財産の分配をおこなうには、どのような相続財産がどれだけあるかを確定させておかなければなりません。
また、相続財産のなかには借金やローンなど、相続人にとってマイナスになるものもあります。相続放棄の判断をするためにも相続財産の確かな内容を把握しておくことが望ましいです。
相続する意思の確認
前述のとおり相続財産のなかには、相続人にとって負担になるものもあります。その点を踏まえて相続を承認するか、放棄するかを判断し、決定します。
なお、万が一相続を放棄する場合は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
遺産分割協議
法定相続人や相続財産などが明確になったら、相続人全員で話し合い、遺産の分配を決める「遺産分割協議」をおこないます。
この協議の結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続登記の手続きをする際に印鑑証明書と併せて提出します。
複数人でマンションを相続するには

遺産の相続人が一人ではなく、兄弟や姉妹などを含めた複数人に及ぶ場合、マンションの承継方法がわからないという方は多いと思います。
以下では複数人でマンションを相続する4つの方法を解説します。
現物分割
マンションを含む相続財産の現物を、相続人全員でそのまま分割する方法です。
例えば二人兄弟の場合、マンションを兄が、現金を弟が相続するという形になります。
現物分割はシンプルでわかりやすい方法ですが、公平に分割するのが困難というデメリットがあります。
換価分割
マンションを売却して得た売却代金を分割する方法です。
公平な分割がしやすく相続人の間でトラブルに発展しにくい方法ですが、マンションの売却には時間がかかるため、金銭を得られるまでにも月日を要します。
また、売却の手間や費用の負担を誰がどのように負うかという話し合いは必要です。
代償分割
一人がマンションを相続し、他の相続人に対して相応の現金を支払う方法です。
マンションをそのまま残しておきたいときに向いている方法であり、現物分割に比べて公平に遺産を分けやすいというメリットがあります。
ただしマンションを相続する方は金銭的な負担が大きくなるので、充分な財力がなければ代償分割によるマンションの相続は成立しません。
また、マンションの相続人が他の相続人に対して代償金を支払わなかった場合も遺産分割協議の結果を無効化することができないことから、信頼関係がないとトラブルになる可能性があります。
共有分割
相続人全員が共同名義でマンションを相続する方法です。
売却する際に全員の同意が必要になる、税金や維持費の負担割合で揉めるなど、何かとトラブルに発展しやすいため、一般的には推奨されません。
相続した親のマンションを売却せず残しておくデメリット
マンションを相続した方のなかには、「今すぐに住む予定はないけれど、将来を見越して手放すのも不安」という方もいらっしゃいます。しかし、住む予定がないにも関わらず親のマンションを残しておくことはおすすめできません。理由は以下のとおりです。
年数が進むと売却しづらくなる
マンションは年数が進むにつれて老朽化し、資産価値が下がります。資産価値が下がると売り手が現れにくくなり、条件を下げるなどして納得のいく金額で取引できなくなります。徐々に売却しづらくなるため、早いうちに売り切っておくのが賢明といえるでしょう。
税金や維持費の負担が大きい
マンションを所有していると、固定資産税・都市計画税が1年ごとに課税されます。加えて建物や部屋のメンテナンスなどの維持費もかかり、金銭面の負担が大きいため、使い道がない場合はすぐに売却することが推奨されます。
親のマンションを売却する際にも一時的に譲渡所得税や印紙税、
登録免許税などの費用がかかりますが、この先、継続的に固定資産税・都市計画税、維持費を支払い続けることを考えると、費用負担は遥かに少なく抑えられます。
迅速にマンション売却の手続きを進めて負担を軽減しましょう
親から相続したマンションを売却するには、まずマンションの名義を変更する相続登記の手続きが必要です。しかしその後の流れは一般的なマンションの売却時と大きな違いはありません。
まずは各種書類の用意や登記申請書の作成を経て、相続登記の手続きを忘れずに済ませましょう。その後は一般的なマンション売却の流れを参考に、不動産会社と協力して売却活動を進めます。
「マンションを相続したけどどう扱えばいいか悩んでいる」
「相続の問題があって気軽に売却できない」
そんなお悩みがある方は一建設が提供する「リースバックプラス+」のサービスがおすすめです。相続したマンションに住み続けながら現金化できるリースバックは、ライフスタイルを変えずにまとまった資金を確保できます。マンションの維持管理や売却処分の負担が減り、また複数の相続人がいる場合も財産の分割がスムーズです。
「リースバックプラス+」はライフスタイルに応じて選べる2プラン3タイプの契約をご用意しています。長く自宅に住み続けたい方に向いている標準プランと、期間を定めることでお得になる定期プラン、ご自身の目的に合ったプランをお選びください。
リースバックはマンションでも可能!マンション所有者の方向けの特設ページはこちら ›
[関連リンク]