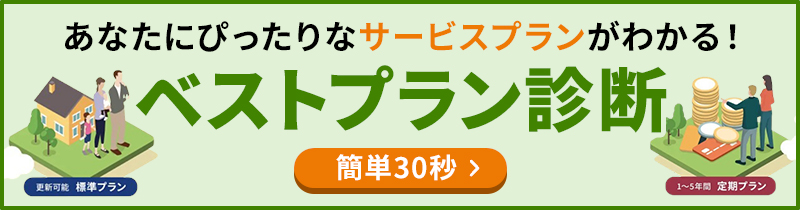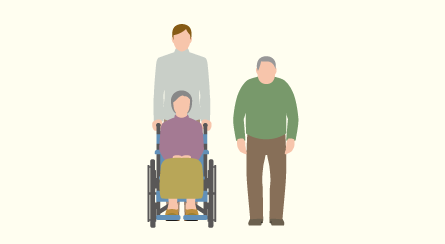「転勤が決まった」「子どもが成長して手狭になった」「親からマンションを相続した」など、マンションを売却する理由は人それぞれです。しかし、多くの方に共通するのが、マンション売却にはどれくらいの期間がかかるのかわからないという不安です。
マンションの売却は、そう頻繁に経験するものではありません。そのため、何から始めればよいのかわからず、思うように進まないこともあります。
この記事では、マンション売却にかかる平均的な期間や、売却が長引く原因、スムーズに売却を進めるためのコツ、売却の流れまでを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
INDEX
マンション売却にかかる平均期間(首都圏)
マンション売却にかかる期間は、物件の状態や立地、売却価格の設定、不動産会社の対応など、さまざまな要因によって変動します。首都圏における中古マンションの平均成約日数をみてみると、以下のような推移が見られます。
| 年度 | 登録から成約に至る日数 中古マンション | 前年比(%) |
|---|---|---|
| 2020年 | 88.3日 | +8.2% |
| 2021年 | 74.7日 | -15.4% |
| 2022年 | 71.4日 | +4.5% |
| 2023年 | 80.1日 | +12.2% |
| 2024年 | 85.3日 | +6.6 |
参考:公益財団法人東日本不動産流通機構|首都圏不動産流通市場の動向(2024年)
2020年には新型コロナウイルスの影響で不動産市場全体が停滞し、売却までに要する期間が長引きました。2023年には再び80日を超え、前年比+12.2%とやや長期化の傾向が見られます。
これは、物件供給の減少や価格の上昇により、買い主側の選別意識が強まっていることが背景にあると考えられます。
また、売却活動は売り出してから買い手が見つかるまでだけでなく、売却前の準備期間や売買契約〜引渡し期間も含めて考える必要があるでしょう。あくまでも目安ですが、これらを考慮すると、全体で4〜6ヵ月が一般的な売却期間といえます。
売却期間が長引くケース
マンション売却において、思ったより時間がかかると感じるケースには、いくつかの共通点があります。ここでは、売却期間が長引きやすい主な要因を具体的にご紹介します。
売り出し価格が相場より高い
売却期間が長引く典型的な原因が価格設定のミスです。売り主の希望価格が市場相場とかけ離れている場合、購入希望者からの関心が集まりにくく、内覧すら入らない状況になりがちです。
基本的には、信頼できる不動産会社に査定を依頼すれば、成約事例や相場データをもとに適正な売り出し価格を提案してもらえます。ただし、以下のような物件では、結果的に相場より高めの価格でスタートしてしまうケースがあるため注意が必要です。
- 築浅マンション
- リフォーム済みのマンション
築浅やリフォーム済み=売れやすいと考えてしまいがちですが、価格設定を誤ると売却活動が長期化する要因になりうるのです。内覧の反応が鈍い場合や問い合わせが少ないと感じたら、不動産会社と価格戦略を見直すタイミングかもしれません。
立地条件や周辺環境が悪い
駅からの距離が遠い、商業施設や教育環境が整っていない、騒音や治安に不安があるといった要素も、売却期間に影響します。特にファミリー層をターゲットにした物件では、学区や公園の有無なども重視されやすいです。
さらに、競合物件が多いエリアでは、立地条件が相対的に見劣りすると価格を下げない限り買い手がつかないこともあります。
築年数が古い
マンションの築年数が古いと、それだけで敬遠されるケースがあります。特に築30年以上になると、外観や共用部の老朽化が目立つだけでなく、購入後の維持費や修繕リスクを懸念されやすくなります。
なかでも注意が必要なのが、1981年(昭和56年)6月1日以前に建てられたマンションです。この時期以前の物件は、いわゆる旧耐震基準で設計されており、現在の新耐震基準に比べて地震に対する構造的な耐久性が劣るとされています。
こうした築古物件を売却する際は、次のような対策がおすすめです。
- 管理組合による修繕履歴や点検記録を整理しておく
- 耐震診断を受けて現状の耐震性を数値で示す
- リフォームの提案や価格調整の柔軟さを伝える
築年数の古さ自体は変えられませんが、管理状態や将来の安心感をアピールすることで、買い手の不安を和らげることが可能です。
物件の面積が広い
面積が広い物件はその分、価格も高額になりやすく、購入層が限定されます。マンションで4LDKや5LDKのような100㎡超の間取りは、そもそも買い手が少なく、売却期間が長引くかもしれません。
広過ぎる物件は、管理コストや家具レイアウトなどの観点から敬遠されることもあります。
管理費と修繕積立金が高い
購入後のランニングコストが高すぎると、買い手の購入意欲に影響を与えます。特に築年数が経っているにもかかわらず、月額3万円近い管理費・修繕積立金がかかる物件は、敬遠されやすい傾向にあります。
首都圏の1戸あたりの管理費・修繕積立金の相場は、以下のとおりです。
- 管理費:13,847円
- 修繕積立金:13,177円
毎月かかる費用によって売却の難易度が上がることがあります。
参考:REINS 首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金(2024年度)
マンション売却をスムーズに進めるコツ

マンションを早く、そして納得のいく条件で売却するには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは、売却活動をスムーズに進めるための具体的なコツをまとめました。
売りたい価格ではなく売れる価格で売り出す
多くの方が「できるだけ高く売りたい」と考えるのは当然のことです。しかし、買い手がつかないまま時間が経ってしまうと、最終的には値下げして売ることになり、結果として損をすることがあります。
スムーズな売却のためには、売れる価格を見極めることが重要です。周辺の成約事例や不動産ポータルサイトの相場情報やデータなどをもとに、現実的な価格で売り出すことで、内覧の数や成約スピードが大きく変わります。
不動産会社からの査定額は複数社で比較し、高すぎず・安すぎないバランスの取れた価格設定を意識しましょう。
需要が高まる繁忙期(2〜3月、9〜10月)を狙う
マンションの購入を検討する方が増え、不動産取引が活発化する時期に売却を開始すると、早期成約につながりやすくなります。特に以下の時期は引っ越しシーズンや転勤時期と重なるため、購入需要が高まります。
- 春(2月〜3月)は新生活に向けた住み替えニーズが高い
- 秋(9月〜10月)は年度内の入居や転勤に備えた動きが活発化
このようなタイミングで売り出すことで、競合物件が多くても注目を集めやすくなるため、戦略的な売却スケジュールの設定が成功の秘訣となります。
内覧の準備を徹底し「この家に住みたい」と思わせる
内覧時の印象によって、購入希望者の気持ちが大きく左右されます。部屋の整理整頓や掃除はもちろん、生活感を抑えたレイアウトや明るさの演出など、第一印象を良くする工夫が成約率につながります。
さらに、リノベーションやハウスクリーニングをおこなうことで、築年数の古い物件でも買い手側に手入れが行き届いているという印象を与えられるでしょう。
アピールポイントと弱点を整理しておく
眺望・日当たり・駅近・ペット可など、あなたのマンションに関するメリットを積極的にアピールしましょう。注意点としては、管理費が高い、築年数が古いといった問題要素も、隠さず説明できる準備をしておくことが大切です。
誠実な対応によって、買い手の信頼を得やすくなり、価格や引渡し時期の交渉もスムーズに進むでしょう。
信頼と実績のあるパートナーを選ぶ
売却の成否は、不動産会社選びで決まるといっても過言ではありません。パートナーの決め方は以下のとおりです。
- 中古マンション売却の実績が豊富か
- 売却地域の相場や動向に詳しいか
- 担当者が誠実で迅速な対応をしてくれるか
複数社に査定を依頼したうえで、説明がわかりやすく、戦略的な提案ができる会社を選ぶことがスムーズな売却への近道です。
買い主からの条件交渉には柔軟な姿勢で臨む
価格交渉や引渡し時期の調整に対して、売り主があまりにも固執してしまうと、せっかくのチャンスを逃すことになりかねません。
もちろんすべての条件を受ける必要はありませんが、価格は少し下げても良い、引渡しはすぐでもOKなど、ある程度の柔軟性を持って交渉に臨む姿勢が、早期成約につながることがあります。
ホームインスペクション(住宅診断)で信頼性を高める
最近では、売却する前に第三者によるホームインスペクション(建物診断)をおこなうケースが増えています。ホームインスペクションとは、建物の劣化状況や不具合の有無を専門家が調査・報告する業務のことです。
なお、国土交通省もホームインスペクションの活用を推奨しており、媒介契約をする際には実施の有無を明記する義務があります。診断結果を事前に提示しておくことで、内覧時の不安を払拭でき、トラブル防止につながるでしょう。
マンション売却の流れと売却期間中におこなうべき項目
マンションの売却は、ただ売り出して完了ではありません。売却の準備から契約・引渡しまで、段階ごとにやるべきことがしっかり分かれており、それぞれに時間がかかります。
ここでは、スムーズな売却を実現するために知っておきたい3つの期間と、各期間にやるべき手順をご紹介します。
準備期間は約1ヵ月|相場の把握とパートナー選び
売却活動を始める前の準備は、想像以上に多岐にわたります。ここでしっかり時間をかけることで、そのあとの売却がスムーズに進みやすくなります。
<ステップ①売却方針の決定>
住み替えを前提とするのか、売却後は賃貸に住むのかなど、実際のライフプランに沿って方向性を定めましょう。
<ステップ②不動産会社探しと査定依頼>
複数の会社に査定を依頼し、提案内容や対応を比較検討することで、信頼できるパートナーを見つけやすくなります。
<ステップ③媒介契約の選択>
専属専任媒介・専任媒介・一般媒介のいずれかを選択します。早期成約を目指すなら専属専任か専任媒介の契約がおすすめです。
<ステップ④必要書類の準備>
登記簿謄本や固定資産税納税通知書、管理規約など、売却に必要な書類を事前に揃えておくとスムーズです。
売却活動期間は約3ヵ月|内覧対応と購入申し込み
売却活動がスタートすると、購入希望者とのやり取りや内覧対応など、実務的な作業が一気に増えます。
<内覧対応(複数回)>
希望者からの内覧依頼には、できるだけ柔軟に対応することで、成約につながるチャンスが広がります。
<購入希望者との交渉>
価格だけでなく、引渡し時期や家具の残置なども交渉が入ることがあります。誠実・柔軟に対応しましょう。
<買付申込と住宅ローン事前審査>
購入希望者が現れたら、買付申込書を受け取ります。その後、買い主側は住宅ローンの事前審査に進みます。
契約・引渡し期間約1〜2ヵ月|売買契約と最終決済
売却が決まったら、売り主・買い主ともに正式な手続きを進めます。
<ステップ①売買契約の締結>
重要事項説明のあと、正式に契約書を取り交わし、手付金を受け取ります。
<ステップ②買い主のローン本審査・融資実行>
買い主側で住宅ローンの本審査が進み、承認後に金融機関から融資が実行されます。
<ステップ③引っ越し準備>
売り主・買い主双方が、引っ越しや生活インフラの手続きを進めます。
<ステップ④残代金の受領・所有権移転・鍵の引渡し>
最終的に残金が支払われ、司法書士立会いのもとで登記の手続きがおこなわれます。これにて正式な引渡しが完了です。
売却期間が長引いたときの具体的な対処法
「売り出してから数ヵ月経っても内覧が入らない」「問い合わせはあるが成約につながらない」。こうした状況が続くと、売り主としては不安や焦りが募るものです。しかし、売却までの期間が長くなる場合でも、適切な対処法を取ることで流れを変えられます。
価格見直し
最も効果が高いのが売り出し価格の再設定です。市場相場や競合物件の価格を再度調べ、買い手にとって割高に見えていないか冷静にチェックしましょう。
特に以下のようなサインが出ている場合は、価格の見直しを前向きに検討すべきタイミングです。
- 内覧希望者がほとんどいない
- 同じマンションや周辺の物件が先に売れている
- 不動産会社から「価格の反応が弱い」と指摘されている
価格を下げることで競合より優位に立てる場合もあり、結果的に早期売却・高評価での印象につながることがあります。
媒介方式の変更
売却活動を委任している不動産会社の動きが鈍いと感じたら、媒介契約の見直しが必要かもしれません。媒介契約の方法には、「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があります。
例えば、現在一般媒介契約を結んでいて複数の会社に依頼している場合でも、販売に本腰を入れてくれる1社に絞って専任媒介へ切り替えることで、積極的な販売活動が再開できます。
また、不動産会社そのものを変更する方法もあります。エリア特化型の会社や、中古のマンション販売に強い会社を選び直すことで、状況が一変するかもしれません。
PR方法の工夫で競合との差別化を図る
近年では、ただポータルサイトに物件情報を掲載するだけでは、多数の物件に埋もれてしまいます。オンラインでの魅せ方や情報発信の工夫が、売却期間の短縮につながるケースも増えています。
例えば以下のような施策がおすすめです。
- SNSでの広告配信(Instagram・Facebookなど)
- 物件紹介動画やドローン撮影の導入
- 360度パノラマ内覧(バーチャルツアー)の利用
- ライフスタイルを訴求したストーリー型コンテンツの掲載
こうしたPR方法は、ファミリー層や若年層に対して物件の魅力をよりダイレクトに伝える手段となり、他の物件との差別化につながります。
期間を気にせず売却できる選択肢
「なるべく早く現金化したい」「引っ越し時期が迫っている」「失敗したくない」といった不安がある場合は、従来の売却方法にこだわらず、柔軟な選択肢を検討することも大切です。ここでは、売却期間に縛られにくい代表的な2つの方法をご紹介します。
選択肢①住み続けながら売却できる「リースバック」
リースバックとは、マンションを不動産会社などに売却したあと、そのまま賃貸借契約を結んで同じ物件に住み続けられる仕組みです。
<こんな方におすすめ>
- 老後資金や急な支出に備えて現金化したい
- 引っ越しせずに住環境を維持したい
- 売却後の住まい探しに余裕を持ちたい
リースバックは通常、1週間〜1ヵ月程度で現金化が可能で、売却と同時に住み慣れた家を手放す必要がない点が魅力です。特に高齢者や相続対策を考える方にとって、安心できる選択肢となり得ます。
ただし、賃料設定や再売却制限などの条件は業者によって異なるため、契約内容の確認と比較検討が不可欠です。
なお、一建設では簡単な入力で査定額がわかる「お試し査定フォーム」をご提供しています。お気軽にご利用ください。
選択肢②最短数日で現金化できる「不動産買い取り」
不動産買い取りは、仲介を介さずに不動産会社が直接買い主となる売却方法です。内覧対応や成約交渉の必要がないため、とにかく早く現金化したい方に向いています。
<メリット>
- 最短で数日〜1ヵ月以内に現金化可能
- 仲介手数料がかからない
- 内覧や売却活動が不要
- 住宅ローン残債があっても対応可能(会社によって異なる)
- 契約不適合責任が免除されるケースが多い
一方で、デメリットもあります。売却価格が市場価格の70〜80%程度になる傾向があり、通常の仲介売却より価格が下がる点には注意が必要です。そのため、価格よりスピードや確実性を重視したい方におすすめです。
マンション売却期間に関するよくある質問
マンション売却を検討するなかで、不安を感じる方は多いです。ここでは、3つのよくある質問をまとめました。
築年数が古いマンションでも期間内に売れますか?
築年数が古くても、適正価格で販売すれば期間内の売却は十分に可能です。売却成功のカギは管理状態の良さと情報の開示です。具体的な対策は以下のとおりです。
- 過去の売却事例と照らして価格を設定する
- 管理状態や修繕履歴を開示する
- リフォーム提案や価格交渉の余地を明示する
築古=売れない、というわけではありません。事前知識と戦略次第で売却できる可能性はあります。
住宅ローンが残っていても売却は可能ですか?
住宅ローンが残っていても売却は可能です。ただし、売却後にはローン残債を完済する必要があります。
売却価格がローン残高を上回っている場合は、売却益からローンを完済し、差額を受け取るという流れです。一方、ローンの残債が売却価格を超えるオーバーローンでも、自己資金や新たなローン(住み替えローンなど)を利用することで対応できるケースがあります。
また、忘れてはならないのが抵当権の抹消です。抵当権とは、住宅ローンの担保として設定されている権利のことで、売却時には必ず抹消手続きをおこなう必要があります。
詳しい手続きや費用を知りたい方は以下の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。
>>住宅ローンの完済後に抵当権の抹消を行う方法。手続きの流れや費用を解説
所有期間が5年の不動産を売却したら税金はいくらですか?
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その金額に応じて譲渡所得税が発生します。税率は、不動産の所有期間が5年以下か、5年を超えているかによって大きく異なる点に注意が必要です。
<所有期間が5年以下(短期譲渡所得)のケース>
売却した年の1月1日時点で5年未満の所有である場合、短期譲渡所得として扱われます。この場合の税率は、所得税+住民税+復興特別所得税を合わせておよそ39.63%と高めに設定されています。
<所有期間が5年超(長期譲渡所得)のケース>
5年を超えて所有していた場合は、長期譲渡所得に区分され、税率は約20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)となります。
例えば、マンション売却によって1,000万円の利益が出たときに、短期なら約396万円、長期なら約203万円が課税額の目安となります(※特別控除を考慮しない単純計算)。
税金の負担を抑えたい場合は、5年を超えてからの売却を検討することも一つの選択肢です。売却のタイミング次第で手取り額が大きく変わるため、前もって税理士や不動産会社への相談をおすすめします。
まとめ:計画的な準備でスムーズなマンション売却を実現しよう
マンションはなかなか売る機会のない資産だからこそ、慎重に進めたいものです。売却期間は平均4〜6ヵ月ですが、価格設定や不動産会社選びによって短くも長くもなります。
「いつ動くべきか、どう売るべきか」と迷ったら、まずは無料査定サービスで相場を知るところから始めましょう。住宅ローンが残っていても売却は可能ですし、築浅物件や人気エリアの住宅ならチャンスも広がります。
また、売却後も住み続けられるリースバックが可能な不動産会社を探すのもおすすめです。
たとえ新築マンションでなくても、管理状態や住環境の魅力を正しく伝えれば悪い印象にはなりません。信頼できるパートナーと、納得のいく売却活動をおこないましょう。
一建設株式会社の「リースバックプラス+」では、マンション売却から住み替えのご相談まで、無料でサポートします。気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。