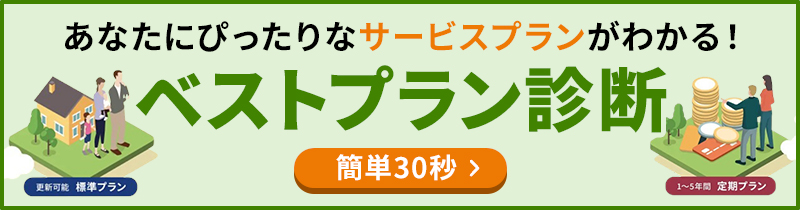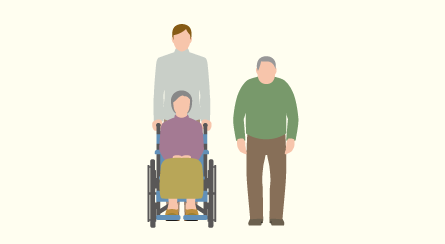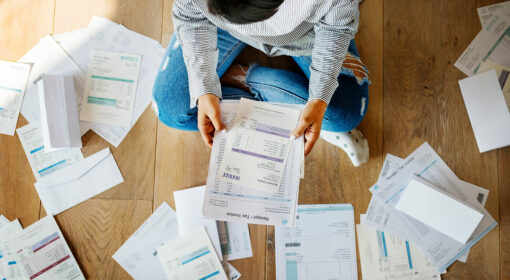住宅ローン返済や老後の資金確保、相続対策など、家を手放さずにまとまった資金を得られる方法として注目されているのが「リースバック」です。しかし、仕組みや相場、相談先を誤ると不利な条件になってしまうこともあります。
この記事では、リースバックの基本から、相談先の選び方、契約の流れ、相場、よくあるトラブルまで詳しく解説します。さらに、一建設の「リースバックプラス+」についてもご紹介します。
INDEX
リースバックとは

リースバックとは、家を売却して新たな所有者と賃貸借契約を結び、その後は家賃を払いながら住み続ける方法のことを指します。
例えば、住宅ローンの返済に行き詰まった場合でも、自宅を売却してローンを完済しつつ、賃貸という形で同じ家に住み続けることが可能になります。
売却代金を一括で受け取れるため、急な資金ニーズにも対応可能です。生活環境を変えずに資金調達ができる点は、大きな魅力といえるでしょう。
また、一般的な不動産売却と異なり、新たな住居を探す手間や引っ越し費用もかからないため、高齢者や子供がいる家庭にも支持されています。契約内容によっては、将来的に自宅を買い戻すことも視野に入れられます。
[関連リンク]
リースバックとは?仕組みやメリット・デメリット、トラブルの対処法をわかりやすく解説
リースバックの主な目的
売却後も同じ家に住み続けられるリースバックですが、どのような目的で利用されるのでしょうか。
ここでは、リースバックの主な利用用途を紹介します。
住宅ローンの返済が難しいため負担をなくしたい
住宅ローンの返済が難しくなり、月々の支払いに悩みを抱えている方にとって、リースバックは現実的な選択肢となり得ます。
リースバックでは売却後に家賃が発生しますが、住宅ローンの返済額と比べると家賃の方が安くなるケースが多く、家計への負担を軽減できます。
また、住み慣れた自宅にそのまま住み続けることができ、手続きも登記上の名義変更が中心となるため、近隣に売却を知られる心配もほとんどありません。さらに、ローンの延滞による信用情報の悪化や督促からも解放されることで、精神的な負担も軽くなるというメリットがあります。
短期間でまとまった資金が欲しい
例えば、急な入院による医療費や子ども・孫の進学、介護費用、事業資金など、まとまった資金が急ぎで必要になるケースでもリースバックはとても有効です。
リースバックでは、一般的な不動産売却とは異なり、リースバック業者が直接物件を買い取るため、買い手を探す手間も省けます。そのため、早ければ数週間〜1ヵ月程度で売却が成立することも。
さらに、売却後に同じ家に住み続けられるのはリースバックならではの魅力であり、転居が不要な点や周囲に売却を知られにくい点も、多くの方にとって安心材料となっています。
住み替えをしたい
住み替えをする場合、一般的な不動産売却では売却活動と並行して転居先を探す必要があります。
退去日と入居日のタイミングが合わなければ、新居に入居するまでの間の仮住まい探しと引っ越しも追加でおこなわなければなりません。
また引っ越しにともない、転職や子どもの転園・転校手続きが同時に発生する場合もあり、売却と住み替えを同じタイミングでおこなうのはとても慌ただしくなります。
リースバックでは、売却後も同じ家に住み続けながらゆっくり転居先を手配できます。引っ越しにともなう手続きも、余裕を持って対応できるでしょう。
相続対策をしたい
将来の相続対策として、リースバックを選択される方もいます。
一つの不動産を複数人で相続するのは難しく、誰が住むのか、どのように分けるのかといった点で親族間のトラブルにつながる恐れがあります。
リースバックによって自宅などの不動産を売却・現金化しておくことで、相続人間での分割がしやすくなり、相続税の納税資金として活用できるというメリットもあります。
さらに、生前にリースバックを利用することで、家を手放さずに資金化しながら生活を安定させることができ、残される家族の負担軽減にもつながります。
リースバックの相談はどこにする?
「リースバックに興味があるものの、まずはどこに相談したら良いかわからない」方もいるのではないでしょうか。
リースバックは、専門業者に相談することをおすすめします。地域の不動産会社や大手の賃貸不動産会社などでは、リースバックの取り扱いがない、またはとても限られていることが多いためです。
一方で、リースバックを専門に取り扱っている不動産会社であれば、制度に対する理解や対応経験が豊富であり、スムーズに手続きが進められます。売却後も住み続けたいという希望や、将来的な買い戻しに関する相談にも柔軟に対応してくれる可能性が高いため、こうした専門業者に相談や手続きを依頼するのが安心です。
なお、万が一リースバックの契約でトラブルがあった場合は、お住まいの地域の消費生活センター等へご相談ください。
リースバックのトラブルを防ぐには、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
次にリースバック業者の選び方を紹介します。
リースバックの相談をする業者選定時の確認事項
業者によって契約条件やサポート体制が異なります。ここでは、業者選びで失敗しないためのポイントを紹介します。
リースバックの実績
リースバック事業の運営年数や年間の契約実績、そして実際に利用した方からの口コミなどを総合的にチェックすることで、その業者に相談しても問題がないかを判断する材料になります。
特に5年以上の運営歴と安定した実績数がある企業は信頼性が高く、ノウハウやトラブル対応の経験も豊富と考えられます。
過去の取り扱い物件や地域
検討している業者がこれまで取り扱ってきた物件に戸建てが多いか、あるいはマンションが多いか、自身の物件に近い種別での対応実績があるかを確認することが大切です。また、その業者が自分の物件がある地域に強いかどうかも見極めましょう。
こうした情報をチェックすることで、各業者が得意とする分野に沿った依頼ができ、より適正な価格での取引が期待できます。
買い戻しの条件
将来的に物件を買い戻したいと考えているなら、買い戻し時の条件も事前にしっかりと確認しておくことが重要です。具体的には、買い戻し価格がいくらになるのか、買い戻しが可能な期限はいつまでかといった点をチェックしておきましょう。
一般的には売却価格に年3〜5%を上乗せした金額が買い戻し価格の目安とされており、契約書にその条件が明記されているかを必ず確認してください。
リースバック後のサポート内容
水回りのトラブル対応や物件の定期清掃、セキュリティサービスといったリースバック後のサポートが充実している業者も存在します。こうしたサービスが整っている業者を選ぶことで、リースバック後も安心して長く暮らし続けることができるでしょう。
リースバックの相談を進める際の流れ
リースバックの契約は、以下のステップで進行します。手順を事前に把握しておくことで、トラブルの防止やスムーズな手続きにつながります。
相談する業者を決める
インターネットの比較サイトや口コミなどを活用して、複数のリースバック業者をリストアップしましょう。その後、査定額だけでなく、買い戻し条件や家賃設定、担当者の対応の良さなども含めて総合的に比較します。
最終的には、単に高額査定を出した会社ではなく、信頼できる対応と明確な条件を提示してくれる業者を選ぶことが大切です。
問い合わせ・査定の依頼
選定した業者に対し、電話や公式サイトの問い合わせフォームから査定依頼をおこないます。
この段階では、まず「机上査定」がおこなわれるのが一般的です。これは、実際に物件を訪問する前に、所在地・築年数・延床面積・周辺の取引事例などの情報をもとに、おおよその査定価格を算出する方法です。
机上査定の結果をもとに訪問査定へ進むかどうかを判断する流れになるため、必要な情報はできるだけ正確に伝えることが重要です。
訪問査定
業者の担当者が実際に現地を訪れ、建物の外観や内装の状態、周辺環境を細かくチェックします。
例えば、外壁や屋根の劣化状況、室内の傷や汚れ、水回りの状態、バリアフリー対応の有無、日当たりや騒音の程度などが確認されます。また、周辺施設や交通の利便性、治安状況なども評価に含まれることが多く、これらが査定価格に影響を及ぼします。
さらに、想定される修繕箇所の有無や、物件をリースバック後にどのように活用しやすいか(投資物件としての需要や再販のしやすさなど)も、考慮される重要なポイントです。
査定価格と賃貸借契約の提示
業者から、買取価格・賃料・契約期間・更新の可否などを含む詳細な賃貸借契約の条件が提示されます。
不明点があれば曖昧にせず、書面での提示を求めたり、複数業者の条件を比較したりして納得のいく選択をしましょう。
契約締結
売買契約と賃貸借契約は同時に締結されます。
売買契約では、売却金額や支払い条件、登記手続きの方法などが定められており、一方で賃貸借契約では、契約の種類、月々の賃料、契約期間、更新の有無、原状回復義務、退去時の条件などが明記されます。
特に注意すべき点として、普通賃貸借か定期賃貸借かの契約の種類、契約の更新条件が自動か手動か、退去予告期間がどのくらいか、修繕費用や固定資産税の負担がどちらにあるかといった細かい内容も確認が必要です。疑問点がある場合は、専門家に契約書の内容をチェックしてもらうと安心です。
売却金の受け取り
契約が成立すると、通常は1〜2週間以内に売却代金が指定口座に振り込まれます。売却代金は原則として一括での支払いとなりますが、業者によっては分割払いとなるケースもあるため、支払いスケジュールの明記があるかどうかも要チェックです。
また、売却にともなって住宅ローンなどの債務が残っている場合、抵当権の抹消手続きが必要になります。抵当権を抹消しなければ正式な所有権移転ができないため、残債の清算と同時に金融機関と連携し、抹消書類の取得と登記手続きを進める必要があります。
振込までに必要な手続きや書類の提出期限なども契約書で定められているため、スムーズに資金を受け取るためには、事前にスケジュールを把握し、必要書類の準備も怠らないようにしましょう。
リースバックの買取相場と家賃相場
相場感を持っておくことで、提示された条件が適正かどうかを見極めやすくなります。
リースバック時の物件買取相場
リースバック時の物件買取相場は、一般的な市場価格の60〜80%が目安とされています。築年数や立地条件、建物の状態によって変動するため、相見積もりを取ることが賢明です。
リースバックでは、売却後も借主として住み続けることになるため、万が一家賃の滞納が発生した際のリスクや、不動産価値の下落といったリスクを業者側が想定しています。そのため、通常の不動産売却に比べて、買取価格はやや低めに設定される傾向があります。
また、投資用不動産として利回りを重視する業者が多く、家賃収入とのバランスを見ながら買取価格を決定することから、相場よりも安くなることが一般的です。
リースバック後の家賃相場
リースバック後の家賃は、売却価格に対する利回りを基準に設定されるのが一般的です。年間の家賃相場は、買取価格の10%前後に設定されるケースが多く、月額家賃はこの金額を12ヵ月で割ったものになります。
より具体的には、年間賃料として買取価格の7〜13%程度が設定され、それを月割りして家賃が決まる仕組みです。例えば、買取価格が2,000万円の場合、年間家賃は140万円〜260万円(月額11.6万円〜21.6万円程度)が相場の目安となります。
このように、業者によって賃料の利回り設定は異なるため、提示された家賃が妥当な範囲にあるかを事前に確認することが重要です。
リースバックでよくあるトラブル
契約内容を十分に理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。ここでは代表的なトラブル事例を紹介します。
買い戻しの価格がリースバック時より高いケース
契約時に買い戻し条件が明記されていなかった場合、市場価格や再評価により買い戻し金額が大幅に上がってしまうことがあります。買い戻し価格は基本的に業者側に利益が出るように設定されるため、売却価格よりも高くなるのが一般的です。
また、リースバック中に支払っていた家賃を「積立金」と誤って認識してしまい、その分を差し引いて買い戻しできると勘違いするケースもあります。実際には家賃は使用料であり、買い戻し価格とは直接関係がないため、金銭の扱いや契約内容を事前にしっかり理解し、書面で明確に取り決めておくことが重要です。
契約が更新できないケース
短期契約で更新が認められない場合、突然退去を求められるリスクもあります。
特に、普通借家契約と定期借家契約の違いを理解しないまま契約してしまうと、「ずっと住めると思っていたのに契約満了で退去しなければならない」といった事態に発展しかねません。
普通借家契約は更新が前提となる一方で、定期借家契約は原則として更新がなく、再契約が必要になります。契約期間や更新条件、契約形態は、事前にしっかり確認し、納得した上で契約を結ぶようにしましょう。
リースバックの相談なら一建設の「リースバックプラス+」がおすすめ

当社「一建設」が提供する「リースバックプラス+」は、長年の住宅事業で培ったノウハウと信頼をもとに生まれた、自社開発のリースバック専用サービスです。
お客様が現在お住まいのご自宅を当社が買い取り、そのまま賃貸として住み続けていただけるため、引っ越しの手間なく資金調達が可能です。また、将来的な買い戻しも選択できる柔軟な契約設計が特徴で、相続対策や老後の生活設計にも最適です。
さらに、契約更新の保証制度や、全国対応のサポート体制、生活インフラに関するご相談への対応など、暮らしに寄り添ったサポートも充実しています。
「住宅を手放したくないけど、まとまった資金が必要……」そんなお悩みをお持ちの方は、まずは無料のお試し査定をご利用ください。
まとめ
リースバックは、現在の住まいに住み続けながら資金を確保できるという大きなメリットがある一方で、契約内容の不理解や業者選びのミスによって、後悔やトラブルにつながるケースも少なくありません。
買取価格や家賃相場、契約形態、買い戻しの条件など、事前に確認すべきポイントは多岐にわたります。特に、「普通借家契約と定期借家契約の違い」や「家賃が積み立てではないこと」といった基本的な仕組みを正しく理解することが重要です。
自分の状況に合った選択をするためにも、信頼できる業者を見極め、まずは無料査定などを通じて気軽に相談してみることをおすすめします。