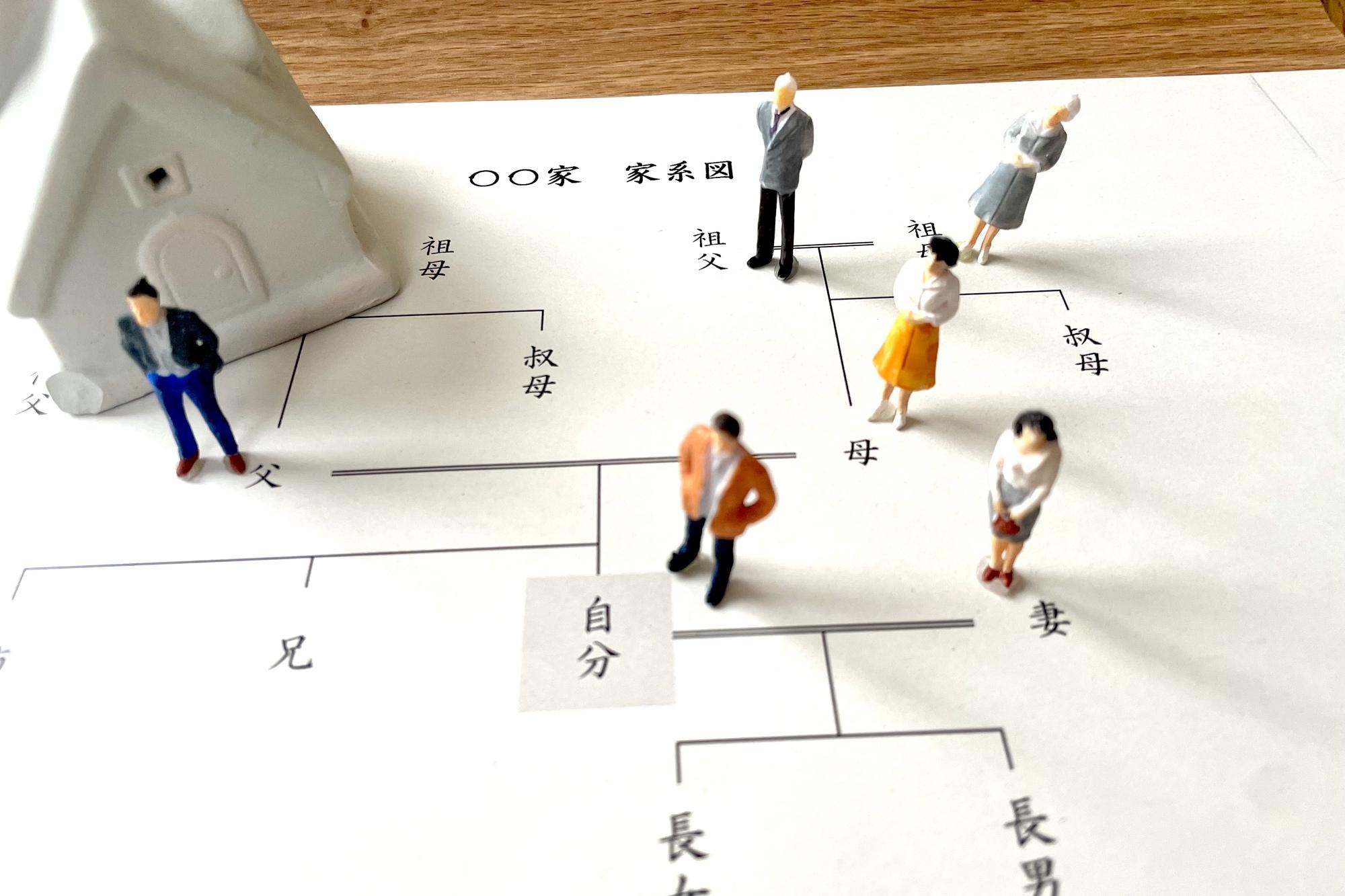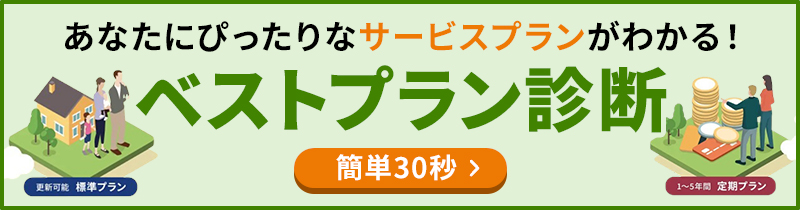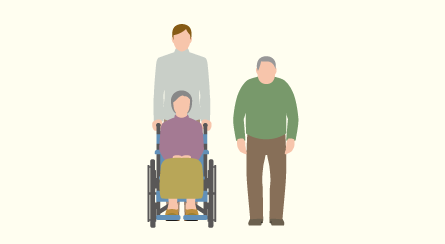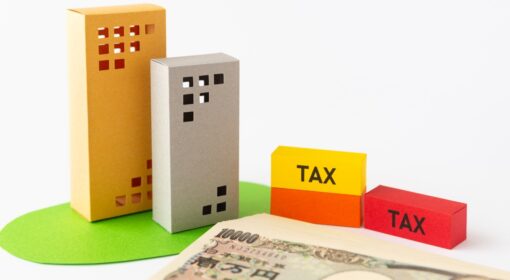兄弟で実家を相続することになった場合、「どのように兄弟で分割すればいいのかわからない」と悩む方は多いのではないでしょうか。
実家は現金のように簡単に分けることが難しいため、兄弟間の話し合いがまとまらず、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
この記事では、実家を相続する際の分割方法から、よくあるトラブル事例とその対処法などを解説します。また、記事の最後では、兄弟間の遺産分割のトラブルを解決する一つの方法として「リースバック」をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
INDEX
相続財産の分割方法の種類
遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合、相続人全員で集まり、どのように財産を分けるかを決めます。これを「遺産分割協議」といい、誰がどの財産をどれだけ相続するかを具体的に決めます。
この協議で合意した内容が、実際に財産を分ける際の具体的な方法となります。
相続財産の分割方法の種類は主に4つに分類され、それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。各方法の特徴や流れを理解し、兄弟全員が納得できる方法を選ぶことが重要です。
現物での分割
現物分割は、相続財産をそのままの形で兄弟で分ける方法です。家自体を手放したくない場合はこの方法が有効です。
具体的には、「実家は兄、金融資産は弟が相続する」というように一つの財産を一人で引き継ぎます。
手間や費用がかからず、実家を残せることが最大のメリットです。
しかし、「相続資産の価値が平等ではない」と不公平感が生まれることが多いため、不満や対立につながる可能性があります。
現金化による分割
実家を売却して現金化し、その現金を兄弟で分ける方法です。
現金化することで公平に遺産を分割することができ、不満が起こりにくいのがメリットです。
ただし、売却する価格は、兄弟で想定している売却価格に差があることもあるため、お互いが納得できる最低限の価格を決めておくことが重要です。
また、売却するための手間と費用がかかるため、相続手続きに時間を要するだけでなく、「誰が不動産会社との手続きを進めるのか」といった役割分担をめぐってトラブルになることも少なくありません。役割を請け負ってくれる兄弟には謝礼なども考慮しましょう。
そして、売却時に利益が出ると譲渡所得税がかかるため、手元に残る現金が減ってしまうことにも注意が必要です。
代償による分割
兄弟の一人が実家を相続し、専門家に家の価値を査定してもらい、その家の価値に見合った現金を他の兄弟に支払う方法を「代償分割」といいます。
この方法ですと、実家を残しつつ、他の兄弟にも公平に財産を分配することが可能です。
しかし、実家を相続する人は、他の兄弟に支払う代償金や相続税などの資金を用意する必要があり、金銭的な負担が大きくなるというデメリットがあります。
もし、資金が足りない場合は、新たな借金を背負うか、兄弟への支払いを待ってもらうことになり、これが原因で兄弟が対立するリスクが高くなります。
また、代償金の金額をめぐり、兄弟間で合意が得られないケースもあります。「専門家の査定が安すぎではないか」「もう少し高く売れるはずだ」のような不満が生まれることもあり、話し合いが難航するケースも少なくありません。
共有による分割
共有分割とは、実家や土地を兄弟全員が共同で所有する方法です。
全員が財産に対する権利を持つため、一見公平な分割に思えますが、実は、最もトラブルになりやすくリスクが高い分割法です。
具体的なトラブル事例は、次の見出しでご説明します。
兄弟間でよくある実家相続トラブル事例

実家を含む遺産相続をするうえでのトラブルは、金銭面だけでなく感情や思い出も絡むため、多くの人が避けて通れない問題です。
2024年(令和6年)のデータによると、全国の家庭裁判所には15,379件の遺産分割事件が持ち込まれています(※)。これは兄弟だけのトラブルに限られませんが、実家の相続をめぐる争いが決して珍しくないことがわかります。ここでは、実際によくあるトラブル事例をご紹介します。
(※出典:令和6年 司法統計年報(家事編))
共有名義によるトラブル
先ほどご説明した通り、最もトラブルになりやすいのが「共有による分割」です。
なかでも、一人が家に住み続け、ほかの兄弟は権利だけを持つ場合は、固定資産税や修繕費の費用負担割合をめぐり対立することもあります。
「兄だけ家に住んでいるのに、なぜ住んでいない自分が費用を負担しなければならないのか」などといった不満から兄弟関係が悪化することもあります。
そのため、共有名義を選択する際は、必要な費用分担や決定権などを、事前に取り決めておくことが大切です。
また、家を売却したい場合は、兄弟全員の同意が必要になります。
たとえ自分が売却したいと考えていても、一人でも反対すると売却手続きは進めることができません。
さらに、長い間共有名義のままにしておくと、兄弟それぞれの子どもにも権利が引き継がれます。そのため時間が経つほど、関係者がどんどん増えていき、話し合いが困難な状況になります。
家に誰も住んでいない場合は管理が行き届かなくなり、放置してしまうという事例が少なくありません。
実家相続人以外の不公平感
被相続人が亡くなる以前から、介護や同居で一緒に住んでいた兄弟がいる場合は、そのまま実家に住み続けるケースが多く見受けられます。
親の介護を担っていた兄弟が実家を相続し、それ以外の兄弟は代償分割として現金を受け取ることが多いです。
しかし、実家の不動産価値が他の財産を上回ると、現金を受け取った兄弟は、「自分だけ損をした」と不満を感じてしまいます。
被相続人の介護を担った兄弟がいるケースだと、その貢献を「寄与分」として考慮できますが、他の兄弟とのバランスが取れなければ、不公平感から対立してしまう恐れがあります。
財産評価の認識の違い
家の価格の評価をする際に、「路線価」と「実勢価格」の2種類の方法があります。
路線価とは、相続税を計算する際に基準となる土地価格のことで、毎年国税庁から発表されています。
(※出典:国税庁「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」)
土地により価格は異なりますので、基準となる目安がなければ税金を計算することができないため、この価格をもとに税金が算出されます。
路線価は、特定の道路に面した標準的な土地を基準にしているため、不動産個別の条件は反映されていません。また、価格の変動を考慮し実勢価格の目安である公示価格の80%の水準に設定されています。
一方「実勢価格」とは、不動産市場で実際に取引されている価格のことです。
これは、不動産会社が査定を行い、不動産の状態やそのときの市場の需要と供給のバランスにより価格が変動します。需要が高ければ価格は上がり、買い手が見つからない場合は、価格が下がります。
一般的には、実勢価格は路線価よりも高くなる傾向があります。しかし、過疎地域や立地が悪く需要が少ないなど、場合によっては実勢価格が路線価を下回ることもあります。
このどちらを評価額にしているかにより、兄弟間で認識のズレが生じます。
相続を円滑に進めるためにも、これらの価格の違いを理解し、お互いが納得できる評価方法を事前に話し合いましょう。納得できない際は、専門家に相談するのも一つの手段でしょう。
実家相続トラブルの原因と背景
実家を相続する際の兄弟間のトラブルはなぜ起こるのでしょうか。ここからは、原因や背景を詳しくご説明します。
分割しにくい
実家や土地は現金のように簡単に平等に分けることができないため、相続時にトラブルになりやすい財産です。
「分割するのが面倒だから」といって安易に共有名義にしてしまうと、あとで管理や処分が難しくなりトラブルに発展するケースが少なくありません。
特に、固定資産税や修繕費などの維持費を誰がどのように負担するかという問題、また売却時に必要な手続きや全員の同意の取得など、関係者全員が平等な負担をすることが難しい場面が多く見られます。
こうした事情から、話し合いがまとまらずに、長年放置されるケースもあります。
このような分割しにくい財産は、計画的な準備が重要です。考えることをあと回しにせず、事前にどのように分割するのか計画を立てておくとトラブルを防ぐことができます。
専門知識の不足
相続をめぐるトラブルを防ぐためには、兄弟全員が知識を持つことが重要です。
具体的には、誰が相続人になるのかを正確に把握し、法定相続分がどのようになるのか調べておくだけで、防ぐことのできるトラブルもあります。
法定相続人とは、以下の通りです。
民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。法定相続人となるのは、亡くなった人の配偶者と一定の血族(子や父母、兄弟姉妹など血縁関係のある人=「血族相続人」)です。子には養子や法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれます。胎児も死産の場合を除き相続人に含まれます。
なお、内縁関係のように事実婚の状態にある人、離婚した元夫や元妻は法定相続人に含まれません。
また、相続における「言った、言わない」のトラブルも少なくありません。「被相続人と二人きりのときに、口約束で財産分与の話をした」といった証拠がないやり取りは、あとで大きな火種になりがちです。このような不確かな約束は、他の兄弟との間で不信感を生み、トラブルに発展する可能性が高いです。
兄弟間のトラブルを回避するためには、被相続人に遺言書を作成してもらうことが最も効果的な方法です。事前に相続人となる兄弟で話し合い、被相続人に遺言書を作成するように伝えておきましょう。遺言は民法で定められた特定の書面形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)で作成する必要があり、それ以外は無効となるため、不明な点などは、専門家に相談することも考えましょう。
兄弟間のトラブルを避けるための対処法
家の相続で、兄弟間のトラブルが起こりそうな場合はどのようにすればいいのでしょうか。ここでは、兄弟間の相続トラブルを回避するための対処法をご紹介します。
兄弟間での話し合い
兄弟間のトラブルが発生する多くの原因は、コミュニケーション不足です。
日頃から仲が悪く、コミュニケーションが不足していると、話し合いが難航するだけでなく、トラブルになる可能性が高くなります。
そして、たとえ普段良好な関係だとしても、金銭が絡む相続のこととなると、話し合いがまとまらず、トラブルになるケースも多くあります。
また、兄弟の一人が取りまとめようと話し合いを勝手に進めた場合は、ほかの兄弟から不満が出るパターンもあります。
普段から兄弟間でコミュニケーションをとり、事前に相続について話し合いをしておきましょう。兄弟で情報共有することが相続の話し合いを進めるうえで、とても重要です。
遺言書の作成
遺言書がある場合は、兄弟間で話し合う「遺産分割協議」は基本的におこなう必要がありません。
そのため、被相続人には遺言書を作成するように伝えておくことが、相続時の話し合いを円滑にし、トラブルを未然に防ぐうえで大切です。
しかし、遺言書の内容が兄弟間で大きく異なる場合は、その内容が法律に抵触する可能性があります。この場合「遺留分侵害請求権」と呼ばれる権利があり、相続人は、一定の割合の遺産を受け取ることが法律で保障されています。
以下、政府広報オンラインより引用になります。
亡くなった人(被相続人)が財産を贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、自身の遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。
なお、遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
そのため、被相続人が遺言書を作成する際は、どの程度であれば認められるのかをよく考えることが大切です。不安な場合は、公平性と法的効力のある内容にするためにも、専門家の助言を受けることをおすすめします。
遺言書の作成方法には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類ありますので、それぞれご紹介します。
自筆証書遺言とは、全文を手書きで作成する遺言書のことです。
以前は被相続人の手書きのみが有効でしたが、2019年1月以降はパソコンや代筆での作成でも認められることになりました。
しかし、要件を満たしていない場合は無効となることもあるため、作成する際は、記載内容に不足がないか慎重に確認しましょう。
以前は、自宅で保管して置く方法でしたが、2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」により法務局で保管することが可能になりました。これにより自宅保管による改ざんや紛失の恐れがなくなり、「遺言書の存在を知らなかった」というトラブルも防ぐことができるようになりました。
公正証書遺言とは、専門家である公証人が被相続人の代筆で遺言書を作成する方法です。法律で定められた要件を満たすことができるため、遺言書が無効になるリスクがありません。
また、原本は公証役場で保管するため、紛失や書き換えなどの心配も不要ですが、手間や費用がかかるのがデメリットです。
専門家への相談
もしも兄弟間でトラブルが起こりそうな場合は、初めから専門家へ相談するのが安心です。
相談する内容により、依頼する専門家が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
| 弁護士 | 相続全般や、すべてのトラブルの相談ができます。 |
|---|---|
| 司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記)の手続きなどの依頼ができます。トラブルの相談は専門外です。 |
| 税理士 | 相続税申告の相談ができます。 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更、許可手続きなどの手続きを依頼できます。 |
相続トラブルを防ぐリースバックという選択肢
遺産分割のトラブルを防ぐ選択肢として、「リースバック」がおすすめです。
リースバックとは、現在住んでいる実家を不動産会社に売却し、その後は実家を賃貸として借りられることで、実家に住み続けながらまとまった現金を手に入れられる仕組みです。
家賃の支払いが発生しますが、リースバックには大きなメリットがあります。売却で得た資金は相続財産として兄弟間で平等に分配できるため、不公平感を減らし、共有名義も避けることができる点で大きなメリットがあるといえます。
さらに、住み慣れた実家にそのまま住み続けられるうえ、所有権が不動産会社に移るため、固定資産税の支払いも不要になります。
一建設の「リースバックプラス+」
一建設の「リースバックプラス+」は、以下の「2プラン 3タイプ」から選ぶことが可能です。
- 標準プラン(普通賃貸借契約)
- 定期プラン(賃料優遇タイプ)
- 定期プラン(買戻優遇タイプ)
ここからは、それぞれのサービス内容と違いをご紹介します。
「数十年後には家を買い戻したい」と考えている方に最適なのが「標準プラン(普通賃貸借契約)」です。
長く住めば住むほど、再購入価格が下がるため、将来買い戻しを検討されている方には最もおすすめです。また、リースバック後は賃貸契約になりますが、敷金礼金などもかからないため、初期費用を抑えることも可能です。
「定期プラン(賃料優遇タイプ)」は、短期間での利用を考えている方におすすめです。最初の1年間賃料が9円ですので、数年後に引っ越しや老人ホームへの入居が決まっている方にピッタリのプランです。
「定期プラン(買戻優遇タイプ)」は、売却価格と同額で再購入することが可能なプランです。
一般的なリースバックは、再購入価格が売却価格を上回ることが多いため、一時的に資金調達をし、早期買い戻し2〜5年)を考えている方には、特におすすめのプランです。
どのプランも「ホームセキュリティ」がついており、在宅時や外出時の防犯面で安心して暮らすことができます。その他にも水回りのトラブルや、玄関の鍵のトラブル時にも対応してもらえる特典サービスもあり、日々の暮らしのサポートをしてくれます。
まとめ
遺産を分割するとなると、公平に分割することがなかなか難しいのがご理解いただけたかと思います。
なかでも実家を相続するときには、兄弟間のトラブルに発展しがちです。
特に共有名義は分割する際は簡単ですが、時が経つにつれ共有人数が増え、結果的に家や土地が放置される可能性が高いので、安易に選択しないことをおすすめします。
こうしたトラブルを防ぐためには、事前に兄弟を含め話し合いをし、被相続人に公平な分割になるよう遺言書を書いてもらいましょう。
公平に分割する方法として、家を現金化する方法が兄弟の対立を防ぐのに有効です。
一建設がご提供する「リースバックプラス+」なら、ご実家を売却し、現金化することにより、兄弟で公平に財産を分割することができます。
また、売却後も実家に住み続けることができるうえ、買い戻しも可能です。
実家の相続に悩んでいる方は、兄弟間のトラブルを解決するための選択肢として「リースバック」を検討してみてはいかがでしょうか。