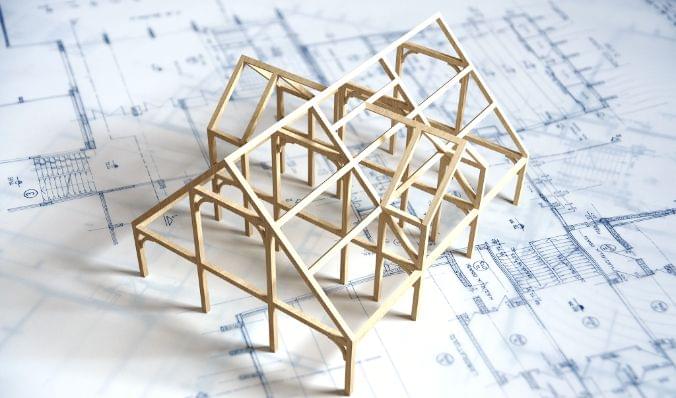2025.05.19 | ローン
住宅ローンはみんないくら払ってる?平均返済額や借入額、注意点など徹底解説

目次
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
住宅ローンは、人生最大の買い物といわれる住まいの購入に欠かせないローンです。「いったいみんなはいくら借りているの?」「自分の返済額は平均的なの?」そんな疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、住宅ローンの平均借入額や返済額、最新の情報をわかりやすく解説します。ぜひ、マイホーム計画の参考にしてください。
1. 住宅ローン利用の平均値
住宅ローンを利用する前に、まずは購入資金の目安やローンを組んでいる方の割合を見ておきましょう。
1.1. 新築住宅の全国平均購入資金
国土交通省が発表した「令和5年度住宅市場動向調査」により、住宅購入にかかる資金の平均額が明らかになりました。
| 住宅種別 | 平均購入資金 |
|---|---|
| 注文住宅(土地含む) | 5,811万円 |
| 注文住宅(土地除く) | 4,319万円 |
| 分譲戸建住宅 | 4,290万円 |
| 分譲集合住宅 | 4,716万円 |
また、同調査ではリフォーム資金も調査しており、平均額は137万円でした。住宅取得を検討する際の目安として参考にしてください。
注文住宅を建てる際に必要な費用を詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
1.2. 注文住宅取得者のローン利用割合は約75%
注文住宅でローンを利用している方の割合は以下のとおりです。
| 地域 | 住宅ローンがある世帯の割合 |
|---|---|
| 全国 | 74.8% |
| 三大都市圏 | 69.7% |
注文住宅を取得した世帯のうち、住宅ローンを利用している割合は全国平均で74.8%に達しており、多くの方が住宅購入時にローンを組んでいることがわかります。一方、三大都市圏では、この比率がやや低く69.7%でした。
また、工事種類別住宅ローン利用率は以下のとおりです。
| 工事の種類 | 住宅ローンがある世帯の割合 |
|---|---|
| 新築 | 79.5% |
| 建て替え | 48.7% |
新築住宅を取得した世帯では、79.5%と高い比率でローンを利用しているのに対し、建て替えをおこなった世帯では48.7%とほぼ半数にとどまっています。
建て替え世帯では、既存住宅の資産価値や蓄えた資金を活用できる場合が多いためと考えられます。これらのデータから、新築住宅の取得には住宅ローンが重要な資金調達手段となっていることが明らかです。
2. 住宅ローン返済の平均値
住宅ローンの返済額の平均値を知ることは、無理のない資金計画を立てるために必要です。他の世帯の返済状況を把握することで、自分の収入やライフプランに合った借入額を判断し、将来的な負担を軽減できます。
2.1. 返済期間は35年超が最多
国土交通省の調査によると、住宅建築資金の借入金返済期間は、全国でも三大都市圏でも「35年以上」を選択する方が最も多く見られました。
住宅ローンの平均返済期間は、以下の表を参考にしてください。
| 項目 | 全国 | 三大都市圏 |
|---|---|---|
| 35年以上の返済期間を選択した割合 | 68.1% | 69.0% |
| 平均返済期間 | 32.7年 | 32.6年 |
上記のデータから、住宅ローンは30年以上の長期返済が一般的であることがわかります。
2.2. 注文住宅の年間ローン返済額は平均155万円
下記の表を見ると、住宅タイプによる住宅ローンの特徴がはっきりと表れています。
| 項目 | 注文住宅 | 分譲戸建住宅 | 分譲集合住宅 |
|---|---|---|---|
| 年間返済額 | 155.2万円 | 125.0万円 | 123.6万円 |
| 毎月の返済額(目安) | 約12.9万円 | 約10.4万円 | 約10.3万円 |
| 変動金利型選択率 | 75.0% | 77.0% | 86.8% |
| 年収に対する返済負担率 | 19.4% | 17.6% | 15.5% |
| 負担感がある世帯の割合 | 64.5% | 61.5% | 47.1% |
注文住宅は年間返済額が最も高く、分譲住宅(戸建て・集合)はほぼ同水準です。
しかし、変動金利型の選択率は分譲集合住宅で最も高く、年収に対する負担率も低くなっています。また、負担感に関しても分譲集合住宅購入者は、他と比べて低いのが特徴です。
3. 住宅ローン利用時の自己資金(頭金)について

頭金の額によって借入額や金利、毎月の返済負担が変わるため、資金計画を立てる必要があります。ここでは、住宅ローン利用時の自己資金はどのくらい必要なのかをご紹介します。
3.1. 注文住宅の自己資金比率は29%
国土交通省の調査で自己資金比率に注目すると、新築物件(注文住宅新築・分譲戸建住宅)は約30%程度の自己資金比率であるのに対し、中古物件は約47〜48%と高くなっています。特に分譲集合住宅は48.3%と半分近くを自己資金で賄っているようです。
| 自己資金比率(住宅建築) | 購入資金総額 | 自己資金額 | 自己資金比率 |
|---|---|---|---|
| 注文住宅新築(土地購入あり) | 5,811万円 | 1,685万円 | 29.0% |
| 注文住宅(建て替え) | 5,745万円 | 2,442万円 | 42.5% |
| 分譲戸建住宅 | 4,290万円 | 1,305万円 | 30.4% |
| 分譲集合住宅 | 4,716万円 | 2,279万円 | 48.3% |
| 既存戸建住宅(中古) | 2,983万円 | 1,411万円 | 47.3% |
| 既存集合住宅(中古) | 2,793万円 | 1,338万円 | 47.9% |
| リフォーム | 137万円 | 112万円 | 81.9% |
また、全国と三大都市圏の違いも顕著に表れていました。
| 地域 | 土地購入資金 | 自己資金額 | 自己資金比率 |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 1,929万円 | 720万円 | 37.3% |
| 三大都市圏平均 | 2,813万円 | 1,063万円 | 37.8% |
土地代は三大都市圏が全国平均より約900万円も高くなっていました。しかし、自己資金比率はどちらも約37〜38%とほぼ同等であることから、三大都市圏では資金力のある層が住宅を購入していると考えられます。
上記の数字から、住宅取得には物件タイプによって必要な資金準備が大きく異なることがわかります。
3.2. 自己資金の内訳
自己資金の内訳としては、全国・三大都市圏ともに「預貯金・有価証券売却代金・退職金」が大きな割合を占めていました。
一方、不足分を補う借入金に関しては、フラット35以外の民間金融機関からの借り入れが最も多く利用されている傾向にあります。
4. 住宅ローンを組んだ年齢と年収の平均値
住宅ローンを組むときの年齢と年収の平均を知ることで、自分の状況と比較でき、借入額や返済計画を立てやすくなります。無理のない返済を続けるために、ぜひ参考にしてください。
4.1. 住宅ローンを契約する年齢は30代が最多
住宅取得者の年齢層には明確な傾向が見られます。注文住宅を取得する世帯では、全国的にも三大都市圏でも30代の世帯主が最も多く、それぞれ36.7%と35.6%を占めています。
特に新築住宅では、新築注文住宅取得者の42.1%が30代と、半数近い数字となっています。
| 住宅の種類 | 最も多い年齢層 | 割合 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 注文住宅(全国) | 30代 | 36.7% | – |
| 注文住宅(三大都市圏) | 30代 | 35.6% | – |
| 注文住宅(新築) | 30代 | 42.1% | – |
| 注文住宅(建て替え) | 60代 | 56.4% | – |
| 分譲戸建住宅 | 30代 | 48.0% | 38.2歳 |
| 分譲集合住宅 | 30代 | 42.7% | 43.0歳 |
上記のデータから、30代を中心とした若い世代が住宅を新規に取得する主な層だと確認できます。一方で、建て替えは高齢層が中心となっています。
なお分譲住宅では、戸建てよりも集合住宅のほうが平均年齢が高い傾向が見られました。
家を建てる際のタイミングを詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
>>家を建てるのにベストなタイミングとは?よくあるきっかけや必要な準備を解説
4.2. 注文住宅購入者の世帯年収は平均915万円
住宅取得者の世帯年収にも違いが見られます。注文住宅取得世帯の世帯年収は、全国では「600万円以上800万円未満」の層が最も多く22.2%を占めています。
一方、三大都市圏では「800万円以上1,000万円未満」の層が20.8%と最多となっており、都市部ではより高所得層が住宅を取得する傾向があることがわかります。平均世帯年収を見ても、全国平均が915万円であるのに対し、三大都市圏平均は989万円と高くなっています。
| 住宅の種類 | 最も多い年収帯 | 割合 | 平均世帯年収 |
|---|---|---|---|
| 注文住宅(全国) | 600万円以上800万円未満 | 22.2% | 915万円 |
| 注文住宅(三大都市圏) | 800万円以上1,000万円未満 | 20.8% | 989万円 |
| 分譲戸建住宅 | 400万円以上600万円未満 | 23.1% | 761万円 |
| 分譲集合住宅 | 400万円以上600万円未満 | 19.8% | 871万円 |
また、注文住宅取得者は、分譲住宅取得者よりも全体的に年収が高く、三大都市圏では「800万円以上1,000万円未満」の年収帯が最多となっています。
分譲住宅では、戸建てよりも集合住宅の取得者のほうが平均年収が110万円も高いことから、都市部の高所得層がマンションを選ぶ傾向にあるようです。
また、すべての住宅タイプで、過去に住宅を購入した経験のある二次取得者のほうが一次取得者より平均年収が高いという共通点がありました。住宅の買い替えには一定の経済力が必要であることを表しています。
5. 住宅ローンを組むときの注意点
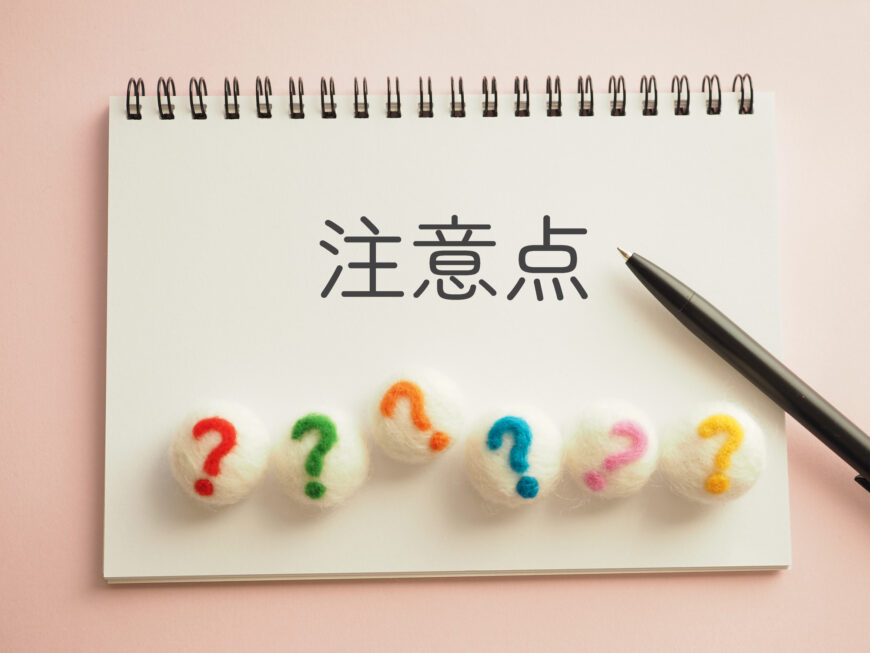
住宅ローンを組む際の注意点を5つご紹介します。
5.1. 年収倍率から借入額を決める
金融機関の多くは年収の35%を返済負担の上限としており、フラット35でも年収400万円以上の場合は35%以下、400万円未満の場合は30%以下という基準を設けています。ただし、住宅ローンを検討する際、実際に限度額まで借りるのはおすすめしません。
例えば、金利1.96%で限度額(返済負担率35%)を借り入れた際の負担額は下記のとおりになります。
| 年収 | 借入限度額 (35%) | 月々の返済額(限度額) | 年間返済額(限度額) | 返済負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 2,278万円 | 7.5万円 | 90万円 | 30% |
| 400万円 | 3,543万円 | 11.7万円 | 140.4万円 | 35% |
| 500万円 | 4,429万円 | 14.6万円 | 175.2万円 | 35% |
| 600万円 | 5,315万円 | 17.5万円 | 210万円 | 35% |
なお、返済負担率25%で計算した場合の負担額は下記のとおりになります。上記の内容と比較検討してみてください。
| 年収 | 借入限度額 (25%) | 月々の返済額(限度額) | 年間返済額(限度額) | 返済負担率 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 1,630万円 | 5.4万円 | 64.8万円 | 21.6% |
| 400万円 | 2,530万円 | 8.3万円 | 99.6万円 | 24.9% |
| 500万円 | 3,164万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 25% |
| 600万円 | 3,796万円 | 12.5万円 | 150万円 | 25% |
将来の金利上昇や老後の収入減少、予期せぬ出費などに備えるためにも、返済負担率は25%以内に抑えるのがおすすめです。
ローンシミュレーションページでは、予算や希望条件に合わせて、購入可能な物件や借入可能額の目安を簡単にチェックできます。気になる方はぜひお試しください。
5.2. 無理のない返済額におさめる
住宅ローンを組む際には、毎月の返済額を慎重に考えることが大切です。金融機関が提示する借入可能額の上限まで借りるのではなく、将来の家計の安定性を考慮した計画が必要です。
月々の返済額は、収入に対して見合った割合に抑えることで、日々の生活に余裕を持たせられます。上述したように、返済負担率を年収の25%以内に設定するのがおすすめです。思わぬ出費や金利上昇など、今後のリスクに備えるためのバッファーとなります。
また、住宅を所有すると、定期的な修繕費や突発的な修理費用、固定資産税などの諸経費が発生することも忘れてはなりません。
例えば、築年数が経つにつれて屋根の修理や外壁の塗り替え、設備の更新など、数十万円から数百万円規模のメンテナンス費用が必要になる可能性があります。
これらの費用を捻出するためにも、住宅ローンの返済に家計を圧迫されすぎない状態をしっかり保つことが大切です。
5.3. 金利タイプを慎重に選ぶ
住宅ローンには、主に3つの金利タイプが提供されており、それぞれに特徴があります。
- 変動金利型
- 固定金利期間選択型
- 全期間固定金利型(超長期固定金利型)
まず、変動金利型は、市場金利の変動に合わせて金利が見直されるタイプです。金利が下がれば返済負担が軽減される一方、上昇すれば返済額も増えるリスクがあります。将来の返済額が確定しないため、長期的な家計計画を立てにくいのが注意したい点です。ただし、国土交通省の調査によると、全国・三大都市圏ともに変動金利型を選択している方が多く、それぞれ 75.0%・80.7%でした。
次に、固定金利期間選択型は、当初の一定期間(2年、3年、5年、10年など)は金利が固定されるタイプです。この期間中は金利変動の影響を受けないため返済額が安定します。固定期間終了後は変動金利に切り替わり、その時点で市場金利が上昇していれば返済負担が増加します。初期の計画は立てやすいものの、期間終了後の見通しは不透明なのがデメリットです。
最後に、全期間固定金利型(超長期固定金利型)は、返済期間全体を通じて金利が変わらないタイプです。代表的なものとして「フラット35」があります。市場金利がどう変動しても返済額は一定のため、最も確実な返済計画を立てられるのがメリットです。ただし、契約時の金利水準が高めに設定されることが多く、変動金利と比べると当初の返済負担が大きくなる傾向にあります。
それぞれのメリットやデメリットを踏まえた上で、自分のライフプランに合わせた選択が大切です。
5.4. 完済年齢を考慮して返済期間を決める
住宅ローンを検討する際、借入額や金利タイプに注目しがちですが、返済計画で大切なのが完済時の年齢を意識することです。住宅ローンを組む時期を決めるのと同様に、いつまでに返済を終了させるかという出口戦略もしっかり計画する必要があります。
理想的には住宅ローンは、できるだけ早い完済が望ましいですが、住宅価格の高騰や収入の伸び悩みなどから、実際の平均返済期間は30年以上になっているのが現状です。
例えば、35歳で35年ローンを組むと完済は70歳となり、定年退職後も返済が続くことになります。退職後は収入が減少するケースが多いため、定年までに完済できる返済計画を立てるか、退職後のお金を確保しておく必要があります。
住宅ローンの返済は、人生で大きな経済的負担となるため、「いつから始めるか」だけでなく「いつまでに終えるか」という視点を持つことで、現実的で無理のない住宅計画を立てられるでしょう。
5.5. 団体信用生命保険(団信)に加入する
団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンに付帯する保険のことです。金融機関が契約者となり、住宅ローン利用者が被保険者となります。主に死亡時や高度障害の場合に、残りのローン残高が保険金で完済される仕組みです。
近年は保障の範囲が広がり、がんと診断されたときや要介護状態になった際にもローンが完済される特約付き団信も増えています。住宅ローンの返済期間中に万一のことがあっても、家族が住まいを失わずに済む大切な保障として、加入を検討する価値があるでしょう。
6. 住宅ローンの平均的な利用額を知って賢く利用しよう

住宅ローンを検討する際には、国内の平均値や傾向を知っておくと資金計画の見直しに役立ちます。平均借入額や返済負担率を参考にしながら、自分の収入や家族計画に合った無理のない住宅ローン計画を立てることが大切です。
一建設では、お客さまの夢と予算に真剣に向き合い、理想のマイホームづくりをサポートします。年間9,000棟以上の建築実績から生まれた確かな技術力と、効率的な供給ノウハウにより、価格を抑えながらも妥協のない品質と性能を持った注文住宅を叶えます。
不安や疑問点があれば、専門スタッフがいつでもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
一建設の注文住宅を見る
はじめの注文住宅
一建設株式会社は、一戸建て住宅販売戸数日本一※1の飯田グループホールディングスの中核企業です。
ローコストとまじめに向き合い大満足のマイホームを実現します。
建築コストをおさえたマイホームを手に入れ、家計的に身軽になることで、
子どもの学費、家族との旅行や趣味、老後の建替え費等、より豊かなゆとりの生活ができます。
リーズナブルにマイホームを建てると安心した将来設計が可能になります。
※1. 出典:日経業界地図2023年版
ご自宅の売却・引越し(住み替え)も一建設にお任せ
一建設の『ラクいえ売却』
住み替えによる不安を無くすために生まれた、一建設の『ラクいえ売却』。
住まいが売れるタイミングと新しい住まいが見つかるタイミングを合わせる必要がなく、
愛着のある住まいが高く売れるまで交渉する手間もありません。
ダブルローンをはじめとする自宅売却のお悩みを解消します。
- #売却後も1年間賃料無料で住み続けられるからゆとりをもった住み替えが可能
- #引越し費用を最大50万円一建設が負担で手厚くサポート
- #新生活に嬉しいキャッシュバック制度あり
- #一建設の取り扱い物件以外も売却可能
よく読まれている人気記事
-

2024.05.10 | 注文住宅
注文住宅のオプション53選!新築でやっておけばよかったと後悔しないための選び方や費用相場を紹介
注文住宅を建てたり新築住宅を購入したりする際、標準仕様とは別にオプションが設定されているケースが多くあります。オプショ...
-

2024.10.28 | 費用・制度
注文住宅の費用相場は?価格帯・広さ別の相場と費用を抑えるコツを解説
「注文住宅を建てたいけど、一体どれくらいお金が必要なんだろう……。」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。そ...
-

注文住宅(新築)のお風呂で後悔しないこだわりの選び方!おしゃれな浴室も紹介!
2024.05.10 | 注文住宅
-

ローコスト住宅がやばいと思われるのはなぜ?後悔しない選び方も解説
2024.09.11 | 注文住宅
-

「平屋はやめたほうがいい」といわれる理由と、実はたくさんある平屋のメリットを解説
2024.09.24 | 平屋
おすすめ記事
-

2025.03.10 | 費用・制度
建ぺい率・容積率とは?家を建てる前に知っておきたい基礎知識
広い土地と十分な資金さえあれば、大きな家が建てられると思っていませんか?実は、建てられる建物の大きさは、自治体によって...
-

2025.02.13 | 平屋
平屋とは?平屋のメリット・デメリットと建築実例をご紹介
戸建て住宅の一般的な階層構造としては、平屋と2階建て、3階建てがあります。これから家を建てる方のなかには、何階建てにす...
-

平屋か2階建てか?どちらを建てるか悩む方へ選ぶポイントを解説
2025.06.13 | 平屋
-

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
2025.12.12 | 注文住宅
-

家を建てるのに必要な期間は?家を建てる流れと最短で完成させるためのポイントを解説
2024.09.24 | 注文住宅
新着記事
-

2025.12.12 | マイホーム
ウォークインクローゼット設置のおすすめの間取りとは?注意すべきポイントや建築実例を紹介
衣類や荷物が増えるほど、「スッキリ片づく収納がほしい」と感じる方は多いでしょう。そんな願いを叶えるのがウォークインクロ...
-

2025.12.12 | マイホーム
シューズインクローゼットとは?シューズクロークとの違いや種類、メリット・デメリットを解説
玄関をスッキリ保つ収納として人気を集めている「シューズインクローゼット(SIC)」。近年は新築やリノベーションの際に設...
-

カーポート設置で注意すべき建ぺい率とは。2025年4月の法改正についても解説
2025.12.12 | 注文住宅
-

家を建てる前に知っておきたい、基礎知識と4つの注意点!
2025.12.01 | マイホーム
-

【平屋4LDKの間取り5選】おしゃれで暮らしやすい間取りづくりのコツを解説
2025.11.06 | 平屋