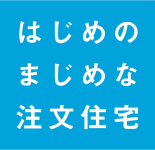マイホームの住み替えには、さまざまな税金がかかります。住み替えでは売却と購入を一度におこなうため、想像よりも多い税金に悩まされる方もいるでしょう。
しかし、税金を軽減できる特例制度が用意されているため、要件を満たせば税金の負担を減らすことが可能です。
この記事では、住み替えの際にかかる税金の種類と、活用できる特例制度を解説します。
住み替えの売却時にかかる3つの税金
住み替えの売却時は、主に3つの税金がかかります。ここでは、売却時にかかる税金の種類と発生する状況を解説します。
譲渡所得税
不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は、売却額から購入額や仲介手数料などの売却費用を差し引いた利益に対してかかる税金です。
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。(※1)
| 譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用) |
また、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられ、以下のようにそれぞれで税率が異なります。(※2)(※3)
| 種類 | 長期譲渡取得 | 短期譲渡取得 |
| 所有期間 | 5年以上 | 5年以内 |
| 所得税率 | 15% | 30% |
| 住民税率 | 5% | 9% |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 0.63% |
所有期間によってかかる税金が異なるため、事前に理解しておきましょう。
(※1)参照:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
(※2)参照:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
(※3)参照:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
登録免許税
登録免許税は、不動産登記をおこなう際にかかる税金です。不動産を売却した際は、所有権を移転するために所有権移転登記が必要となります。
所有権移転登記にかかる登録免許税は、買い主負担が一般的です。ただし、登録免許税の負担に明確な法律はないため、中間業者を介さず個人間での譲渡の場合などでは、当事者間での取り決めが必要となるでしょう。
また、住宅ローンが残っているなど、所有権移転を妨げるような抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記が必要です。
参照:法務局「登録免許税の計算」
印紙税
印紙税は、契約書など重要な書類に収入印紙の貼付を通じて納める税金です。税額は、契約書に記載されている金額によって異なります。
不動産売買での印紙税の金額は以下のとおりです。(※1)(※2)
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減税額 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
軽減税額は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書が対象です。契約書の金額と軽減措置の対象期間をしっかり確認しておきましょう。
(※1)参照:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
(※2)参照:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
住み替えの購入時にかかる4つの税金
住み替えの購入時には、主に4つの税金がかかります。ここでは、購入時にかかる税金の種類や特徴を解説します。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際にかかる税金です。不動産を購入後に、都道府県から納税通知書が届きます。
不動産取得税を求める計算式は以下のとおりです。(※1)
| 不動産取得税額 = 不動産の評価額 × 税率(4%) |
不動産の評価額は、固定資産税の税額算定に使用される課税標準額で算出されます。また、令和9年3月31日までは、軽減税率として3%の税率で計算が可能です。(※2)
なお、住宅取得の場合は、要件を満たすことで特例措置を受けられるため、不動産取得税がかからないケースもあります。
(※1)参照:総務省「不動産取得税」
(※2)参照:国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」
登録免許税
住み替えで新たに住宅を購入した際は、所有権移転登記が必要です。税額は不動産の評価額や住宅ローン額に税率をかけて計算されます。
また、要件を満たせば登録免許税の軽減措置を受けられます。主な登記の種類とそれぞれの税額は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 内容 | 本則 税率 | 軽減税率(適用期限) |
| 土地の所有権移転登記 | 土地の所有権を移す登記 | 2.0% | 1.5%(令和8年3月31日まで) |
| 建物の所有権移転登記 | 中古住宅など、所有権を移す登記 | 2% | 0.3% (令和9年3月31日まで) |
| 建物の所有権保存登記 | 新築住宅等、初めておこなう登記 | 0.4% | 0.15%(令和9年3月31日まで) |
| 抵当権設定登記 (債権額に課税) | 住宅ローン等、不動産を担保とするための登記 | 0.4% | 0.1% (令和9年3月31日まで) |
なお、軽減措置を受けるには、取得する住宅用家屋の床面積が50㎡以上であることなど、一定の要件を満たした証明書の提出が必要な場合があります。
住み替えでは、複数の登記が必要になるケースが多いため、事前に費用を確認しておきましょう。
参照:国税庁「登録免許税の税額表」
参照:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
印紙税
売却時と同様に、不動産の購入時にも印紙税が必要です。不動産売買契約書や工事請負契約書など、それぞれ一定額を超えた書類は印紙税の軽減措置が適用されます。
しかし、住宅ローンの契約書など、不動産売買契約とは直接関係のない書類は、軽減税率の対象から外れる場合もあるため注意が必要です。
参照:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
消費税
住み替えで不動産を購入する際は、不動産の売り主によって消費税が発生します。
売り主が個人の場合は、資産を譲渡したとみなされ、建物に消費税はかかりません。一方、売り主が不動産会社などの事業者であれば、事業に付随して対価を得ておこなわれる資産の譲渡にあたるため、消費税が課税されます。
また、土地は消費財産ではないことから、売り主が誰であっても消費税はかかりません。
参照:国税庁「No.6931 消費税等と譲渡所得」
参照:国税庁「No.6201 非課税となる取引」
住み替えで利用できる5つの特例制度
住み替えでの不動産の売買では、さまざまな税金がかかります。しかし、特例制度を活用すれば、支払う税金を減らすことが可能です。
ここでは、住み替えで利用できる特例制度の内容と適用条件を解説します。
3,000万円の特別控除
マイホームの売却によって利益を得た場合、特別控除の特例を活用すれば、譲渡所得を3,000万円まで控除が可能です。
3,000万円の特別控除を活用するための、主な要件を以下に抜粋します。
- 自分が住んでいる(または最近まで住んでいた)マイホームである
- 家屋を取り壊して売却する場合は、「取り壊しから1年以内の締結」かつ「取り壊し後に他の用途に使っていない」こと
- 売却相手が親子・夫婦・生計を同一にする親族などの「特別な関係」にない
- 売却の前年および前々年に、この3,000万円の特別控除の特例や損益通算および繰越控除の特例を受けていない
ただし、3,000万円の特別控除を受けると、住宅ローン控除が一定期間利用できなくなる場合があるため、どちらが有利かを比較検討する必要があります。
参照:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
軽減税率の特例
軽減税率の特例は、10年以上所有したマイホームを売却する際に、譲渡所得の税率が軽減される制度です。
軽減税率の特例は3,000万円の特別控除と併用が可能です。3,000万円の特別控除後の金額で6,000万円以下の部分が軽減税率の対象となります。
譲渡所得額と特例後の税率は以下のとおりです。(※1)
| 譲渡所得金額 | 合計税率(※2) |
| 6,000万円以下の部分 | 14.21% (所得税10.21% + 住民税4%) |
| 6,000万円を超える部分 | 20.315% (所得税15.315% + 住民税5%) |
軽減税率の特例を受けるための要件を以下に抜粋します。(※1)
- 売却する年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている
- 自分が住んで居住している(または最近まで住んでいた)マイホームである
- 売却相手が親子・夫婦・生計を同一にする親族などの「特別な関係」にない
- 売却の前年および前々年に、この特例の適用を受けていない
ただし、3,000万円の特別控除と同様に、この軽減税率の特例を適用すると、住宅ローン控除が受けられなくなる場合があるため注意が必要です。
(※1)参照:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
(※2)復興特別所得税として所得税に2.1%を上乗せして計算しています。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、新築住宅購入から最長13年間、中古住宅で最長10年間にわたり、住宅ローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。
住宅ローン控除できる借入限度額は、新築の認定住宅で最大5,000万円まで、中古住宅で最大3,000万円までが控除の対象となります。
以下、住宅ローン控除を受けるための主な要件を抜粋しました。
- 引渡しから6ヵ月以内に入居している
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である
- 住宅ローンの借入期間が10年以上ある
- 床面積が50㎡以上ある
住宅ローン控除は、売却時に受けられる譲渡所得の3,000万円の特別控除と併用できません。売却益からどちらの制度を活用したほうがお得か比較する必要があります。
参照:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国税庁「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
特定居住用財産の買い替え特例
特定居住用財産の買い替え特例とは、マイホームの売却によって利益が出た場合は、譲渡所得税を支払う必要があります。しかし、本来納税すべき譲渡所得税を、将来購入したマイホームを譲渡するときまで繰り延べられる制度です。
買い替え特例を受けるための代表的な要件を、以下に抜粋しました。
- 売却した年の1月1日時点で、居住期間・所有期間ともに10年を超えている
- 売却価格が1億円以下である
- 売却相手が親子・夫婦・生計を同一にする親族などの「特別な関係」にない
買い替え特例制度は、あくまで納税を繰り延べているだけで税金の支払いが不要になったわけではありません。また、譲渡所得の3,000万円の特別控除や軽減税率の特例など、その他特例と併用できないケースがあるため、注意が必要です。
参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
売却で利益が出ない場合の損益通算
住み替えのためにマイホームを売却し、売却額が購入時より低く損失が出た場合、その損失は給与所得や事業所得などと相殺できます。これを「損益通算」といい、課税対象となる所得を減らせることで、所得税や住民税の負担軽減が可能です。
また、譲渡損失が大きく、その年だけで控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できます。
損失が出た場合は確定申告の義務はありませんが、損益通算や繰越控除を受けるためには確定申告が必要です。
参照:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
住み替えで失敗しないために専門家へ相談しよう
住み替えは、マイホームの売却や購入、引っ越しの準備などを限られた期間で同時に進める必要があるうえ、法律や税金の知識も求められます。人生で何度も経験することではないため、判断に迷う場面も少なくありません。
また、税制上の特例や手続きの漏れがあると、想定外の出費もあるでしょう。このような事態を避けるためにも、まずは、不動産や税金に詳しい専門家に相談するのが有効です。
専門家のサポートを受けることで状況に合ったアドバイスが得られ、スムーズな住み替えが可能になり、不要な支出を抑えることにもつながるでしょう。
まとめ
マイホームの住み替えでは、売却や購入の際にさまざまな税金が発生します。譲渡所得税や不動産取得税をはじめ、印紙税や登録免許税などの費用が必要となるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
一方で、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例、住宅ローン控除など、税負担を軽減できる制度も複数用意されています。条件が合えば大きな節税につながるため、自身が該当する特例があるかどうか、事前に確認しておきましょう。
「ラクいえ売却」は、豊富な実績を活かして、住み替えによる不動産売却のお悩みを解決します。さらに、マイホーム売却後も1年間は賃料無料で住み続けられるサービスによって、ゆとりある新居探しが可能です。
まずは無料査定で、マイホームの価値を知ることから始めてみましょう。