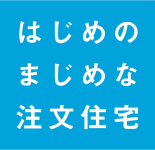住宅ローン控除は、以前に控除を受けたことがある方でも条件を満たしていれば住み替え時に利用できます。ただし、適用条件は住宅の種類によって異なり、併用できない特例もあるため注意が必要です。
この記事では、住宅ローン控除の制度内容や適用条件、ほかの特例との併用などを解説します。家の買い替えで住宅ローン控除の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
INDEX
住宅ローン控除の制度内容
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得または増改築した場合に所得税が控除される制度です。住宅ローン減税と呼ばれることもありますが、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローン控除の適用期間は、新築が最大13年間、中古住宅が最大10年間です。
控除対象となった場合、「年末の住宅ローン残高×0.7%(控除額の上限あり)」が所得税から控除されます。所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から残りの控除額が差し引かれます(前年度の課税総所得金額等の5%、上限9万7,500円)。
参照:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国土交通省「住宅ローン減税」
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
参照:総務省「新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。」
住宅の種類別の最大控除額
住宅ローン控除の対象となるローンの借入限度額や税金の最大控除額は、新築や中古住宅だけでなく、家の省エネ性能によっても異なります。また、制度内容は適宜変更されているため、1回目に利用したときとは条件が異なる場合もあります。
2025年に住宅ローン控除の適用を受ける場合、各住宅の限度額は以下のとおりです。
【新築・買取再販住宅(※1)】
| 住宅区分 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
| 年間 | 合計 | ||||
| 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 | 4,500万円 (5,000万円※2) |
0.7% | 13年 | 31.5万円(35万円※2) | 409.5万円(455万円※2) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 (4,500万円※2) |
24.5万円(31.5万円※2) | 318.5万円(409.5万円※2) | ||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 (4,000万円※2) |
21万円(28万円※2) | 273万円(364万円※2) | ||
| その他の住宅(※3) | 0円 | ー | ー | ー | |
(※1)宅建業者が特定の増改築などをおこなった家屋のことです。
(※2)以下のいずれかに該当する子育て世帯・若者夫婦世帯が対象です。
- 19歳未満の子どもがいる
- 夫婦のいずれかが40歳未満
(※3) 2023年12月31日までに建築確認を受けている、または2024年6月30日までに建築が完了している住宅は、借入限度額2,000万円、年間最大控除額14万円(10年間)が適用されます。
【中古住宅】
| 住宅区分 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額 | |
| 年間 | 合計 | ||||
| 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 10年 | 21万円 | 210万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 | ||
令和4年度税制改正により、2024年1月以降に建築確認を受けた新築に関しては、住宅ローン控除を受けるために省エネ基準を満たす必要があります。
また、省エネ性能や世帯に応じて控除の対象となる借入限度額は異なります。
例えば、一般世帯の方が「省エネ基準適合住宅」を5,000万円のローンで購入した場合、控除対象となるのは借入限度額である3,000万円までです。この金額に控除率0.7%をかけた21万円が1年目の控除額となります。
このように、住宅ローン控除が適用される金額を事前に確認しておくことが重要です。
一方で、中古住宅に関しては省エネ基準に達していない住宅の場合でも、所定の要件を満たしていれば控除を受けられます。
参照:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
参照:国税庁「No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国土交通省「住宅ローン減税」
参照:国土交通省「住宅の供給に携わる事業者の皆様へ」
住み替えでも条件を満たせば2度目の住宅ローン控除を利用できる
住み替えの場合でも、条件を満たせば2度目の住宅ローン控除が適用されます。
ここでは、住宅ローン控除の適用条件を項目ごとに紹介します。
居住要件
住宅ローン控除を利用するには、住宅取得後6ヵ月以内に入居し、継続して居住している必要があります。別荘や賃貸用住宅など、自身が継続して住まない家は対象外です。
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
住宅要件
住宅ローン控除の住宅要件は、新築と買取再販住宅・中古住宅で以下のように異なります。
【新築】
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(※)
- 床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
- 書類で省エネ性能が証明されていること
(※)家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(2025年12月31日までに建築確認を受けたもの)の場合、控除を受ける年の所得が1,000万円以下の方が対象となります。
【買取再販住宅・中古住宅】
- 家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
- 床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
- 使用された家屋であること
- 以下のいずれかに当てはまる家屋であること
- 1982年1月1日以降に新築されたもの
- 取得日前2年以内に耐震住宅と証明されたもの
- 取得日までに耐震改修を実施すると申請し、居住日までに耐震住宅と証明されたもの
- (買取再販住宅の場合)宅建業者が特定の増改築などをおこなった家屋を取得し、新築から10年経過したものであること
買取再販住宅や中古住宅で住宅ローン控除を適用する場合、床面積が必ず50㎡以上でなければならない点に注意しましょう。
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
参照:国土交通省「住宅ローン減税」
所得要件
住宅ローン控除は、控除を受ける年に所得2,000万円以下の方が対象です。
例外として、2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅で、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、所得1,000万円以下が所得要件となります。
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
参照:国土交通省「住宅ローン減税」
住宅ローン返済期間の要件
住宅ローン控除の対象となるには、住宅ローンの返済期間が10年以上でなければなりません。
繰上げ返済によって返済期間が10年未満となった場合は控除を受けられなくなるため、利息負担額と控除額を考慮した返済計画を立てることが重要です。
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」参照:国税庁「繰上返済等をした場合の償還期間」
特例との併用要件
住宅ローン控除以外にも、住宅の売却や買い替え時に利用できる特例があります。
ただし、なかには住宅ローン控除と併用できないものもあるため、事前に利用する特例を検討することが大切です。
参照:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
住み替え時に住宅ローン控除と併用できない特例
ここでは、住宅ローン控除と併用できない3つの特例を紹介します。それぞれの内容と適用条件を確認しましょう。
3,000万円特別控除の特例
「3,000万円特別控除の特例」とは、マイホームを売却した際に譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。
主な適用条件は、以下のとおりです。
- 居住中の家屋であること
- 売却年の前年や前々年にこの特例を受けていないこと
- 親子や夫婦などに対して売ったものでないこと
不動産売却時の利益を「譲渡所得」といい、その金額に応じて税金を支払う必要があります。しかし、この特例を利用することで譲渡所得が控除されるため、家の売却時の税負担を軽減できます。
例えば、3,000万円の譲渡所得が発生した場合でも、特例を利用すると3,000万円が控除されて譲渡所得が0円となり、税金はかかりません。
所有期間5年超の住宅の場合、譲渡所得には通常20.315%(※)の税率が適用されるため、約609万円の税負担がなくなると考えると、節税効果の大きい特例といえます。
(※)2013年から2037年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加算されています。
参照:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
10年超所有軽減税率の特例
「10年超所有軽減税率の特例」とは、マイホームの売却時に所有期間が10年超の場合、譲渡所得の税率が軽減される特例です。
適用条件は、居住用財産の所有期間が10年超に指定されている点を除けば、3,000万円特別控除の特例と大差ありません。
また、3,000万円特別控除の特例との併用も可能なため、仮に譲渡所得が4,000万円発生した場合、3,000万円控除したあとの1,000万円が軽減税率の対象です。
特例対象となると、6,000万円以下の譲渡所得に対して以下の軽減税率が適用されます。
| 譲渡所得6,000万円以下 | 譲渡所得6,000万円超 | ||
| 6,000万円以下の部分 | 6,000万円超の部分 | ||
| 所得税 | 10.21%(※) | 10.21%(※) | 15.315%(※) |
| 住民税 | 4% | 4% | 5% |
| 合計 | 14.21% | 14.21% | 20.315% |
(※)2013年から2037年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加算されています。
譲渡所得の合計額が6,000万円を超える場合でも、6,000万円以下の部分に関しては軽減税率が適用されます。
参照:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
特定居住用財産の買換え特例
「特定居住用財産の買換え特例」とは、マイホームを売却して家を買い替えた場合に、売却益に対する課税を将来に持ち越せる特例です。
主な適用条件は以下のとおりです。
- 売却価格が1億円以下であること
- 売却年の前年から翌年までの3年の間に家を買い換えること
- 買い換える建物の床面積が50㎡以上で、土地の面積が500㎡以下であること
通常、住宅を売却して譲渡益が発生した場合、その年度の確定申告で譲渡所得税を納める必要があります。この特例を利用することで、新居の売却時に納税すれば良いため、一時的に支出を抑えられます。
ただし、将来的に支払う必要があるので、納税額が軽減されるわけではありません。また、3,000万円特別控除の特例や10年超所有軽減税率の特例と併用できない点にも注意が必要です。
参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
住み替え時に住宅ローン控除と譲渡損失の損益通算は併用できる
住み替え時に住宅ローン控除と併用できない特例がある一方で、併用できる制度として「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」があります。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは、マイホームを売却して新居を購入し譲渡損失が発生した場合に、その損失を所得控除(損益通算)できる特例です。
主な適用条件は以下のとおりです。
- 売却年の1月1日時点で、家の所有期間が5年を超えていること
- 譲渡年の前年の1月1日から売却年の翌年12月31日までの間に、床面積50㎡以上の家屋を取得すること
- 新居取得年の翌年12月31日までに、居住用として使用または使用の見込みがあること
通常、不動産の譲渡損失は他の所得と損益通算できませんが、この特例を適用すれば所得税の負担軽減が期待できます。損益通算をおこなっても控除しきれない場合は、売却年の翌年以降3年以内に繰り越し控除することも可能です。
参照:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
参照:国税庁「No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」
住宅ローン控除と3,000万円特別控除はどちらを使う?シミュレーションで比較
住宅ローン控除と3,000万円特別控除の特例は節税効果が大きい制度ですが、どちらか一方しか利用できません。
ここでは、以下の条件でどちらの制度がお得になるのかを確認しましょう。
【売却物件】
- 売却価格:4,000万円
- 取得費:2,000万円
- 譲渡費用:160万円
- 所有期間:20年
【新居】
- 購入価格:5,000万円
- 住宅ローンの借入金:3,500万円
- 借入期間:30年
- 住宅の区分:ZEH水準省エネ住宅
この場合の譲渡所得は、以下のように計算できます。
譲渡所得
=売却価格-(取得費+譲渡費用)
=4,000万円-(2,000万円+160万円)
=1,840万円
売却物件の所有期間は20年で、長期譲渡所得に該当するため、課税額は次のとおりです。
1,840万円×20.315%(※)=約374万円
(※)2013年から2037年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%が加算されています。
この際、3,000万円特別控除の特例を適用すると、譲渡所得の1,840万円が全額控除されるため、約374万円の税負担がなくなります。
一方、住宅ローン控除を利用する場合は、年末借入金残高の0.7%の控除を13年間受けられます。
ZEH水準省エネ住宅の場合、最大控除額は年間24.5万円、合計で318.5万円です。ただし、実際には住宅ローン残高の0.7%が控除され、毎年ローン残高は減少していくので、控除額はさらに少なくなります。
したがって、今回の条件においては3,000万円特別控除の特例のほうが、節税効果が大きいといえるでしょう。お得になる制度は条件によって変わるため、実際の売却物件や購入物件を踏まえて慎重に判断することが重要です。
ご自身で判断が難しい場合は、不動産会社への相談がおすすめです。例えば、一建設では住み替え支援に特化した不動産買取サービス「ラクいえ売却」を提供しています。
「なるべく費用を抑えて理想の家に住み替えたい」「資金計画に不安を感じる」といった、住み替えを進めるうえでのお悩みにもお答えします。
住み替えに関する知識や経験が豊富なスタッフが対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
参照:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
住み替えで住宅ローン控除を利用する際の手続き
住宅ローン控除を利用する場合、所定の手続きをおこなう必要があります。
ここでは、住宅ローン控除の利用初年度と2年目以降に分けて、必要な書類や手続きの方法を解説します。
1年目は確定申告が必要
住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告が必要です。新居を購入し入居した翌年の2月中旬から3月中旬に、必要書類を税務署へ提出しなければなりません。
新築で住宅ローン控除を利用する場合、以下の書類を提出します。
| 必要書類 | 入手方法 |
| 確定申告書 | 国税庁ホームページ、税務署 |
| 本人確認書類の提示または写しの添付 | ー |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁ホームページ、税務署 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関から送付される |
| 登記事項証明書(※) | 法務局 |
| 工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し | 不動産会社との締結時に交付される |
| 住宅の省エネ性能を証明する書類 | 各書類で異なる |
(※)計算明細書への不動産番号の記載または登記事項証明書の写しの添付に代替できます。
このほか、国から補助金を受ける場合などは別途書類が必要です。
参照:国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
参照:国税庁「【確定申告・還付申告】」
参照:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」
参照:法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」
給与所得者は2年目から年末調整で手続きが完了
給与所得者(年収2,000万円以下)の場合、住宅ローン控除の申請2年目以降は確定申告が不要です。
以下の書類に必要事項を記入し、年末調整の書類に添付して勤務先に提出するだけで手続きは完了します。
| 必要書類 | 入手方法 |
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 税務署から送付される |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 金融機関から送付される |
一方、自営業などの給与所得者以外の方の場合は、2年目以降も確定申告をおこなう必要があります。
参照:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
参照:国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
まとめ
住宅ローン控除は、利用回数の制限がありません。そのため、条件に当てはまる方であれば、住み替えで2件目の家をローンで購入する場合でも、必要な手続きをおこなうことで控除を受けられます。
ただし、住宅ローン控除と併用できない特例があるため、どちらがお得になるかを見極めることが大切です。また、住み替えでは家の売却と新居探しの両者を進める必要があり、思うように手続きが進まないケースもあります。
費用と時間に余裕を持ち、理想の条件に当てはまる新居を見つけたい方には「ラクいえ売却」の利用がおすすめです。ラクいえ売却では、自宅を適正価格で素早く資金化できるだけでなく、売却後も賃料無料で1年間住み続けられます。
無料住み替えシミュレーションも実施しているため、まずはお気軽にご連絡ください。