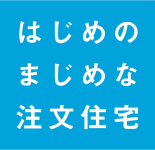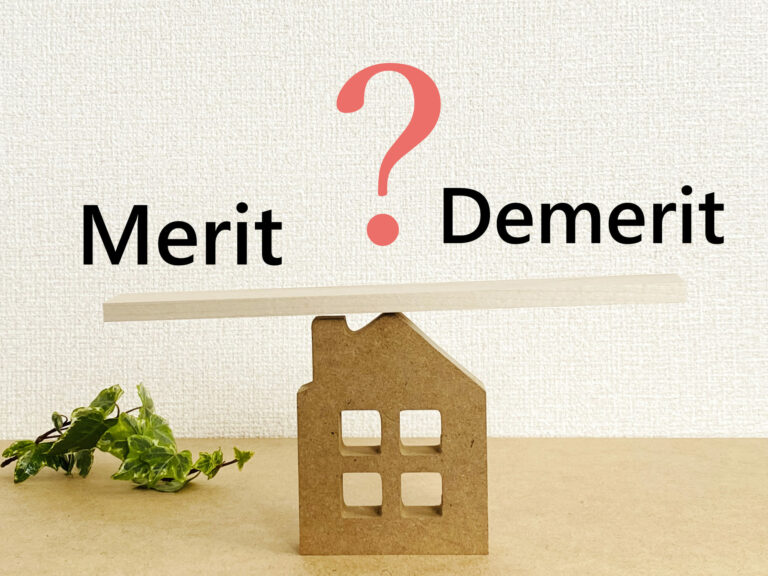不動産の買い替えを検討する際、税金への不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
不動産の買い替えでは売却と購入の両方で税金が発生しますが、適切な特例制度を活用することで節税につながる可能性があります。3,000万円特別控除や、買い替え特例を正しく理解すれば、大幅に税負担を軽減できるケースもあります。
この記事では、不動産の買い替えでかかる7つの税金と、節税が期待できる4つの特例制度を解説するため、ぜひ参考にしてください。
不動産買い替え時にかかる7つの税金
不動産の買い替えでは、住まいの売却と購入でさまざまな税金が発生します。ここでは、税金の種類と内容を確認していきましょう。
売却時にかかる3つの税金
現在の住まいを売却する際には、主に3つの税金が発生します。
譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産売却で得た利益に対して課税される税金です。売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に税率をかけて計算されます。
| 種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計 |
| 長期譲渡所得 | 5年以上 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
例えば、10年前に3,000万円で購入した物件を4,000万円で売却し、諸費用が200万円かかった場合の譲渡所得税は次のとおりです。
譲渡所得:4,000万円 − (3,000万円 + 200万円) = 800万円
税額:800万円 × 20.315% = 162万5,200円
上記の場合は譲渡所得が800万円で、税額は合計162万5,200円になります。譲渡所得税は所有期間や費用により税額が変動するため、事前に計算しておくと安心です。
参照:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
参照:国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」
参照:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」
印紙税
不動産売買契約書に貼付する収入印紙代として支払う税金です。印紙税の税額は以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減税額 |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
契約書に記載された売買金額に応じて税額が決まります。
令和9年3月31日までに作成された契約書は、軽減措置が適用される場合があります。軽減措置の適用は契約金額によって異なるため、確認が必要です。
また、印紙の貼り忘れや金額不足があると、過怠税が課される恐れがあるため注意しましょう。
参照:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
参照:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
登録免許税
住宅ローンが残っている不動産を売却する際の抵当権抹消登記にかかる税金です。
抵当権1件につき1,000円で、土地と建物にそれぞれ抵当権が設定されている場合は2,000円かかります。
また、登記申請は司法書士に依頼するのが一般的で、その場合は報酬として別途1万~2万円程度の費用がかかります。
参照:法務局「登録免許税の計算」
購入時にかかる4つの税金
不動産の購入時には、主に4つの税金がかかる可能性があります。
印紙税
不動産の売却時と同じように、購入時にも印紙税が必要です。不動産売買契約書や工事請負契約書などは、一定額以上で印紙税の軽減措置対象となります。
ただし、住宅ローン契約書など不動産売買と直接関係のない書類は、軽減税率の対象外となる可能性があるため注意が必要です。
近年普及している電子契約では、印紙税は不要とされています。しかし、金融機関によって対応状況が異なるため、事前に確認しましょう。
参照:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
登録免許税
所有権移転登記や抵当権設定登記の際に課税される税金です。固定資産税評価額に税率をかけて計算します。
また、条件を満たせば以下のような軽減税率が適用されます。
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 所有権移転(土地) | 2.0% | 1.5%(令和8年3月31日まで) |
| 所有権移転(建物) | 2.0% | 0.3%(令和9年3月31日まで) |
| 所有権保存登記(建物) | 0.4% | 0.15%(令和9年3月31日まで) |
| 抵当権設定 | 0.4% | 0.1%(令和9年3月31日まで) |
参照:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
例えば、評価額が2,000万円の住宅で軽減措置を受けた場合、所有権移転登記の登録免許税は以下のように計算されます。
所有権移転登記(建物):2,000万円 × 0.3% = 6万円
不動産の買い替えでは、複数の登記が必要になるケースが多いため、事前に費用を確認しておきましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県が課税する地方税です。本則税率は4%ですが、住宅と住宅用土地は令和9年3月31日までの軽減措置で3%となります。
新築住宅は床面積50㎡以上240㎡以下なら1,200万円控除、住宅用土地も大幅な軽減があるため、多くの一般的な住宅では実質非課税となるケースが多いです。
購入から約半年〜1年後に納税通知書が届くため、納付忘れにご注意ください。
参照:総務省「不動産取得税」
参照:国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」
消費税
新築住宅の建物部分には、10%の消費税がかかります。土地は「消費」するものではなく「資本の移転」とみなされるため、消費税は非課税です。
個人間の中古住宅売買では売り主が課税事業者でないため、消費税はかかりません。ただし、不動産会社が売り主の物件や仲介手数料には消費税がかかります。
不動産買い替えの税金を抑える4つの特例制度
不動産の買い替えでは、税負担を軽減できるさまざまな特例制度があります。
ここでは、主な特例制度を4つ解説します。
3,000万円の特別控除
居住用財産の売却時に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。この特例は、マイホームとして実際に住んでいた物件が対象で、住まなくなってから3年目の年末までに売却する必要があります。
親族間取引や、過去2年以内にこの特例を利用している場合は適用できません。売却益が3,000万円以下なら譲渡所得税は非課税となるため、税負担を大幅に軽減できます。
ただし、住宅ローン控除や買い替え特例との併用はできないため、それぞれのメリットを比較して判断しましょう。
たとえ税金が発生しない場合でも確定申告が必要なため、忘れないようにしてください。
特定居住用財産の買い替え特例
正式名称は「特定の居住用財産の買換えの特例」で、譲渡所得税の支払いを将来に繰り延べる制度です。
税額が免除されるわけではなく、買い替え後の物件を売却する際にまとめて課税されます。
所有期間・居住期間ともに10年以上など、いくつか要件があり、新居の購入価格が売却価格以上でなければなりません。
特例を利用することで税金が免除されるわけではなく、あくまで納税のタイミングが変更されるだけのため、今後を見越した資金計画が重要です。
参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
10年超所有による軽減税率
所有期間10年超の居住用財産を売却した際に適用される軽減税率の特例です。
| 課税長期譲渡所得の区分 | 税率(所得税 + 住民税 + 復興税) |
| 6,000万円以下の部分 | 14.21%(所得税10.21% + 住民税4%) |
| 6,000万円を超える部分 | 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%) |
参照:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
また、10年超所有による軽減税率は、3,000万円特別控除との併用が可能です。例えば、売却益が8,000万円なら、3,000万円控除後の5,000万円に14.21%の税率が適用されます。
所有期間の判定は、売却年の1月1日時点でおこなわれるため、取得時期の確認が重要です。上手に利用すれば、大幅な税金の節約につながる可能性があるでしょう。
譲渡損失の損益通算・繰越控除
不動産の売却で出た損失を、給与所得などから差し引いて税負担を軽減できる制度です。買い替えの有無に関わらず、損失を他の所得から差し引いて所得税・住民税を軽減できます。
控除しきれなかった損失は翌年から3年間繰り越すことができ、合計4年間にわたって控除を受けられます。適用には確定申告が必要ですが、住宅ローン控除との併用が可能です。
ただし、令和7年12月31日までの譲渡が適用期限となっているため、売却時期に注意しましょう。損失の繰越期間中は毎年、確定申告を継続する必要があります。
不動産買い替えで税金の特例を利用する際の注意点
節税効果の高い特例制度ですが、適用条件を正しく理解していないと利用できない場合があります。
ここからは、不動産の買い替えで特例を利用する際の注意点を見ていきましょう。
特例には非適用ケースがある
3,000万円特別控除は多くの方が利用できる制度ですが、条件を満たさないケースも存在します。適用されないケースは以下のとおりです。
- 親子や夫婦など親族間での売買
- 住宅ローン控除や買い替え特例との併用
- 特例を利用する目的で取得した物件
- 確定申告の未実施
親子や夫婦など親族間での売買では適用されず、生計をともにする家族への売却も対象外です。
住宅ローン控除や買い替え特例とは併用できないため、どちらが有利かを事前に比較・検討する必要があります。別荘や投資用物件など、この特例を利用する目的で取得した物件は居住用財産と認められません。
また、確定申告をしないと控除は受けられず、申告を忘れると節税のチャンスを逃すことになります。適用条件を確認し、条件を満たしていることを確認してから売却を進めましょう。
買い替え特例は支払いの先送りであって免除ではない
買い替え特例は「税金が免除される制度」ではなく「将来に繰り延べる制度」という点で大きな誤解が生じやすい制度です。買い替え特例を利用すると、譲渡所得税の支払いを次回売却時まで先送りできますが、将来的に物件を手放す際には繰り延べた税金も含めて課税されます。
また、買い替え特例は3,000万円特別控除との併用ができないため、一時的な資金負担の軽減を取るか、実質的な節税効果を取るかの選択が必要です。
さらに、所有期間・居住期間10年以上や買い替え先の条件など、いくつかの要件を満たす必要があります。将来的な売却の見通しや資金の流れを考慮し、慎重に制度の利用を判断しましょう。
参照:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
まとめ
不動産の買い替えでは、売却や購入時にさまざまな税金が発生しますが、3,000万円特別控除や買い替え特例、軽減税率などの特例制度を活用すれば大幅な節税が期待できます。
特例制度の特徴はそれぞれ異なるため、将来設計や資金状況に合わせて使い分けることが重要です。
住み替えをお考えなら、税金の不安も含めてゆとりを持って新居選びができる「ラクいえ売却」がおすすめです。売却後も無料で最長1年間住める制度があるため、焦って引っ越す必要はありません。
時間と気持ちに余裕を持って住み替えを始めたい方は「ラクいえ売却」で、新生活への準備を始めてみてはいかがでしょうか。