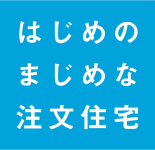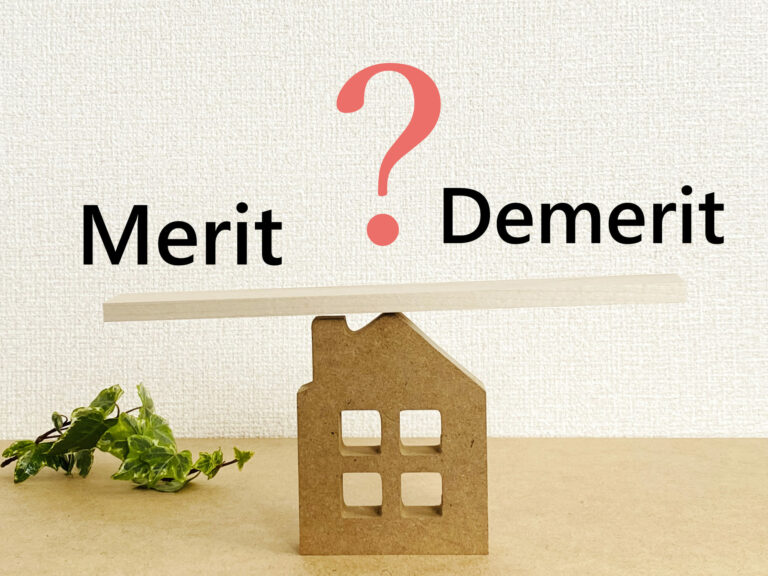住み替えは、新しい住まいを見つけるために今の家を売却する大きな決断です。しかし、どのタイミングで動くべきか、どんな費用がかかるのか、税金面での優遇措置など、さまざまな要素を考慮する必要があります。
この記事では、住み替えを検討している方に向けて、売却と購入の流れ、費用相場、税金の軽減措置など、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。住み替えをスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてみてください。
INDEX
住み替えとは?
住み替えとは、現在住んでいる住宅を売却して、別の住宅へ移ることを指します。住宅の購入と売却を同時に進めるため、資金計画やスケジュール調整が求められる複雑なプロセスです。近年では、人生100年時代とも言われる中で、ライフスタイルの変化に合わせて住環境を見直す人が増えており、「住み替え」は単なる引越しではなく、人生設計の一環として注目されています。
住み替えを検討する主な理由
住み替えを検討する背景には、実にさまざまな事情があります。
たとえば、結婚や出産によって家族が増え、より広い住まいを必要とするケースや、子どもが独立して部屋が余り始めたことで、コンパクトな住まいへ移るケースがあります。また、転勤などによる通勤時間の見直しも大きな理由です。老後に向けて階段のないバリアフリー住宅や、病院やスーパーが近い利便性の高いエリアへの移住を検討する人も増えています。
さらに、築年数が経過し資産価値が下がる前に売却し、資産を有効活用したいという目的も見逃せません。
住み替えには「売り先行」と「買い先行」がある
住み替えには、大きく分けて「売り先行」と「買い先行」という2つのアプローチがあります。「売り先行」は今の家を先に売却し、その資金を元手に新居を購入する方法。一方、「買い先行」は先に理想の住まいを購入し、その後に今の住まいを売却する方法です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
売り先行のメリットとデメリット
売り先行の最大のメリットは、資金計画が立てやすい点です。売却価格が確定するため、購入可能な価格帯が明確になり、無理のない資金計画が立てられます。
ただし、先に家を手放すため、新居の引渡しまでの間に仮住まいが必要になる可能性があり、引越しも2回必要となるケースがあります。このため、余計な手間と費用がかかることがあります。
売り先行の流れ
売り先行の場合の一般的な流れは以下の通りです。
1.不動産会社に売却の相談・査定依頼
最初のステップは、自分の住んでいる家の売却価格を把握することです。不動産会社に査定を依頼すると、専門の担当者が家の状態、立地、相場などを基に価格を算出します。この査定価格を参考にして、売却価格を決定します。査定を複数の不動産会社に依頼することで、価格の相場感を得ることができます。
2.売却活動の開始
売却価格が決まったら、実際に販売活動を開始します。物件の写真撮影や広告、オープンハウスの実施など、販売戦略を立てる必要があります。現地見学や内見が進む中で、購入希望者が現れることを期待します。販売活動の期間は物件によって異なりますが、相場や需要によって調整が必要なこともあります。
3.購入希望者との売買契約締結
購入希望者が現れ、交渉がまとまると、売却契約が成立します。この契約時に、売主と買主の間で引渡し日などを調整し、必要な手続きを進めます。売却契約が成立した後、物件の引渡しに向けた準備が整います。
4.新居の本格的な物件探し・購入契約
すでに現在の住まいの売却契約が成立した段階で、新居の購入活動が本格化します。住み替えの場合、購入する物件が決まった時点で、住宅ローンの審査を受けることが一般的です。また、購入する物件の条件や予算に合わせて物件選びを進めます。新居を見つけ、契約を結ぶと、購入手続きが完了します。
5.引越しおよび旧居の引渡し
売却契約の引渡し日と、新居の引渡し日が決まると、実際の引越し準備が始まります。新しい住まいが準備できたら、引越し業者を手配してスムーズに移動を行います。必要な家具や家電の搬入、旧居の掃除なども忘れずに行います。
買い先行のメリットとデメリット
一方で、買い先行のメリットは、時間をかけて希望に沿った物件を探せる点と、仮住まいを避けられる点です。家族の都合や転校などを最小限に抑えられるのも魅力です。
ただし、現住居のローンが残っている場合、新たに住宅ローンを組むことで二重ローンの状態になり、月々の返済が増えるリスクがあります。
買い先行の流れ
買い先行での住み替えは、以下のようなステップで進められます。
1.事前審査を依頼して購入可能額を確認
まずは自分が購入できる金額を確認するため、金融機関に事前審査を依頼します。住宅ローンの審査を通るかどうかを確かめることが、この段階のポイントです。事前審査に通ることで、購入時に大きな問題が発生しないように準備できます。
2.希望条件に合った新居を探し、購入契約を結ぶ
事前審査を通過したら、次に理想の物件を探し始めます。立地や広さ、間取り、予算に合った物件を見学し、決定します。購入前には必ず現地に足を運び、実際に内見をして、物件の状態や周辺環境も確認することが重要です。
3.購入契約を締結
購入物件が決まったら、売主と購入契約を交わします。この契約では、物件の価格、引渡し日、契約時期などをしっかりと確認しておきます。また、購入後に必要な諸費用(登記費用や手数料など)も考慮して、契約内容を把握しておくことが重要です。
4.新居の引渡しを受ける
購入契約後、金融機関と住宅ローンの契約を締結し、新居の引渡しを受けます。ローンの手続きが完了し、物件の引渡しを受けた時点で、購入手続きは完了します。新居に住む準備が整い、必要なインフラや家具を整えます。
5.現在の住まいの売却活動を開始
新居に引越しを完了した後は、現在住んでいる家の売却活動を開始します。物件の査定を依頼し、売却活動を始めます。この段階で、現住居が市場に出るため、しっかりと価格設定を行う必要があります。場合によっては、売却活動が長引くこともあるので、注意が必要です。
6.売却契約を締結し、引渡しを完了
現住居が売却されると、引渡しが行われます。買主に対する物件の引渡しや必要な書類の提出、支払いなどの最終手続きを進めます。この時点で、売却が完了し、住み替えが完了します。
ラクいえ売却なら…
「売る」と「買う」を別々に考えると、時間も手間もかかりがちです。、「ラクいえ売却」なら、住み替えの売却と新居購入をワンストップでサポートしてくれます。
家を売ってから買うのか、先に買ってから売るのか。状況に応じたスケジュール調整もプロが的確にアドバイスいたします。また、煩雑な手続きもまとめて任せられるので、初めての方でもスムーズに買い替え・住み替えが進められます。
住み替えのベストなタイミング
住み替えにおいて「いつ動くか」は非常に重要なポイントです。次のタイミングを意識して住み替えを検討しましょう。
家が値下がりする前
築年数が経過するごとに住宅の資産価値は下落していく傾向があります。特に築20年を超えると、売却価格が新築時の30%以上下落することも珍しくありません。市場の動向を見極めて、資産価値が高いうちに売却するのが得策です。
住宅ローン控除の期間終了後
住宅ローン控除は、最大13年間、所得税から一定額を控除できる制度です。これが終了したタイミングで住み替えを行うことで、税制上のメリットを十分に受けた上で新たな住環境に移行できます。
ライフイベントの節目
結婚、出産、子どもの入学や独立、さらには定年退職など、人生の大きな節目は住み替えの好機です。生活環境が変化するタイミングで家の見直しを行うと、長期的に快適な暮らしを実現しやすくなります。
住み替えにかかる費用の相場と内訳
住み替えには、売却と購入に関するさまざまな費用が発生します。これらの費用を事前に把握しておくことが、スムーズな住み替えを実現するためのカギとなります。以下では、住み替えにかかる費用の各項目ごとに簡単な説明と具体的な相場金額を紹介します。
持ち家の売却にかかる費用
住み替えをする際、現在住んでいる家を売却する必要があります。売却にはいくつかの費用がかかります。主な費用項目とその相場金額は以下の通りです。
| 費用項目 | 概要 | 相場金額 |
| 不動産仲介手数料 | 売却時に不動産業者に支払う手数料。 売却価格に応じて3.3%+6.6万円が相場です。 | 売却価格の3.3%+6.6万円(例:3,000万円の物件で約105万円) |
| 登記費用 | 売却に伴う登記手続きに必要な費用。 司法書士に依頼することが一般的です。 | 約2〜5万円 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙税。 契約金額に応じて決まります。 | 約1〜4万円 (契約金額による) |
| 引越し費用 | 売却後の引越しにかかる費用。 荷物量や距離によって異なります。 | 約5〜10万円 |
| リフォーム費用 | 売却前に住宅の価値を上げるためのリフォームが必要な場合の費用です。 | 数万円〜数百万円(物件の状態による) |
新しい家の購入にかかる費用
新しい家を購入する際にも、以下のようなさまざまな費用が発生します。
| 費用項目 | 概要 | 相場金額 |
| 不動産取得税 | 新居購入時にかかる税金。 購入価格の3%程度が相場です。 | 物件価格の3%前後(地域差あり) |
| 登記費用 | 所有権移転登記に必要な司法書士手数料です。 | 約3〜5万円 |
| 住宅ローン事務手数料 | 新居購入時に住宅ローンを組む場合、金融機関に支払う手数料です。 | 約3〜5万円 |
| 住宅ローン保証料 | 住宅ローンを借りる際に必要な保証料。 金融機関によって異なります。 | 約5〜10万円 |
| 火災保険料 | 住宅ローンを組んだ場合、必須となる火災保険にかかる費用です。 | 約2〜5万円 |
新築マンションの購入にのみかかる費用
新築マンションを購入する場合は、追加で下記の費用がかかります。
| 費用項目 | 概要 | 相場金額 |
| 修繕積立金 | 新築マンション購入時に必要な初期費用。 管理組合に支払う積立金です。 | 約5〜10万円 |
| 管理準備金 | 新築マンションにおいて、管理組合が運営を開始するために必要な準備金です。 | 約10〜30万円 |
| 建物保証料 | 新築マンションにかかる建物の保証に必要な費用です。 | 約5〜10万円 |
住み替えで利用できる税金の軽減措置
税金面でも住み替えには次のような軽減措置が用意されています。
3000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却して利益が出た場合でも、一定の条件を満たせば最大3,000万円までの譲渡所得が非課税になります。たとえば、5年以上住んでいた住宅を売却することや、家族以外への売却であることなどが条件です。
この制度を活用すれば、売却益に対する税負担を大幅に軽減でき、次の住まいへの資金計画にも大きく貢献します。
特定の住居用財産の買換え特例
この特例は、マイホームを売却して新たな住居を購入する場合、売却益に対する課税を一定条件のもとで将来に繰り延べられる制度です。
たとえば、旧居を売ってから1年以内に新居を購入するなど、所定の条件を満たす必要があります。住み替えによる資金繰りをスムーズにするための重要な税制優遇措置であり、適用の可否によっては税負担に大きな差が出ることもあります。
譲渡損失の損益通算・繰越控除
住み替えに際して、マイホームの売却で損失が出た場合には、その損失を他の所得(給与所得など)と相殺する「損益通算」が可能です。これにより、所得税の負担を軽減できます。
さらに、その年で控除しきれなかった損失が大きい場合は、翌年以降3年間にわたり繰越して控除する「繰越控除」も認められています。
住み替えを検討しているなら『ラクいえ売却』がおすすめ
住み替えは、人生の転機に合わせて新たな住環境を整える絶好のチャンスです。ただし、売却と購入、資金計画や税制まで幅広い知識が求められるため、しっかりとした準備と信頼できる専門家のサポートが不可欠です。自身のライフプランに最適なタイミングと方法を見極め、無理のない住み替え計画を立てましょう。